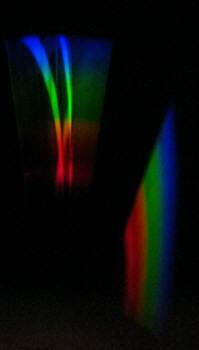私の肺も少し緑になるかも。
細い枝の先の先まで茂った葉が少しでも日の光を浴びようと工夫を凝らしています。
地面は草がぐんぐん伸び、
小道は緑に埋もれ、
太い幹に生えるシダやコケの緑も鮮やかさを増しています。



御苑の中の森の木々はいっそう力強く、堂々として、
命に満ち溢れて、歩きだしそうです。

太い枝はまるで脊椎動物の骨のよう、今にも腕を振り回しそうです。

幹に生えた羊歯に光があたってキラキラ輝いています。







「京都科学読み物研究会」の「やさしい自然教室」に参加して、
クモのエキスパート、吉田真さんの案内で
初めてセアカゴケグモに対面しました。
国際会議場前(宝が池)の地下鉄の出入り口の建物の周辺に何匹もいました。
まわりは整備された公園です。
セアカコケグモは主にそんなような明るい場所の、人工物に棲んでいます。
この場所では定期的に駆除を行っているそうです。
オーストラリアからやって来たセアカコケグモは、
どんどん分布を広げています。
「毒蜘蛛のいない日本」はもう戻らないのかもしれません。
これがセアカゴケグモの巣、食べ残しの餌(クモ)が巣の上に引っ掛かっています。
巣の左の方にセアカゴケグモが隠れています。
巣を壊して追い出したら出て来ました。これがセアカゴケグモです。
卵嚢と一緒にアルコール浸けにしています。
おとなしいクモなので素手でつかんだりしなければ噛みつくことはないそうですが、
知らなければうっかり触ってしまいそうなほど身近な所に居るのが困りものです。
普段見慣れた日本のクモとはずいぶん違う姿で、
真っ黒な丸い身体に強そうな長い手足、背と腹に真っ赤なストライブ、一度見ればもう忘れません。
かっこいいと思うか、毒々しいと思うか、
ただしそれはメスの姿、オスは目立たない茶色で、メスの4~5分の1くらいの大きさで、
毒も持っていないそうです。
分布が拡大しているので、子どもたちにもアルコール浸けのセアカゴケグモを見せて
覚えてもらうことも大事かなと思います。
2時間で、みんなでセアカゴケグモ他約20種のクモを見つけました。




庭にキクナの花が咲いています。
見ているると次々と点みたいに小さな虫が飛んで来ては花に留まります。
花の中で待ちかまえているのはクモ、
残念ながらピンボケだけど。
網にしても地面の穴にしてもクモは「待つ」ことがライフ・ワークのようです。

花びらを全部食べられて花芯だけになってしまったのもあるのですが、
その犯人は見当たりません。
花束を作りグラスに挿せば野菜の花とは思えない華やかさです。