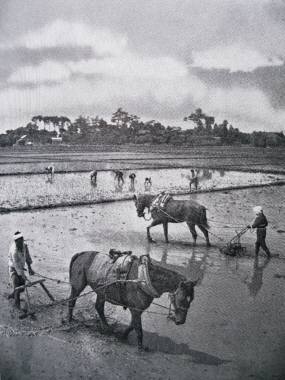昨日は滋賀県の近江八幡へ出かけました。
前から行きたかった、小さな美術館「ボーダレス・アートミュージアムNO-MA」にやっと行けました。
到着すると冷たい風がびゅんびゅん吹いていました。
「NO-MA」は昭和初期の古い民家を改装して作った素敵なミュージアムで、
細かなところまで気配りが見える見事な建物でした。
2階の一部屋には座卓と座布団が用意されていて
本棚にならんだアールブリュットの画集などをゆっくり眺めることができます。

開催中の展示は、滋賀県内の各福祉施設が合同で企画展示をしているものです。
「ing...障害のある人の進行形」と題されています。
今ではアールブリットもメジャーな存在となりました。
サバン症候群の人たちの驚異的な作品がテレビで紹介されたりして、
いろいろな形で私たちも眼にすることができるようになりました。
自分が気に入った作品を楽しめばいいのだと思いますが、
映画を見たり、実物をゆっくり見ていると、
精神の深淵、人の心の複雑さ、微妙なバランスなどなど、
いろいろなことを思う気持ちが心をよぎって時にはドキドキしてしまいます。
あたりが暗くなりかけた頃、雪がぱらつき始め、慌てて帰ってきました。
京都に入ると雪は時雨れになって、
風も無く空気の冷たさも違う感じがします。
すぐ近くなのに随分違うもんだと思いました。
でも、今朝起きると、庭に、顔の形みたいな氷が張っていました。

前から行きたかった、小さな美術館「ボーダレス・アートミュージアムNO-MA」にやっと行けました。
到着すると冷たい風がびゅんびゅん吹いていました。
「NO-MA」は昭和初期の古い民家を改装して作った素敵なミュージアムで、
細かなところまで気配りが見える見事な建物でした。
2階の一部屋には座卓と座布団が用意されていて
本棚にならんだアールブリュットの画集などをゆっくり眺めることができます。

開催中の展示は、滋賀県内の各福祉施設が合同で企画展示をしているものです。
「ing...障害のある人の進行形」と題されています。
今ではアールブリットもメジャーな存在となりました。
サバン症候群の人たちの驚異的な作品がテレビで紹介されたりして、
いろいろな形で私たちも眼にすることができるようになりました。
自分が気に入った作品を楽しめばいいのだと思いますが、
映画を見たり、実物をゆっくり見ていると、
精神の深淵、人の心の複雑さ、微妙なバランスなどなど、
いろいろなことを思う気持ちが心をよぎって時にはドキドキしてしまいます。
あたりが暗くなりかけた頃、雪がぱらつき始め、慌てて帰ってきました。
京都に入ると雪は時雨れになって、
風も無く空気の冷たさも違う感じがします。
すぐ近くなのに随分違うもんだと思いました。
でも、今朝起きると、庭に、顔の形みたいな氷が張っていました。