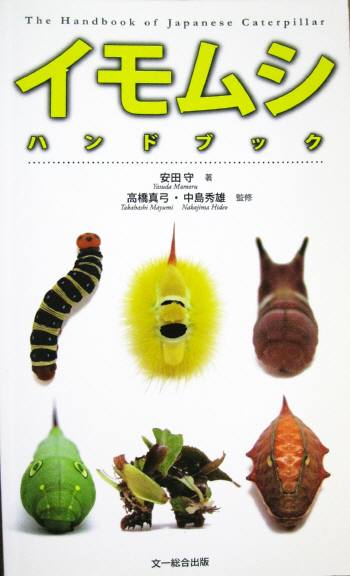京都の町屋では鍾馗(しょうき)さんをよく見かけます。
我が家にも有りましたが改築の際欠けてしまったので、
今は押し入れの中にしまってあります。
修学旅行生やツアーの人たちにガイドさんが、
「これはショウキさんと言って、沖縄のシーサーのようなもので、
家に悪いものが入ってこないように守っているのです。」
と説明をして歩いているのをよく見かけます。
すると、「へー、珍しいねー」と観光客が驚いているので、
私は、「へー、京都だけのものなんだ。」と思っていましたが、
調べてみれば関西地方の随分広い範囲にみられるもののようです。
一昨日、三重県の古い家にも見つけました。
ここは久居インターチェンジに近い小さな集落です。
京都でよく見かける鍾馗さんとは一味違う顔立ちです。
立ち姿も少し違います。
大きな古い瓦屋根や鬼瓦を観るのが好きですが、
維持するのは大変だろうなと思います。

この鍾馗さんのあった家は500坪強の敷地に母屋や農作業小屋、蚕のための様々な建物、さらに土蔵がありました。畑や庭には様々な木や花や野菜が植えてあって、おばあさんが一人で暮らしておられるようでした。
写真は上記の家の、通りに面している部分、蚕小屋だったそうです。中は普通の部屋に改造されていて、子どもたちが大人になるまでは子ども部屋になっていたようです。
こんな立派で巨大な家におばあさんがたった一人で住んでいる、というような状況が、
あっちにもこっちにもあって、
この先どうなるんだろうと気がかりです。