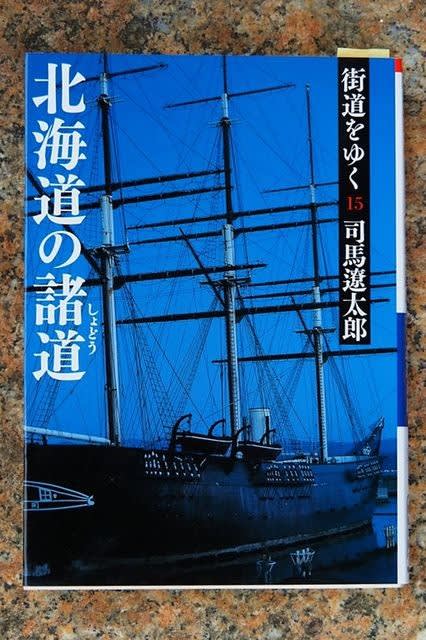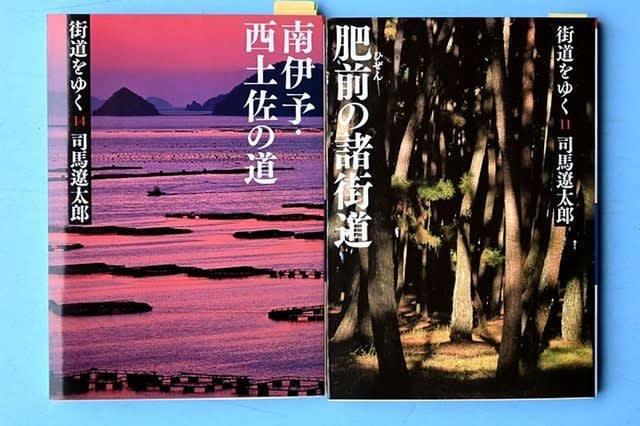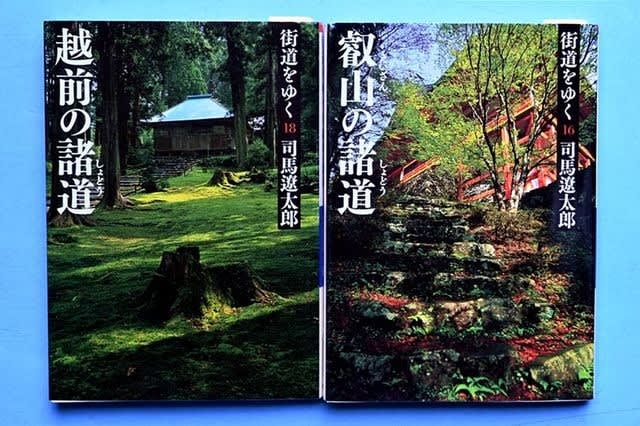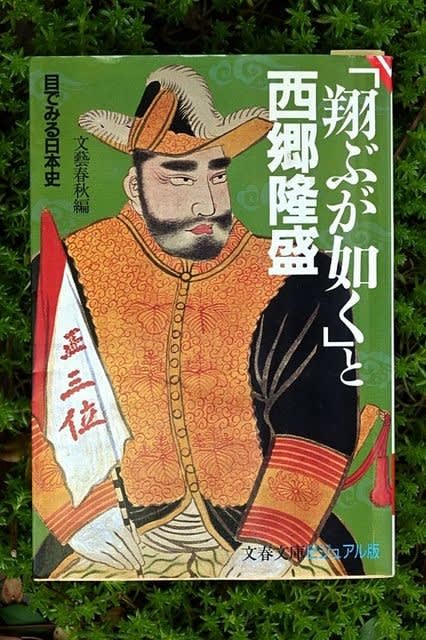(「別冊太陽」表紙 平凡社 2021年刊)
ウィキペディアを参照すると、
《半藤 一利(はんどう かずとし、1930年〈昭和5年〉5月21日 - 2021年〈令和3年〉1月12日)は、日本のジャーナリスト、戦史研究家、作家。近現代史、特に昭和史に関し人物論・史論を、対談・座談も含め多く刊行している。》
かなりのボリュームがある記事の冒頭はこのようにはじまっている。
ああそうだった。 . . . 本文を読む
はじめにごく私的な話をさせていただくと、平凡社ライブラリー版で読んだイザベラ・バードの「日本奥地紀行」こそ、わたしの紀行文学好きを決定づけた書物でありまする(´ω`*)
読んでから12年が経過し、記憶がうすれてきたので、半年ほど前から、再読をかんがえていた。
村上春樹の紀行文学を読み、司馬さんの「街道をゆく」を読む。
そういった作業のはじまりに、イザベラ・バードの「日本奥地紀行」があるのであります . . . 本文を読む
■「北海道の諸道」街道をゆく15 朝日文庫 2008年刊(原本は1979年「週刊朝日」連載)
途中で何週間か中断してしまった。すでに書いたように、中里恒子「時雨の記」という、映画および原作を読んで、頭の一部が地殻変動を起こした。
短いもの(20枚程度の短編のような)は読めたのだが、持続力を必要とする長いものはだめ。
心のある部分が浸水してしまい、その水がなかなか引いてくれなかった・・・とでもいっ . . . 本文を読む
■「湖西のみち、甲州街道、長州路ほか」(「街道をゆく」第1巻朝日文庫2008年版
本編のオリジナルというべき単行本は1971年に刊行されている。
「街道をゆく」はロングセラーなので、改版や新装版と銘打ったさまざまな版が存在する。
わたしは単行本(ハードカバー)をはじめ、この第1巻は数種の版が手許にある。
Topに掲げた文庫が最新版かと思っていたが、そうではないことに、半分ほど読んだところで気 . . . 本文を読む
■「甲賀と伊賀のみち、砂鉄のみち ほか」街道をゆく(朝日文庫)第7巻 「週刊朝日」連載1973年1974年1975年
「街道をゆく」を読みながら気になってきた本がある。
それは沢木耕太郎「深夜特急」である。
過去(40代の後半)に読みかけたことがあったけど、あえなく挫折。
沢木さんはノンフィクション作家、エッセイスト、小説家、写真家と、いろいろな横顔を持っておられる。
中でも「深夜特急」(mi . . . 本文を読む
■「壱岐・対馬の道」街道をゆく(朝日文庫) 第13巻 「週刊朝日」連載1978年
本編も司馬さんらしい観察眼が随所にただよっている。
なぜ「壱岐・対馬」へ出かけたのかが興味の焦点であった。司馬さんという人は、若いころから文明の“へり”(縁)に強く惹かれている。
だから大阪外語でモンゴル語を選択したのだ。
辺境ではないが、辺境に近い“へり”の地域が持っている、文化的な累積地層を眺め、虫眼鏡で観察す . . . 本文を読む
中途半端に土地があるから、この時期になると厄介である。
・草を刈る(草刈り機が3台ある)
・除草剤を散布する
・草を毟る
時間もかかるが、費用だってばかにならない。わたしは農業をしていないので、すべてムダな労力・ムダな出費である。
今日は草刈り機で桑の木を伐っていて、あっというまに右手薬指を傷つけてしまった。
長さ約10㎜、深さ約2㎜。シャワーを浴びたあと、傷口を洗い、アルコール消毒(ノω`* . . . 本文を読む
前回のレビューで少し書いたのでパスしようとかんがえていた。
しかし・・・しかしわたし的に面白すぎたので、簡単に感想を綴っておく気になった。
司馬遼太郎は私小説はまったく書かなかったが、己を露出しないのではない。
本編には、ためらったり、あせったり、気をもんだり、ひとをからかったりからかわれたり、そばに舌鼓を打ったり、書物の山を探索したり、インタビューしたり、バスに揺られたり、ベッドに横たわって叡山 . . . 本文を読む
(「越前の諸道」と「叡山の諸道」朝日文庫 現行版)
■「越前の諸道」新装版第一刷 1980~81年 「週刊朝日」連載
司馬遼太郎にはまりかけている、いまさらながら。
買うだけ買って手許にありながら、読めていない、読んでいない本がたくさんあるからだ。
しかも、さらに買ったり、平積みした蔵書を漁ったりしている(´ω`*) こういう現象を何といったらいいのか!?
まあ、定年退職したら司馬 . . . 本文を読む
(目で見る日本史『「翔ぶが如く」と西郷隆盛』文春文庫ビジュアル版 1989年刊)
昨夜遅く『「翔ぶが如く」と西郷隆盛』に収録された司馬さんのエッセイ「南方古俗と西郷の乱」を、ベッドの上で読んでいた。
《西郷という人は、高士であるにちがいない。
とくにかれは維新後、そうなった。高士とは儒教的済民意識と道教的な退隠哲学を混淆させ、蒸留させ、そこから滴ってくる精神のようなもので、中国人には . . . 本文を読む