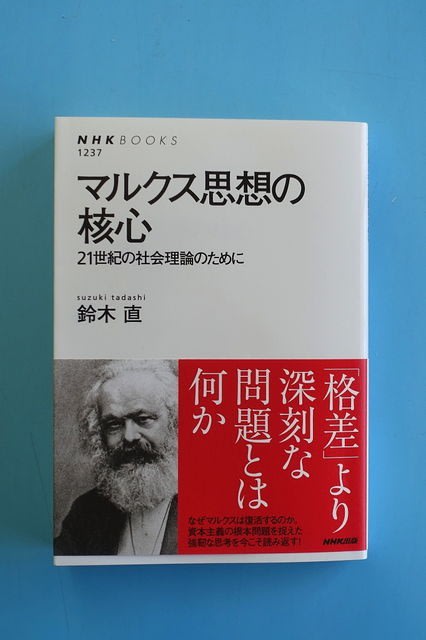
(昨夜この「マルクス思想の核心」を読みはじめた)
漫然と書籍の世界に耽溺しているようだけれど、わたしなり方向性ははっきりしている。
1.聖書(旧約・新約)を読む
2.プラトンまでさかのぼって、哲学書を読み、哲学史に理解を深める
3.その中から、デカルト、スピノザ、ニーチェなどと、フランスの「ポストモダン」といわれる一群の思想家について、ある程度の知見をもつ。
4.世界史に関する読書を継続していく。
5.ドストエフスキー、カフカを中心に、“世界文学”の古典を読み返し、さらに新しい作品にも挑戦!
こういった中にマルクス「資本論」もリストアップされている。
4-5日前に、岩波文庫の「資本論」を読みはじめたのだけど、やっぱり歯が立たずに挫折。
十代の終わりころから、こういう経験が過去に二度ある(ノ_・)。
「ドイツ・イデオロギー」と「共産党宣言」だけは二十歳のころにあらかた読んだけれど、理解できたかどうかは別問題であ~る。
岩波版の資本論も、訳がかなり古めかしいので、新訳版を買えばいいのだけど、
大きく重く、高価なので、躊躇しているのだ。
新訳を買って取り組んでも、途中でギブアップしてしまう危惧が多分にあるから・・・。
マルクス、資本論をキーワードにネット検索すると、膨大な情報がダダーと現れて、つい怖気づく。
まあ、そんなことをいっていたら、一生わからないまま・・・。
したがって、まず外濠を埋めるつもりで、たくさんの本を仕入れた。
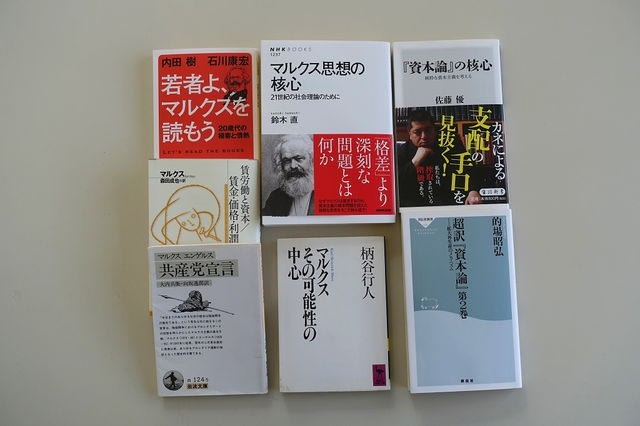
昨夜、NHK・BOOKSの鈴木直さんの「マルクス思想の核心――21世紀の社会理論のために」を読みはじめたら、これがおもしろく、夜中まで読みふけってしまい、今日は寝不足。
目次(大見出し)をひろうと、つぎのようになる。
1.マルクスはいかに受容されてきたか
2.現代資本主義の危機
3.近代社会哲学の出発点
4.自由主義批判と疎外論
5.賃金労働の本質
6.実体論から関係論へ
7.現代社会理論の条件
本書は2014年NHKのカルチャーラジオで放送された「思想史の中のマルクス」というラジオ講座をもとにして編集されているから、教科書ふうの書きぶりが特長となっている。
だから、明快でわかりやすく、「マルクスをまだ一度も読んだことのない読者を念頭において」書かれているのだ。
本書の刊行は2016年なので、最新の情報がつめこまれている。
思弁的、観念的論議はほとんどなく、どちらかといえば、大学の1-2年生向きのレベルといえる。
まだ第2章までしか読んでいないが、全体的には経済論的、哲学的議論より、社会学的視点に立った論調が、本書をアクチュアルなものにしている・・・といった感想を抱いた。
「ようやく読みたかった本にぶつかったな」という手応えがある(。・_・)
「資本論刊行当時」
「刊行から五十年」
「刊行から百年」
「刊行から百五十年」
こういう鳥瞰図によって、「資本論」のパースペクティヴが的確にあぶり出されてくる。
わたしの読書は芋ヅル式、螺旋階段的。
ツルを引っ張ったり、階段をのぼったり下りたり。
・・・そんなことが、おもしろくて仕方ないのである。
身辺にはいつだって、12-3冊の本をスタンバイさせてある。
21世紀のいま、マルクスを読むということ。
わたし的には、まだ、走りはじめたばかりなので、5年、あるいはもっと長いスパンの中で、マルクス思想へ接近していこう・・・いや、いけたらいいなあ、ということであ~る(^^ゞ
漫然と書籍の世界に耽溺しているようだけれど、わたしなり方向性ははっきりしている。
1.聖書(旧約・新約)を読む
2.プラトンまでさかのぼって、哲学書を読み、哲学史に理解を深める
3.その中から、デカルト、スピノザ、ニーチェなどと、フランスの「ポストモダン」といわれる一群の思想家について、ある程度の知見をもつ。
4.世界史に関する読書を継続していく。
5.ドストエフスキー、カフカを中心に、“世界文学”の古典を読み返し、さらに新しい作品にも挑戦!
こういった中にマルクス「資本論」もリストアップされている。
4-5日前に、岩波文庫の「資本論」を読みはじめたのだけど、やっぱり歯が立たずに挫折。
十代の終わりころから、こういう経験が過去に二度ある(ノ_・)。
「ドイツ・イデオロギー」と「共産党宣言」だけは二十歳のころにあらかた読んだけれど、理解できたかどうかは別問題であ~る。
岩波版の資本論も、訳がかなり古めかしいので、新訳版を買えばいいのだけど、
大きく重く、高価なので、躊躇しているのだ。
新訳を買って取り組んでも、途中でギブアップしてしまう危惧が多分にあるから・・・。
マルクス、資本論をキーワードにネット検索すると、膨大な情報がダダーと現れて、つい怖気づく。
まあ、そんなことをいっていたら、一生わからないまま・・・。
したがって、まず外濠を埋めるつもりで、たくさんの本を仕入れた。
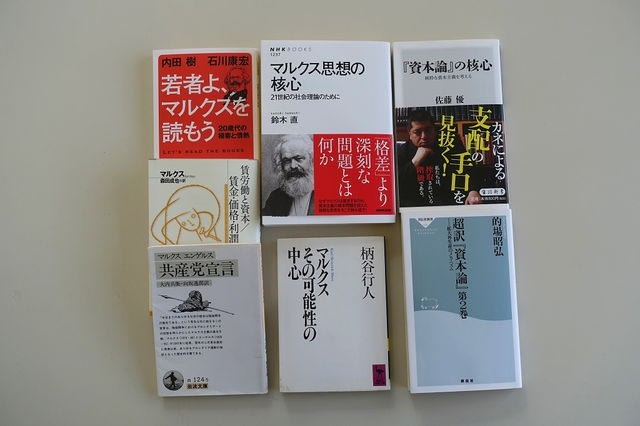
昨夜、NHK・BOOKSの鈴木直さんの「マルクス思想の核心――21世紀の社会理論のために」を読みはじめたら、これがおもしろく、夜中まで読みふけってしまい、今日は寝不足。
目次(大見出し)をひろうと、つぎのようになる。
1.マルクスはいかに受容されてきたか
2.現代資本主義の危機
3.近代社会哲学の出発点
4.自由主義批判と疎外論
5.賃金労働の本質
6.実体論から関係論へ
7.現代社会理論の条件
本書は2014年NHKのカルチャーラジオで放送された「思想史の中のマルクス」というラジオ講座をもとにして編集されているから、教科書ふうの書きぶりが特長となっている。
だから、明快でわかりやすく、「マルクスをまだ一度も読んだことのない読者を念頭において」書かれているのだ。
本書の刊行は2016年なので、最新の情報がつめこまれている。
思弁的、観念的論議はほとんどなく、どちらかといえば、大学の1-2年生向きのレベルといえる。
まだ第2章までしか読んでいないが、全体的には経済論的、哲学的議論より、社会学的視点に立った論調が、本書をアクチュアルなものにしている・・・といった感想を抱いた。
「ようやく読みたかった本にぶつかったな」という手応えがある(。・_・)
「資本論刊行当時」
「刊行から五十年」
「刊行から百年」
「刊行から百五十年」
こういう鳥瞰図によって、「資本論」のパースペクティヴが的確にあぶり出されてくる。
わたしの読書は芋ヅル式、螺旋階段的。
ツルを引っ張ったり、階段をのぼったり下りたり。
・・・そんなことが、おもしろくて仕方ないのである。
身辺にはいつだって、12-3冊の本をスタンバイさせてある。
21世紀のいま、マルクスを読むということ。
わたし的には、まだ、走りはじめたばかりなので、5年、あるいはもっと長いスパンの中で、マルクス思想へ接近していこう・・・いや、いけたらいいなあ、ということであ~る(^^ゞ



























