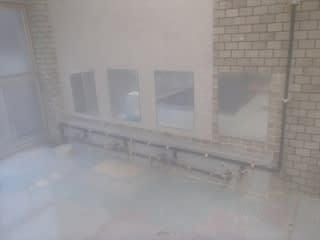信州の霊泉寺温泉へ公共交通機関でアクセスするには、上田駅から千曲バスの鹿教湯線に乗って宮沢バス停で下車します。ちなみに画像のバスは上田駅行。


バス停近くの広場には上画像のような小屋と2つの道標が立っており、大きな方の道標には「欲深霊泉脈 截流向左邊」(霊泉の脈を探ねんと欲すれば、流れを截(き)りて左辺に向かうべし)という、いかにも禅寺らしい臍の曲がった文言が彫られているのですが、標識のくせに難解な表現はいかがなものかという判断が働いたのか(というか移転の都合なんでしょうけど)、手前に置かれている小さな道標の内容は「右かけゆ道 左霊泉寺道」(霊は異体字)という万人が理解できるものでした。


バス停から温泉街へは約2キロですから、荷物が重くなければ歩けなくもない距離ですが、宿泊利用の場合にはお宿の方がバス停まで車で迎えにきてくれますので、普段は徒歩派の私も今回は送迎をお願いしました。広場の小屋には有線電話が置かれており、各旅館の番号が貼りだされています。尤も、今回宿泊した「遊楽」さんではこの電話が使えないため、自分の携帯電話で連絡することになるのですが、バス乗車前に宿へ連絡しておいたので、私がバス停へ降りた時には、既に宿のご主人が待っていてくださいました。

ご主人が運転する車はいまどき珍しいMTの軽乗用車で、結構年季が入っているらしく、ギアが入りにくそうでした。宮沢バス停から5分ほどで「遊楽」へ到着。前回の記事で紹介した禅寺「霊泉寺」の斜前に位置しており、温泉街の入口にあたるポジションです。玄関を開けると朗らかに笑顔を振りまく奥様が出迎えてくださいました。
こちらの宿は一旦廃業した旅館を、お仕事をリタイヤしたご主人が買い取って新たに営業を再開させたんだとか。従いまして、こちらは本格的な旅館ではなく、老夫婦がリタイア後ののんびりとした時間を活かして営業している民宿なのであります。今回は「じゃらん」で提示されていた料金が3連休にもかかわらず1泊2食付で6,700円(入湯税別途)というリーズナブルな設定であり、また拙ブログでリンクしております「しーさん」さんのサイト
「温泉を通じて」にて紹介されていた内容が魅力的でしたので、1泊させていただくことにしました。


ご主人に案内されて客室へ向かう途中に通過した2階の喫煙スペースには、昔懐かしい室内アンテナを載せたブラウン管テレビが置かれていました。これって使えるのかしら…。平成生まれの方だったら、室内アンテナなんて知らないでしょうね。


今回のお部屋はこちら。お年を召したご夫婦2人で全てを切り盛りしている宿ゆえ、お食事の最中に布団を敷いて…なんてことはできませんから、予め布団を敷いておくようです。そのおかげで到着してすぐにゴロンと横になれますね。ちなみに夜になると布団の中へ湯たんぽを入れてくれました。
窓からは川の流れと霊泉寺の境内がそれぞれチラっと窺える程度に望め、その窓際には底冷えする冬の信州に欠かせないこたつが置かれています。客室のテレビも喫煙スペースに負けず劣らずの骨董品でして、デジアナ変換によって現在でもしっかり映ります。この手のテレビが我が家にあったのは、かれこれ30年前だったなぁ…。まだ家電量販店なんて存在しておらず、地元の電気屋さんから購入していましたっけ。
ちなみにお食事は夕食朝食ともに玄関ホールでいただきます。信州の味覚を活かしながらも家庭的な献立となっていて、たとえばこの日の夕食は…鮎の塩焼き、コイの洗い、ダイコンの煮付け、鶏の甘辛炒め、信州そば(椀そば)、十穀米、ゼリー等などです(画像は撮っていません)。
3連休の初日とあってか、この日は全ての部屋が埋まるほどの賑わいでしたが、むしろご夫婦にはその盛況が負担になっていたようで、調理と配膳だけで精一杯のご様子でした。

さて腹を満たしたところで風呂へと参りましょう。
浴室は大小の2つがあるのですが、まずは大きな方から。浴場入口前のラウンジ周りはリフォームされているらしく、家庭的ながらシックで落ち着いた雰囲気が漂っています。また室内の一角には冷たい麦茶が用意されており、湯上りの火照った体にその麦茶を流し込むと、とっても爽快でした。こうしたアットホームな気配りは嬉しいですね。


元々旅館だけあって、脱衣室はそれなりの広さが確保されていました。棚には替えのタオルが積まれており、宿泊中に複数回入浴する場合はとても便利です。なお大小両浴室とも普段は貸切利用ができるらしく、使用していない時は浴室(脱衣室)扉を開けておくことによって使用中でないことを示すのがこちらの宿のローカルルールとなっています。尤もこの日は宿泊客が多かったために貸切とはせず、2つあるお風呂を男女で使い分けていました(23時~6時は入浴不可)。
浴室も宿の規模を考えるとなかなか広い造りで、室内の左右両側にはシャワーがひとつずつ配置されており、窓の下に据えられた角の取れた浴槽は4~5人が足を伸ばして入れそうな大きさがあります。浴槽に面した窓をあけると、すぐ目の前には川が流れていました。浴槽は全面タイル貼りで、以前の旅館時代から長年使われ続けているものかと思われますが、縁の黒タイルの上に青いペンキを塗ったり、底のタイルにも塗装を施したりと、色彩面でできるだけ明るくしようと頑張っているフシが見受けられます(でもその塗装が所々剥げちゃっているので、却って見窄らしい印象を与えているようにも感じられます)。


竜か鰐かは判然としませんが、とにかく大型の爬虫類と思しき石の湯口から加温された源泉がドボドボと注がれています。放流式の湯使いで、源泉の投入量は比較的多く、宿泊中に3度ほど入浴しましたが、湯船のお湯は常に鮮度良好でした。ただ湯口から吐出される量や温度は常に一定というわけではなく、量・温度ともに上下を繰り返していました。湯船の状況に応じて自動調整されているのかしら。
なお排湯に関しては長野県で顕著に見られる独特の方式、すなわち浴槽湯面より若干低い位置の洗い場床に穴があけられ、その穴と直結した浴槽内の吸入口からお湯が流れて排湯されてゆく仕組みによって、浴槽縁の上面を乗り越えることなくお湯が洗い場へと流れ出ています。
お湯は無色澄明で、共同浴場で感じられた硫黄感こそ無かったものの、石膏感ははっきりと有しており、弱い引っ掛かりとトロミのある浴感が優しく全身を包んでくれ、入浴中は夢心地そのものでした。
それにしてもこの湯口、どこかで見たことあるなぁ…。
 あ、そうか。大鰐か!
あ、そうか。大鰐か!
参考までに、私が思いついた青森県大鰐温泉の湯魂石薬師堂にある飲泉所の鰐を載せておきますね。ちょっと似てますでしょ。
こちらは小浴室。こぢんまりとした民宿サイズのお風呂です。大きなお風呂と同様に、脱衣室のラックには替えのタイルが用意されていました。よく手入れが行き届いており清潔です。ご夫婦2人でお風呂を含めた全てのメンテナンスをされているんですから、さそがしご苦労のこととお察しします。


浴室内には扇型の岩風呂がひとつ。そしてシャワーもひとつ。貸切利用には丁度良いサイズですね。小さいお風呂ながらも湯船の排湯は大きなお風呂と同じく貫通穴から流れ出されていました。もちろんこっちも(加温の上で)掛け流しですよ。
旅館や民宿というより、田舎のおじいちゃんの家に泊まるような、ノスタルジー且つアットホームな施設でした。ご夫婦ともにお喋り好きのようでして、機会があればゆっくりお話したかったのですが、残念ながら今回はお二人とも忙しくてそんな余裕は無く、チェックイン時とアウト時にちょこちょこっと会話を交わしただけでした。日帰り利用に関しては予約も可能なんだそうですから、次回利用時には繁忙期を避けてのんびりお邪魔したく存じます。
単純温泉 36.0℃ pH8.3 掘削動力揚湯 溶存物質901.9mg/kg 成分総計906.3mg/kg
Na+:62.8mg(20.92mval%), Ca++:205.3mg(78.45mval%),
SO4--:545.8mg(89.23mval%),
H2SiO3:26.8mg,
(平成17年5月24日)
上田駅より
千曲バスの鹿教湯線で「宮沢」バス停下車、徒歩18分(約1.6km)
長野県上田市丸子町平井2540-15
0268-41-7170
ホームページ
日帰り入浴時間不明(10:00~19:00?)
500円(予約利用時は800円)
シャンプー類・ドライヤーあり
私の好み:★★★