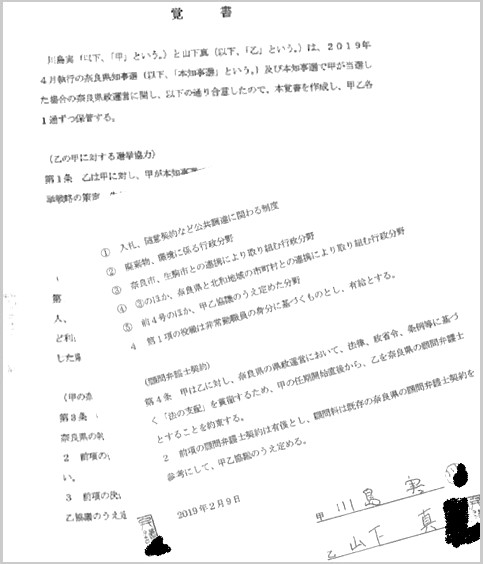◆国は開示できない理由をまったく説明できなかった
本来、行政機関が行う公共事業は会計法によって競争入札することが原則とされている。しかし、アベノマスクは緊急性が存在するとして随意契約で調達された。例外的に行われた事業のプロセスを国民が検証するには行政文書が開示されなくてはならない。情報公開法は原則として情報公開を義務とし、非開示とする場合は、国に同法が定める非開示事由の主張立証責任を課している。
今回の訴訟において、被告・国は「開示された企業の競争上の地位やその他の正当な利益を害する恐れがある」「契約・交渉に係る国の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある」として、単価等の不開示は適正だったと主張。しかし、原告弁護団の「単なる確率的可能性があるにすぎない」という反論に対し、国はまともに言い返すことすらできなかった。
そのうえ国は最終準備書面を出すにあたり、裁判所と約束した期限を8日も過ぎた2022年9月30日の弁論期日当日になってようやく提出しようとする。
原告弁護団の「いくらなんでも遅すぎる」というクレームを受けた裁判長は、
「被告の方の準備書面、裁判所もいただきましたが、原告が『そんな直前に出されてもと』おっしゃるので、どうしますかね。新たな主張もないということで、証拠調べの結果もふまえた上で主張を整理するというのであれば、陳述せず終結ということで宜しいですかね」
と述べ、20ページにわたる書面を受け取らないまま審理は終わってしまったのだ。
原告弁護団の谷真介弁護士は「国は訴訟において定められた期限を必ず守るので、こんなことは異例です。ビックリしました」と語る。
こうした対応を見ていると、国は国民に知らしめなくてはならない情報をなんの根拠もなく隠蔽していたように思えるのである。
◆法廷で明らかになったアベノマスク事業のずさんさ
2022年6月28日、厚労省、経産省、総務省の職員で構成された合同マスクチームの実務上の責任者である厚労省医政局経済課・課長(当時)に対する証人尋問が行われた。
原告側の谷真介弁護士が、2020年4月1日、安倍晋三首相が突如として全世帯に布マスクを配布すると宣言した際の状況について尋ねたとき、合同マスクチームの責任者は驚くべきことを口にした。
「それ(全世帯向け、介護施設向けのマスク調達)をすべて経済課で担当することになります。そういう理解でいいですか?」
「はい」
「これはとんでもないことになったなと思われましたか?」
「はい」
「全世帯向けマスクが一番注目を浴びたんですけれども、いつの時点で知ったんですか。政府の発表があってから知ったんですか?」
「直前です」
マスク調達を担う合同マスクチームは全世帯向け1億枚以上、介護施設向けにも1億枚以上を追加で調達しなくてはならなくなったことを、発表直前まで知らされていなかった。
アベノマスク全世帯向け配布事業は経済産業省出身の佐伯耕三首相秘書官が、「全国民に布マスクを配れば、不安はパッと消えますから」と安倍晋三首相に進言したことから始まったと複数の雑誌メディアが報道している。(FACTA2020年5月20日号、週刊東洋経済2020年5月30日号、週刊新潮2020年9月3日号など)
現場との実現可能性の検討など一切行われず、官邸官僚の思いつきのまま首相官邸からのトップダウンで強行された事業であったことが、合同マスクチーム責任者の法廷での証言から明らかになったのである。
そもそも、この施策を決めた時点でWHO(世界保健機構)は「新型コロナ感染拡大期における布マスクの使用はいかなる状況においても勧めない」と断言していた。
その後、カビや汚れ、虫の混入などによる回収騒ぎを経て、菅義偉官房長官が「全世帯向けのマスク配布を終えた」と発表したのは2020年6月25日。すでに市場には不織布マスクがあふれかえっていたのである。
◆安倍晋三元首相は回顧録において「間違っていなかった」と断言
介護施設・妊婦向けなどのアベノマスク配布事業は2020年7月30日に中止され、8272万枚が在庫となった。会計検査院の検査報告によると、同年8月からの8ヵ月間で6億0096万円の保管料がかかっている。結局、残されたマスクのうち約7100万枚はネットで申し込んだ希望者に無償で配られた。その費用だけで5億円かかったと言われている。
このような顛末となったアベノマスク事業だが、2023年2月8日、中央公論新社より刊行された「安倍晋三回顧録」おいては、「わたしは政策として全く間違っていなかったと自信を持っています」と語られていた。
はたしてアベノマスク事業は妥当なものだったのか。
原告は今回判決が下された裁判以外にもうひとつ、アベノマスクの情報開示についての訴訟を提起しており、現在も審理が続いている。公文書管理法は行政機関の職員に対し、経緯も含めて意思形成に至る過程、および事務や事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう文書の作成を義務づけている。ところが国が業者との間で契約、発注、回収を行うにあたり、その契約や交渉などの経過を記載した文書の開示を求めたところ、「作成していない」として不開示だった。原告側は「契約締結の経過の文書がないわけないだろう」と不開示の取り消しを求めているのである。
■https://news.yahoo.co.jp/byline/akazawatatsuya/20220924-00316227
こちらの裁判では当初、国は業者との「やりとり」そのものを記載した文書として電子メールがあったものの、それらは保存期間1年未満文書と位置づけていたため、ぜんぶ捨ててしまっていると主張した。
国が電子メールを廃棄していたとしても、相手方である業者には残っているはず。こう考えた弁護団は送付嘱託という手続を大阪地裁に申し立て、裁判所は採用を決定。複数の業者からメールや契約書などが提出された。その結果、アベノマスク1枚あたりの調達単価に55円以上の開きがあったことも明らかになっている。
■https://news.yahoo.co.jp/byline/akazawatatsuya/20220715-00303993
また、開示関連文書や業者から出された契約関係の書類を見ると、すべてにおいて見積書と契約書の日付けが同じだった。アベノマスク調達に関し、国は交渉など行わず、ほどんど相手の言い値で売買価格が決まっていた可能性が高い。
しかし、国はふたつの裁判のなかで、「マスク一枚あたりの単価と数量は明らかにできない」「契約締結にいたる交渉の経過を記録した文書は作っていない」「やりとりした文書である業者とのメールはほとんど廃棄済み」と主張するなど、いまだにアベノマスク事業の適切な検証がまったくできない状態となっている。
原告である神戸学院大学の上脇博之教授は、
「アベノマスク事業は随意契約という例外的な方法で行われているわけですから、競争によらずして締結された契約の内容、とりわけ国民の税金で購入されている布マスクの価格が妥当であったのかどうかについて、国には説明責任があります。しかし、わたしの情報公開請求やその後の裁判において、国は文書を開示しない理由について不合理な言い訳を重ね続けています。アベノマスク事業の実態をとにかく隠し通したいという意図なのでしょうけれども、これは国民主権原理や憲法21条に由来する『国民の知る権利』を踏みにじる行為であり、言語道断だと考えています」
と語る。
公文書は国民のもの。政権の都合で意図的に出したり出さなかったり、勝手に捨てられてしまったりするようなことが許されてはならない。
















 </picture>
</picture>
 </picture>
</picture>