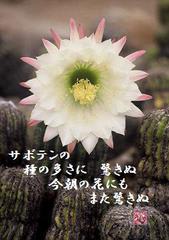サボテンの 種の多さに 驚きぬ 今朝の花にも また驚きぬ
■
 あしたの会
あしたの会
八ッ場ダム建設中止の動向を見て、「これが政治なんだ
なぁ~」と。国家官僚としては大型建設をこなすほど楽
なものはない。ゼネコンに丸投げ、ゼネコンは系列、下
請けに丸投げ。調整は地元議員先生や顔役にお任せ。揉
めそうな場合は、派閥の長におまかせ。官僚は元官僚と
して関連団体に天下りと渡り(この高度成長期の日本型
ケイジアンの構図は、戦前の軍・顔・官と同じ、「やり
はじたらやめられない」)。新政権は熟れていないから、
<撤収特別予算>が準備できていないのは可愛そうな気が
するが(※利水若しくは、治水に特化縮小するのかの選
択肢は検討してみてはどうか)。
■
6世紀後半に南蛮人が日本に持ち込まれたのが初めとさ
れる。彼らが「ウチワサボテン」の樹液をシャボン(石
けん)としてつかっていたため「しゃぼてん」と呼ばれ
るようになったとする説が有力。花も美しい「サボテン
」。花言葉は「風刺」「恩情」
■
「ユダヤ人ってなんなの」と唐突に夕食後彼女が尋ねる。
どうして、それほどまでにイスラエルにこだわるのか理
解できなくはないが、昔、領土だったから二千年経って
武力で建国するなんて、余りにも、学習能力がないので
はないのかと思ってしまう。
■ Bruno Bauer
Bruno Bauer
バウアーは、政治的解放を人間的解放を混同してい
る。キリスト教国家のみを批判し、国家そのものを
批判していない。真の解放とは、そのような市民と
公民との対立そのものの解消、すなわちキリスト教
国家批判ではなく、国家一般、国家そのものへの批
判こそが、なされるべきである。
カール・マルクス「ユダヤ人問題」
宗教は悩めるもののため息であり、心なき世界の心
情であるとともに、精神なき状態の精神である。そ
れは民衆の阿片である。民衆の幻想的幸福である宗
教を廃棄することは、民衆の現実的幸福を要求する
ことである。民衆の状態についての幻想を放棄せよ
と要求することは、幻想を必要とするような状態を
放棄せよという要求することである。
同著「ヘーゲル法哲学批判序説」
と、ここでは、ユダヤ人のマルクスのお復習いだが宗教、
国家、貨幣という幻想の廃絶の実現がいかに困難かをマ
ルクスは炙り出す役割をはたしている。
■ Judaism, Zionism and Anti-Zionism
Judaism, Zionism and Anti-Zionism
理性と知性を欠いた議論、記事はここでは退席いただく
として、ヤコブ・ラブキン(モントリオール大学教授)
の「ユダヤ人と旧ソ連の記憶―文学・宗教の交差―」の
講演を考察し以下にまとめる。
■ Yakov M Rabkin
Yakov M Rabkin
第二神殿時代以降のユダヤ人のアイデンティティ構築の
歴史を概観し、18世紀の欧州に端を発する啓蒙主義思想
の影響を受けたロシアこそが、民族的定義に依る「無神
論者としてのユダヤ人」という新たな自己理解の創出地
であったことを社会史的観点から浮き彫りにした。![]()
ラビ・ユダヤ教の理解によれば、ユダヤの信仰共同体を
担い支えているのは、専らトーラーとその教説である。
この自己理解は、ユダヤ教を土地や神殿などの地理上の
規定から解き放ち、他所へと移送可能な宗教とした点、
またトーラーとその教説にのみに基礎を置くことで政治
的野心を総じて放棄し、移住先の支配者と良好な関係を
結ぶことを可能にした点で、ディアスポラ以降、今日に
至るまで重要な意味を持っている。
■
キリスト教圏の欧州ではユダヤ人は長らく迫害の対象と
なってきたが、18世紀から19世紀初頭にかけて啓蒙主義
が台頭することで、その状況に大きな変化が生じる。信
仰の相違に依らない人間性と、その平等性を唱える啓蒙
思想の普及により、ユダヤ人にも他の国民と同等の市民
権が与えられた。それはまた宗教の世俗化をも惹起する
ものでもあり、ユダヤ教内部では改革派ユダヤ教などリ
ベラリズムの潮流を生み出した。
■
啓蒙専制君主エカテリーナ2世の即位により、ロシア帝
国にも啓蒙主義の潮流が波及し、一部ユダヤ人がユダヤ
教から離反し始めた。居住地選択の自由が認められてい
たドイツやフランスとは異なり、農奴制の影響が残存す
るロシア帝国では、多くの農奴と同様にユダヤ人はユダ
ヤ人居住区に留まらざるを得なかった。その結果、その
制限された地域の内部で、正統派ユダヤ教徒と世俗的ユ
ダヤ人との軋轢、緊張関係が他国では見られないほどに
高まってゆくこととなる。
■
その際、世俗的ユダヤ人は宗教的要素を退け、言語(イ
ディッシュ語)と土地(ユダヤ人居住区)という民族的
要素にアイデンティティの基礎を求めた。ここに民族的
自己規定に依拠した「無神論者としてのユダヤ人」が創
出されたのである。この無神論者のユダヤ人は、19世紀
末から始まるのシオニズム運動積極的な担い手となって
ゆく。
1881年のロシア皇帝暗殺を契機にポグロムがロシア全土
に波及し、ユダヤ人の間では「約束の地」に自民族の国
家を建立しようとの気運が高まるが、その初期シオニズ
ム運動の指導的役割を果たしたのは、ユダヤ人固有の領
土を獲得し、そこでユダヤ文化を開花させることを悲願
とする彼らであった。1920年代から30年代にかけてのソ
ビエト国内での宗教弾圧や第二次大戦後の苦境を経た結
果、無神論者のユダヤ人にとって、多大な労苦を負うこ
となく自民族の文化を保存、発展させることが可能とな
る安住の地はイスラエルのみとなる。
■
また同時に、イスラエルにおける彼らの文化構築への専
心は新たな抗争の火種ともなった。それは、かつてロシ
ア帝国のユダヤ人居住区で生じたものと同じであり、つ
まりは正統派ユダヤ教と無神論者のユダヤ人との抗争で
ある。この対立は今日のイスラエルにおいてもなお解決
を見ていない。
■
なるほどそういうことか。アジア専制主義的な後進性を
引き摺っているのかと腑に落とす。
GLOBE(091019) の「ユダヤ教徒がシオニズムに反発する
理由」(同著者)で、パレスチナの地にユダヤ人のホー
ムランド建設を目指す「シオニズム(Zionism)は、聖地エル
サレムに由来する。これは宗教イデオロギーでなく、政
治的イデオロギとして19世紀後半に欧州で誕生。戒律、
律法に従う人々の宗数的共同体のユダヤ人社会に欧州の
ナショナリズムを当てはめたものだ。独自言語 (ヘブラ
イ語)を持つ国民、民族として「ユダヤ人」(The Jews)を位
置づけた国民国家主義だとし以下の様に語る。
■
日本人が、お寺に参拝しなくても 「日本人」という民族的
アイデンティティーを持てるが、世俗化した東欧系ユダ
ヤ人は、シオニズムによって、民族的アイデンティティ
ーを持ち、欧州の反ユダヤ主義(a nti-Semitiszm )に対抗し
少数者の権利を主張できるようになった。イスラエルの
ある学者は「我々がこの土地を求める理由は単純だ。神
は存在しない。だが、神はこの土地を我々に約束したのだ
」と。この発言はシオニズムが非宗数的な政治的主張で
あることをよく示している。
■
20世紀のドイツ系ユダヤ人の政治思想家 ハンナ・アーレ
ント(1906~75 )は自身もシオニストだったが、シオニス
ト国家の樹立には否定的だった。彼女はイスラエルが建
国された 1948年の段階で、シオニスト国家を作れば、絶
え間ない紛争が続くと見ていた。昨年後、事態はまさに
その通りになっている。昨年暮れから今年初めにガザで
起きたスラエルの軍事行動は、彼女の見通した事態が現
実化したものなのだと述べる。
残念だが容量が尽きそうだ。この続きは明日にでも。
■