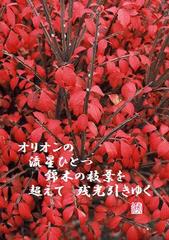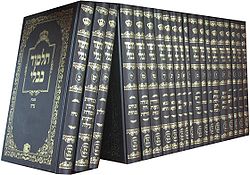オリオンの流星ひとつ 錦木の 枝葉を超えて 残光引きゆく
■
理由」(GLOBE/091019)の続きから-日本人に理解し
てほしいのは、中東紛争はイスラム教徒とユダヤ教徒と
の宗教紛争ではない、ということだ。実際には、両者は何
世紀にもわたって共生、共存してきた。一握りのシオニ
ストが武力を行使して、そこにいた居住者(パレスチナ
人)を彼らの意思に反して、家から追い出した。武力で国
家を樹立したために起きた、極めて単純な人権問題なの
だ。パレスチナ自治政府や、ハマスのせいで紛争が続い
ているのではないと述べている。
■
イスラエルの指導者はあらゆる戦争に勝ってきたが、残
念ながら平和を勝ち取ることはできなかった。それは、
彼らが、パレスチナ人に対して、不公正なことをしたこ
とを決して認めようとしないからだ。イスラエル社会は
多様で、世俗的か宗教的か、東欧出身か、アラブ・北アフ
リカ出身(セファルディム:Sephardim)かで分かれ、明確な統一
の核といったものがない。指導者は「アラブの脅威」を使
うことで国家の結束を維持してきたのだ。宗教が中東
和平の妨げになるとすれば、その最大の要因は、米国の
宗教右派に信奉者が多いクリスチャン・シオニズムだろ
う。彼らにとって、この問題は純粋に宗数的な問題であ
り、妥協の余地がない。
■
キリストの再臨(the Second Coming)を早めるためにユダ
ヤ教徒をイスラエルに集めなければならない、と考えて
いる。そして、キリストが再臨すれば、ユダヤ教徒は二つ
の選択を迫られる。ユダヤ教徒はキリストをメシア救世
主)ではないと考えているが、キリストをメシアと認めて、
キリスト教に改宗するか、あるいは最後の審判を受けて
死ぬかだ。彼らのシナリオでは、我々ユダヤ教徒は全5幕
の演劇の第4幕で消えてしまう。極めて危ないのは、宗
教右派やイスラエル・ロビーの影響が大きい米国やい
くつかの国において、彼らが政治的に大きな力を持って
いるために「親イスラエル政策」をとっているというこ
とだ。米国で最も影響力のある宗教右派団体「アメリカ
キリスト教徒連合(CCA)]はブッシュ前大統領と密接な
関係を保っていた。
■
いま、イスラエル国内にも、米国が主導する「パレスチナ
国家とイスラエルとの2国家共存案」にかわり、ひとつ
の国のなかでユダヤ人とパレスチナ人が共生する「1国
家解決案」を主張する意見がある。今日、世界中でユダ
ヤ人がユダヤ人であることを理由に殺害されうるのは、
不幸なことにイスラエル国内だけだ。世界をみれば、米
国でもロシアでも、そしてイランにおいてすら、ユダヤ
人はふつうに少数者として暮らしている。
■
だったら、パレスチナでもできるのではないか。実際、こ
の場所は何世紀にもわたってオスマントルコというひ
とつの国だった。議論しているのは、理想ではなく、歴
史的に存在していたものなのだ。ドイツで起きたホロ
コースト(ユダヤ人大虐殺)から、アーレントやアインシ
ュタインらが得た教訓は、民族、宗教、人種の面で差別す
るような国家に対しては警戒しなければならないとい
うものだった。
■
半面、シオニスト国家の樹立を求めるシオニストらの
教訓は単純だった。我々は弱かった、我々は強くなくて
はならない、というものだった。彼らはパレスチナ人と
の共生を望まず、民族的に「純粋な」国家を持ちたいと考
えている。かつて、南アフリカや旧ローデシア(ジンバブ
エ)は、敵ばかりに囲まれた孤島のような国を作ったが、
そんな国は長つづきしない。シオニズムに対しては、ア
ラブだけでなく、イスラエル内外のユダヤ教徒の間に
も極めて大きな反発がある。
(1)ユダヤ人とは、何らかの道徳的な価値を持ち、そ
れを守る人々の集団であるはずなのにイスラエル
国家のありようはこうした原則に反する。
(2)イスラエル国家の建国によって、ユダヤ人のアイ
デンティティーが、「ユダヤ教徒」から「イスラエル
国家の政治的支持者」に変質してしまう。
というのが主な理由だ。そして、戒律を破ってもまっ
たくおかまいなしなのにイスラエルを批判すると即座
にひどい反応が返ってくるといった事例に事欠かない。
■
私は学者としての見解と、個人的な意見は常に区別して
いるが、旧ソ連でユダヤ系ロシア人として育った私を含
む宗教的なユダヤ数徒にとっては、ユダヤ教の継続性を
保つことこそが重要なのだ。2千年にわたる伝統の本質
とは、道徳的な価値を守るシステムなのであり、政治的、
軍事的パワーとは無縁だった。自分にとって何ものにも
代え難いことは、神の戒律、安息日、ヨム・キプール(贖
いの日)を守り、ユダヤ教に従った食物(kosher)食べる。
それだけだ。宗教的なユダヤ数徒にとって、啓典宗教の
始祖アブラハムが葬られている聖地ヘブロン(ヨルダ
ン川西岸の都市)を大事だと思うからといって占領して
そこに住む必要はない。ヘブロンを愛することはニュー
ヨークからもできるしテルアビブからもできる。
「ユダヤ教的lな態度とは、常に極めてプラグマティ
ック(現実的)で、妥協的でもある。ユダヤ教的なアイデ
ンティティとは、国境や領土を超越したものだ。だから
こそ、ユダヤ人はチリでも神戸でもモスクワでも暮らせ
る。ユダヤ教の本来の教えは、平和を探求し、協調性か
求めること。よい行いをし、同情の気待ちを持つことだ。
イスラエル国内にはユダヤ国家が存在することは認め
られない、と考えるユダヤ教徒らもいる。彼らは現在の
イスラエル国家は、メシアによる救済を実現する上で、
神学的にも妨げであると考えている。
■
ユダヤ教の戒律では、他人の悪口をいうべきではないと
いう教えがある。日本人はあまり他人の悪口を言わない。
他人のことを自分よりも大事だと考えることを自然に
できる。多くの文化的な面で、ユダヤ教的な考え方と極
めて類似していると感じ、興味深い。中東に重要な利害
を持つ日本は、国連などの場で米国の後追いだけではな
い、何か独自なことができるはずだと。
虔なユダヤ教徒で、日本人に対する自尊心の慰撫と期
待を掛ける。さて、道理でロシアマルクス主義の影響
なのか(マルクスは、中欧の強く影響を受けたが→ヘ
ーゲル哲学)、偶然にも「ユダヤ人問題によせて」か
らの切り口は強ち、間違いはなかったようだ ^^;。日
本の10分の1程度の人口でイスラエルと米国にその
3分の2が居住。過酷な歴史的背景を抱え現代まで残
りえたのは奇蹟的とあらためて驚嘆する。
■
【古代イスラエル】
紀元前5千年頃、カルデア人がウルに王朝を建てる。
紀元前4千年頃、メソポタミアの平原一帯に大規模な
洪水が起こる。その後、二つの民族があらたにウルに
侵入し新しい王朝を建てる。紀元前3千年代、シュメ
ール朝が興る。この都が「創世記」で言われるカルデ
ア人のウルである。紀元前2千百年頃、ウル第三王朝
のウル・ナンムは支配下においたバビロンにジグラッ
ドを建てる。このような建造物の存在が創世記のバベ
ルの塔の物語の背景にあるとも考えられる。
■

紀元前2千年、ウルは古バビロニアのハムラビ王によ
って滅ぼされる。やがて、アブラハムはハランの南方
カナンの地に半定住する。これは旧約のなかでアブラ
ハムの放浪として描かれている。旧約の「創世記」に
は、アブラハムの子のイサク、イサクの子ヤコブが後
の古代イスラエル人の直系であるとある。ヤコブは後
にイスラエルと改名、このイスラエルの十二人の子供
の子孫がイスラエル十二部族と呼ばれる。
■
新バビロニアを滅ぼしたペルシア王大キュロス(前600
年~前529年)は、紀元前538年にイスラエル人を解放
する(エルサレムに帰還したユダヤ人は2~3割)。ペ
ルシア王ダレイオス1世治下の紀元前515年、ゼルバベ
ルの指導でエルサレム神殿が再建された。これは第二
神殿と呼ばれている。紀元前458年にエズラの指導のも
とで二度目の集団帰還が行われた。またネヘミヤとエ
ズラとがこの時期、国の整備とユダヤ教の形式とを固
めこれが現代のユダヤ教またはユダヤ文化へ直接に影
響している。ユダヤ人の民族外結婚を禁じたのもこの
時であり民族の独自性が確立されたとされる。
■

ニシキギ(学名:Euonymus alatus)とはニシキギ科ニシ
キギ属の落葉低木。庭木や生垣、盆栽にされることが
多い。日本、中国に自生する。紅葉が見事で、モミジ・
スズランノキと共に世界三大紅葉樹に数えられる。名
前の由来は紅葉を錦に例えたことによる。別名ヤハズ
ニシキギ。オリオン座流星群が見えたと息を切らし報
告するきみは、漆黒に浮かぶ錦織の様に輝くと描く。
紅葉が美しい「ニシキギ」。花言葉は「危険な遊び」。
■