都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「イサム・ノグチ 世界とつながる彫刻展」 横浜美術館 6/18
横浜美術館(横浜市西区みなとみらい3-4-1)
「イサム・ノグチ 世界とつながる彫刻展」
4/15-6/25
会期末になってしまいましたが、横浜美術館の「イサム・ノグチ 世界とつながる彫刻展」へようやく行くことが出来ました。前々からとても期待していた展覧会です。
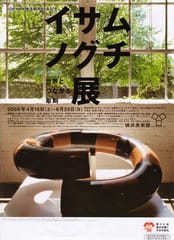
ところでイサム・ノグチの展覧会と言うと、私が彼の彫刻の良さを見出す切っ掛けともなった昨年のMOTでの展覧会を思い出します。巨大な吹き抜け空間に展示されていた「エナジー・ヴォイド」の圧倒的な存在感。そこで受けた感動は今も忘れることがありません。また、暗がりの空間にて床に這いつくばるように置かれていた、半ば「もの派」のような彫刻群。そして陽の光を浴びていた屋外の「オクテトラ」。それまで殆ど分からなかったイサム・ノグチの魅力を初めて体感出来た展覧会でした。


さて、今回の横浜の展覧会ですが、そのMOTの展覧会と比べると全体的にややこぢんまりとしています。それは例えば「エネジー・ヴォイド」のような、空間を大胆に変えていく作品よりも、(また暗室に展示されていた、半ばインスタレーション的な展示ではなく。)もっと、一つの確固とした、まさにオブジェとしての彫刻作品が多く並んでいるとも言えるでしょう。また作品は、「顔」や「神話・民族」、それに「コミュニティーのために」や「太陽」などというテーマに括られて展示されています。戦前の「死」(1934、画像上右)から、いつも横浜美術館に置かれていた晩年の「真夜中の太陽」(1989、画像上左)までが、時系列ではなく、あくまでもそれぞれのテーマの元にまとまって置かれている。またそのテーマ設定も、決して鑑賞者に解釈を無理強いするような強引さがありません。とても良心的に、適度にまとめられていました。

展示自体も良く出来ています。モダンダンスのマーサ・グラハムのために作られた舞台セットを再現し、初演の映像をスクリーンへ流すコーナー。とても見応えがありました。そして李禹煥展の時のように、全部ではないものの、所々カーペットを剥がしてコンクリートに作品を直に置いている。またスポットライトに当てられた作品のシルエットも美しい。いつも窮屈な建物のせいなのか、期待ほど感銘することがない横浜美術館も、今回はそれなりに満足出来ました。少なくとも李禹煥展の際よりは器用に会場を使っています。

ノグチの彫刻を見ていると、どれも原初的なアニミズムのイメージが湧き上がってきました。大地や空へ呼びかけて精霊を呼び集める。魂の宿った石。「広島の原爆死没者慰霊碑(1/5模型)」(1952)はまさにそんなイメージの典型例かもしれません。また会場にて作品が並ぶ様を見ていても、それぞれが相互に関連し合っていると言うより、一つ一つが全く干渉しないで、ジ一と鈍い音を立てて敢然と立っているようにも見えます。もちろんノグチの彫刻をいくつか組み合わせて展示するのも魅力的かもしれませんが、私には一点だけ、殆ど偶然にノグチの作品と出会った方がより衝撃的な印象が強いのです。(もしかしたら彼の作品は、美術館に集めて展示するのがそぐわないのかもしれません。)ややこしい言い回しになってしまいましたが、要は、いくつも見ていると次第に面白さがなくなる嫌いもあると言うことです。これはMOTの展示でも少しだけ感じていたのですが、今回の展覧会ではもう一歩その思いが強まってしまいました。まだノグチを完全に好きになりきれない。どこか構えた見方で作品を捉えているのかもしれません。
とは言え、少なくとも彫刻作家としてのノグチの魅力を巧みに伝えた良い展覧会かと思います。次の日曜日までの開催です。
「イサム・ノグチ 世界とつながる彫刻展」
4/15-6/25
会期末になってしまいましたが、横浜美術館の「イサム・ノグチ 世界とつながる彫刻展」へようやく行くことが出来ました。前々からとても期待していた展覧会です。
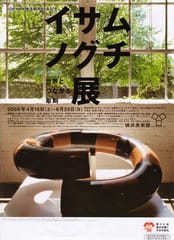
ところでイサム・ノグチの展覧会と言うと、私が彼の彫刻の良さを見出す切っ掛けともなった昨年のMOTでの展覧会を思い出します。巨大な吹き抜け空間に展示されていた「エナジー・ヴォイド」の圧倒的な存在感。そこで受けた感動は今も忘れることがありません。また、暗がりの空間にて床に這いつくばるように置かれていた、半ば「もの派」のような彫刻群。そして陽の光を浴びていた屋外の「オクテトラ」。それまで殆ど分からなかったイサム・ノグチの魅力を初めて体感出来た展覧会でした。


さて、今回の横浜の展覧会ですが、そのMOTの展覧会と比べると全体的にややこぢんまりとしています。それは例えば「エネジー・ヴォイド」のような、空間を大胆に変えていく作品よりも、(また暗室に展示されていた、半ばインスタレーション的な展示ではなく。)もっと、一つの確固とした、まさにオブジェとしての彫刻作品が多く並んでいるとも言えるでしょう。また作品は、「顔」や「神話・民族」、それに「コミュニティーのために」や「太陽」などというテーマに括られて展示されています。戦前の「死」(1934、画像上右)から、いつも横浜美術館に置かれていた晩年の「真夜中の太陽」(1989、画像上左)までが、時系列ではなく、あくまでもそれぞれのテーマの元にまとまって置かれている。またそのテーマ設定も、決して鑑賞者に解釈を無理強いするような強引さがありません。とても良心的に、適度にまとめられていました。

展示自体も良く出来ています。モダンダンスのマーサ・グラハムのために作られた舞台セットを再現し、初演の映像をスクリーンへ流すコーナー。とても見応えがありました。そして李禹煥展の時のように、全部ではないものの、所々カーペットを剥がしてコンクリートに作品を直に置いている。またスポットライトに当てられた作品のシルエットも美しい。いつも窮屈な建物のせいなのか、期待ほど感銘することがない横浜美術館も、今回はそれなりに満足出来ました。少なくとも李禹煥展の際よりは器用に会場を使っています。

ノグチの彫刻を見ていると、どれも原初的なアニミズムのイメージが湧き上がってきました。大地や空へ呼びかけて精霊を呼び集める。魂の宿った石。「広島の原爆死没者慰霊碑(1/5模型)」(1952)はまさにそんなイメージの典型例かもしれません。また会場にて作品が並ぶ様を見ていても、それぞれが相互に関連し合っていると言うより、一つ一つが全く干渉しないで、ジ一と鈍い音を立てて敢然と立っているようにも見えます。もちろんノグチの彫刻をいくつか組み合わせて展示するのも魅力的かもしれませんが、私には一点だけ、殆ど偶然にノグチの作品と出会った方がより衝撃的な印象が強いのです。(もしかしたら彼の作品は、美術館に集めて展示するのがそぐわないのかもしれません。)ややこしい言い回しになってしまいましたが、要は、いくつも見ていると次第に面白さがなくなる嫌いもあると言うことです。これはMOTの展示でも少しだけ感じていたのですが、今回の展覧会ではもう一歩その思いが強まってしまいました。まだノグチを完全に好きになりきれない。どこか構えた見方で作品を捉えているのかもしれません。
とは言え、少なくとも彫刻作家としてのノグチの魅力を巧みに伝えた良い展覧会かと思います。次の日曜日までの開催です。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
NHK-FMは存続へ
一連のNHK「改革」にて、先日当然打ち出されたNHK-FMの廃止話ですが、どうやら見送られる方向が強まったようです。NHKのFM放送は、最近、縮小傾向にあったにしろ、唯一、クラシック音楽を身近に楽しめる媒体でした。もちろんNHKを全面的に応援するつもりはありませんが、こればかりはまず一安心とでも言ったところかもしれません。
NHKのFMラジオ削減盛り込まず 政府・与党合意(asahi.com)
WEBの時代を迎えたとは言え、依然として既存のメディアが大きな力を持っています。それと同様に、インターネットラジオが普及しつつあるにしろ、まだFM放送で聴くクラシック音楽の味わいは失われていません。大上段に構えて申し上げれば、政府の狙いはただ一つ、受信料不払いへの罰則導入にあるのでしょう。FMやBSの削減を打ち出した例の懇談会の答申も、そのごく一部が実現されてひとまず終りと言うことになるのではないでしょうか。ともかくNHKは貴重な音源をいくつも抱えています。この合意に安心しきることなく、ネット放送を使った試みなど、さらなるクラシック音楽の財産を生かした取り組みをしていただきたいものです。
NHKのFMラジオ削減盛り込まず 政府・与党合意(asahi.com)
WEBの時代を迎えたとは言え、依然として既存のメディアが大きな力を持っています。それと同様に、インターネットラジオが普及しつつあるにしろ、まだFM放送で聴くクラシック音楽の味わいは失われていません。大上段に構えて申し上げれば、政府の狙いはただ一つ、受信料不払いへの罰則導入にあるのでしょう。FMやBSの削減を打ち出した例の懇談会の答申も、そのごく一部が実現されてひとまず終りと言うことになるのではないでしょうか。ともかくNHKは貴重な音源をいくつも抱えています。この合意に安心しきることなく、ネット放送を使った試みなど、さらなるクラシック音楽の財産を生かした取り組みをしていただきたいものです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
国立新美術館が完成
少し前のニュースですが、六本木に建設されていた国立新美術館が完成しました。設計は建築家の黒川紀章氏。ガラス張りのウエーブが印象的な巨大な建物です。開館予定は2006年度中。(1月?)もう間もなくでしょうか。

国立新美術館が完成・六本木でお披露目(NIKKEI NET)
何一つ所蔵品を持たない、全くの貸し館にて運営されます。第二の東京都美術館と言っても差し支えないでしょう。(実際に、都美から多くの公募展がこちらへ移るそうです。)また学芸員を数名おいての、近現代アートなどをテーマとした大型企画展なども予定されています。ただし今後、全体のいわゆる美術人口が増えるとも思えません。展開次第では都美はもとより、横浜美術館や東京都現代美術館の活動にも大きな影響を与えそうです。

総工費は350億円。展示室は全12室、約1万4000平方メートルと国内最大級です。もう少し具体的な方向性が煮詰まらないと何とも見えてきません。これからの動きにも注目です。
*最近建設された主な「文化施設」の総工費
水戸芸術館(1990) 103億円
愛知芸術文化センター(1992) 628億円
東京都現代美術館(1995) 415億円
新国立劇場(1997) 750億円
兵庫県立美術館(2002) 300億円
金沢21世紀美術館(2004) 200億円
九州国立博物館(2005) 230億円
国立新美術館(2007予定) 350億円

国立新美術館が完成・六本木でお披露目(NIKKEI NET)
何一つ所蔵品を持たない、全くの貸し館にて運営されます。第二の東京都美術館と言っても差し支えないでしょう。(実際に、都美から多くの公募展がこちらへ移るそうです。)また学芸員を数名おいての、近現代アートなどをテーマとした大型企画展なども予定されています。ただし今後、全体のいわゆる美術人口が増えるとも思えません。展開次第では都美はもとより、横浜美術館や東京都現代美術館の活動にも大きな影響を与えそうです。

総工費は350億円。展示室は全12室、約1万4000平方メートルと国内最大級です。もう少し具体的な方向性が煮詰まらないと何とも見えてきません。これからの動きにも注目です。
*最近建設された主な「文化施設」の総工費
水戸芸術館(1990) 103億円
愛知芸術文化センター(1992) 628億円
東京都現代美術館(1995) 415億円
新国立劇場(1997) 750億円
兵庫県立美術館(2002) 300億円
金沢21世紀美術館(2004) 200億円
九州国立博物館(2005) 230億円
国立新美術館(2007予定) 350億円
コメント ( 12 ) | Trackback ( 0 )










