都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「シュルレアリスムと写真 - 痙攣する美 - 」 東京都写真美術館
東京都写真美術館(目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)
「シュルレアリスムと写真 - 痙攣する美 - 」
3/15-5/6
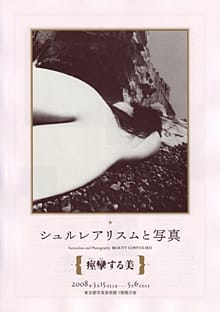
シュルレアリスムにおける写真表現を概観します。東京都写真美術館で開催中の「シュルレアリスムと写真」へ行ってきました。
構成は以下の通りです。館蔵品を中心に、横浜美、埼玉県美、その他個人蔵の写真、約200点余りが展示されていました。
1「都市に向かう視線」:シュルレアリスムの産声をあげたパリ。街角写真にシュルレアリスムの萌芽を見る。
2「都市の中のオブジェ」:シュルレアリスムの文脈に沿って「発見」された街のオブジェ。
3「ボディー、あるいは切断された身体」:シュルレアリスムで好まれた身体、ヌードのモチーフ。コラージュによる身体表現など。
4「細部に注がれた視線」:植物、昆虫、それに建築物など、シュルレアリスムにおける細部への関心を辿る。
都市写真におけるシュルレアリスム表現を見る第1章では、アジェらに続いて紹介されているブラッサイがとりわけ魅力的です。モノクロに沈み込むパリの街の風景が、明暗のコントラストも鮮やかに、あたかも影絵のようにして写し出されていました。特にいくつもの煙突の突き出す「パリの屋根」(1932)は一推しの作品です。浜口の同名のカラーメゾチントを思い起こさせる表題でもありますが、上空に灯る月明かりの元でのびる煙突のシルエットが、あたかもロマン派絵画を見るような雰囲気で表現されています。また石畳の小径を写した「サン・ジャックの塔」(1932)にも惹かれました。実際のところ、ブラッサイをシュルの文脈で語ることにはよく分からない部分もありますが、2005年に同館で開催された回顧展を見逃した私にとってはたまらない内容でした。ここはじっくり楽しめます。
マン・レイ、ヴォルス、瑛九、植田正治と続く第2章では、これぞシュルレアリスムとも言えるような後藤敬一郎の「最後の審判図」(1938-40)の印象が鮮烈です。宙に浮く丸太の断面が山を望む地平の上に大きく写し出されていますが、これはもはやマグリットの絵画をそのまま写真にしたと言っても良いのではないでしょうか。ちなみにマグリットの手がけた写真も一点ほど展示されていました。またマン・レイの『リンゴ』や「ガラスの涙」(こちらは第3章)など、半ば王道的な作品もいくつか揃っています。
ベルメール、バイヤー、ボワファールらの身体表現(第3章)を経由し、最後に辿り着いたのは、例えばアールヌーヴォー下のパリの建築物の装飾を捉えたアジェらの作品でした。そしてここでは、植物やその種子などを標本的に写し出した、ブロスフェルの作品が心に残ります。「オオムギ」(1932)では、まさに名の指す通り、炎のように広がる麦の穂先がそのまま捉えられてますが、その姿が半ば幾何学的な紋様に、言い換えれば植物を通り越した一種の抽象的な図形としてあるかのように示されていました。あるがままのモノに独特のフィルターを通すことで、逆に新鮮な「見えなかった現実」を抉り出す、まさにシュルレアリスムの得意とするところの表現かもしれません。
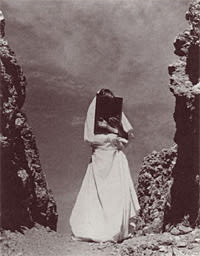
写真におけるシュルレアリスムを史的に追うわけではなく、むしろ上記のような切り口にてそのエッセンスを引き出す展覧会です。またシュルレアリスムと写真の関係を見る大規模な展示としては、国内初の開催でもあるそうです。(会場内解説パネルより。)

AVANTGARDE VOL.5特別号。展覧会のカタログに準じる特集号です。一般の書店でも購入出来ます。
5月6日までの開催です。
「シュルレアリスムと写真 - 痙攣する美 - 」
3/15-5/6
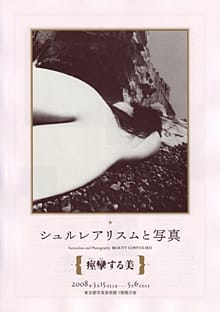
シュルレアリスムにおける写真表現を概観します。東京都写真美術館で開催中の「シュルレアリスムと写真」へ行ってきました。
構成は以下の通りです。館蔵品を中心に、横浜美、埼玉県美、その他個人蔵の写真、約200点余りが展示されていました。
1「都市に向かう視線」:シュルレアリスムの産声をあげたパリ。街角写真にシュルレアリスムの萌芽を見る。
2「都市の中のオブジェ」:シュルレアリスムの文脈に沿って「発見」された街のオブジェ。
3「ボディー、あるいは切断された身体」:シュルレアリスムで好まれた身体、ヌードのモチーフ。コラージュによる身体表現など。
4「細部に注がれた視線」:植物、昆虫、それに建築物など、シュルレアリスムにおける細部への関心を辿る。
都市写真におけるシュルレアリスム表現を見る第1章では、アジェらに続いて紹介されているブラッサイがとりわけ魅力的です。モノクロに沈み込むパリの街の風景が、明暗のコントラストも鮮やかに、あたかも影絵のようにして写し出されていました。特にいくつもの煙突の突き出す「パリの屋根」(1932)は一推しの作品です。浜口の同名のカラーメゾチントを思い起こさせる表題でもありますが、上空に灯る月明かりの元でのびる煙突のシルエットが、あたかもロマン派絵画を見るような雰囲気で表現されています。また石畳の小径を写した「サン・ジャックの塔」(1932)にも惹かれました。実際のところ、ブラッサイをシュルの文脈で語ることにはよく分からない部分もありますが、2005年に同館で開催された回顧展を見逃した私にとってはたまらない内容でした。ここはじっくり楽しめます。
マン・レイ、ヴォルス、瑛九、植田正治と続く第2章では、これぞシュルレアリスムとも言えるような後藤敬一郎の「最後の審判図」(1938-40)の印象が鮮烈です。宙に浮く丸太の断面が山を望む地平の上に大きく写し出されていますが、これはもはやマグリットの絵画をそのまま写真にしたと言っても良いのではないでしょうか。ちなみにマグリットの手がけた写真も一点ほど展示されていました。またマン・レイの『リンゴ』や「ガラスの涙」(こちらは第3章)など、半ば王道的な作品もいくつか揃っています。
ベルメール、バイヤー、ボワファールらの身体表現(第3章)を経由し、最後に辿り着いたのは、例えばアールヌーヴォー下のパリの建築物の装飾を捉えたアジェらの作品でした。そしてここでは、植物やその種子などを標本的に写し出した、ブロスフェルの作品が心に残ります。「オオムギ」(1932)では、まさに名の指す通り、炎のように広がる麦の穂先がそのまま捉えられてますが、その姿が半ば幾何学的な紋様に、言い換えれば植物を通り越した一種の抽象的な図形としてあるかのように示されていました。あるがままのモノに独特のフィルターを通すことで、逆に新鮮な「見えなかった現実」を抉り出す、まさにシュルレアリスムの得意とするところの表現かもしれません。
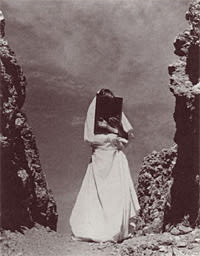
写真におけるシュルレアリスムを史的に追うわけではなく、むしろ上記のような切り口にてそのエッセンスを引き出す展覧会です。またシュルレアリスムと写真の関係を見る大規模な展示としては、国内初の開催でもあるそうです。(会場内解説パネルより。)

AVANTGARDE VOL.5特別号。展覧会のカタログに準じる特集号です。一般の書店でも購入出来ます。
5月6日までの開催です。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )









