都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「コレクション展 近現代日本陶芸の巨匠たち」 茨城県陶芸美術館
茨城県陶芸美術館(茨城県笠間市笠間2345 笠間芸術の森公園内)
「コレクション展 近現代日本陶芸の巨匠たち」
2/5-6/1
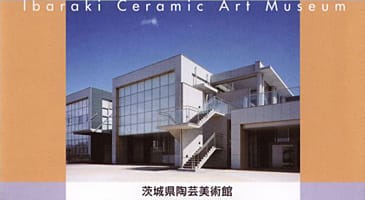
茨城は笠間芸術の森公園の中にある、県陶芸美術館の常設展示を拝見してきました。

この美術館の位置する茨城県中部の町、笠間は、江戸時代より続く焼き物の故郷としても知られていますが、今回のコレクション展では当地より目を県内全域に広げ、茨城と所縁のある陶芸作家の作品(約80点)を展示しています。そして中でも重点の置かれているのが、下館、現筑西市出身の板谷波山(1872-1963)と、生まれこそ長野であるものの、戦時中に笠間へ疎開してきた縁もある松井康成(1927-2003)の作品です。あのミルク色にお馴染みの波山、もしくは「練上」といわれる技法を駆使して、独自の抽象表現を生む松井の作をともに約20点ほど楽しむことが出来ました。

松井康成の作品をこれほど見るのは初めてでしたが、展示品中でもとりわけ惹かれるのは、モノトーンの色合いも美しい器にゆらゆらとした線が波紋上に広がる「練上線文鉢」などでした。そもそも練上とは、色の異なる土を重ね合わせることで模様のある素地をつくり、成形する陶芸技法だそうですが、その色の異なる土が巧みに混じり合い、また溶け合いながら一つの紋様が生まれる様子が何とも興味深く感じられます。私のような素人にはつい絵付けでもしたのではないかと思ってしまいますが、例えば表面にあえて傷をつけ、それを膨らませることで模様をつくるという象裂と呼ばれる技法の作品には、抽象画を見るかのような味わいすら感じられました。土の元来に持つ色や形などの奥深さを見ることが出来ます。


波山ではまず、ミルク色に灯る「葆光彩磁葡萄紋様花瓶」や、魚が器の空間で仲良く向き合う「葆光彩磁赤呉須模様鉢」などに魅力を感じましたが、あまり見慣れない青磁による口の長い瓶の「青磁瓢花瓶」や、アール・ヌーヴォーの影響も濃いという葉の紋様も鮮やかな「彩磁八ツ手葉文鉢」にも見入るものがありました。またかの出光興産の創業者である出光佐三が、これを見て波山のコレクションを開始したという半ば伝説的な「氷華磁仙桃文花瓶」も展示されています。吉祥の画題でもある大振りの桃が瓶いっぱいに配された花瓶です。その重みを感じました。
波山、松井の他は、富本憲吉や三輪壹雪などが紹介されていました。またこの展示より続く常設展示2室では、現代の陶芸作家による「現代茨城の陶芸展」も合わせて開催されています。陶芸の火を絶やさすことなく今も続く、焼き物の町笠間ならではの企画と言えるのかもしれません。(また企画展示室では「人間国宝 荒川豊蔵展」を6月22日まで開催中です。下はそのちらしです。)
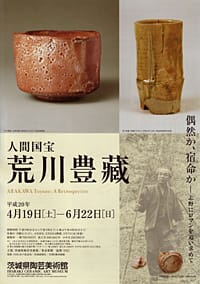
美術館を含む「笠間芸術の森公園」そのものが、一種の工芸のテーマパークのような様相を呈しています。隣接の工芸の丘では、陶芸体験なども随時行われているようでした。



最寄りの笠間駅から陶芸美術館へ歩くと、最短ルートを使ってもおおよそ30分以上はかかってしまいます。本数はかなり少なめですが、笠間市内を周遊する100円バス、もしくはタクシーを利用するか、駅前のレンタサイクルを借りるのが無難です。(自転車なら大通りを使っても10~15分程度でした。)
常設展示「近現代日本陶芸の巨匠たち」展は、6月1日までの開催です。
*関連エントリ
笠間、水戸、アートミニ紀行 2008/4
「コレクション展 近現代日本陶芸の巨匠たち」
2/5-6/1
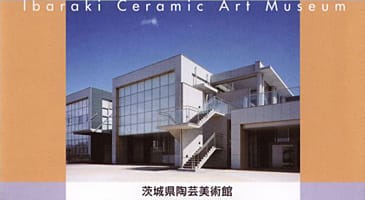
茨城は笠間芸術の森公園の中にある、県陶芸美術館の常設展示を拝見してきました。

この美術館の位置する茨城県中部の町、笠間は、江戸時代より続く焼き物の故郷としても知られていますが、今回のコレクション展では当地より目を県内全域に広げ、茨城と所縁のある陶芸作家の作品(約80点)を展示しています。そして中でも重点の置かれているのが、下館、現筑西市出身の板谷波山(1872-1963)と、生まれこそ長野であるものの、戦時中に笠間へ疎開してきた縁もある松井康成(1927-2003)の作品です。あのミルク色にお馴染みの波山、もしくは「練上」といわれる技法を駆使して、独自の抽象表現を生む松井の作をともに約20点ほど楽しむことが出来ました。

松井康成の作品をこれほど見るのは初めてでしたが、展示品中でもとりわけ惹かれるのは、モノトーンの色合いも美しい器にゆらゆらとした線が波紋上に広がる「練上線文鉢」などでした。そもそも練上とは、色の異なる土を重ね合わせることで模様のある素地をつくり、成形する陶芸技法だそうですが、その色の異なる土が巧みに混じり合い、また溶け合いながら一つの紋様が生まれる様子が何とも興味深く感じられます。私のような素人にはつい絵付けでもしたのではないかと思ってしまいますが、例えば表面にあえて傷をつけ、それを膨らませることで模様をつくるという象裂と呼ばれる技法の作品には、抽象画を見るかのような味わいすら感じられました。土の元来に持つ色や形などの奥深さを見ることが出来ます。


波山ではまず、ミルク色に灯る「葆光彩磁葡萄紋様花瓶」や、魚が器の空間で仲良く向き合う「葆光彩磁赤呉須模様鉢」などに魅力を感じましたが、あまり見慣れない青磁による口の長い瓶の「青磁瓢花瓶」や、アール・ヌーヴォーの影響も濃いという葉の紋様も鮮やかな「彩磁八ツ手葉文鉢」にも見入るものがありました。またかの出光興産の創業者である出光佐三が、これを見て波山のコレクションを開始したという半ば伝説的な「氷華磁仙桃文花瓶」も展示されています。吉祥の画題でもある大振りの桃が瓶いっぱいに配された花瓶です。その重みを感じました。
波山、松井の他は、富本憲吉や三輪壹雪などが紹介されていました。またこの展示より続く常設展示2室では、現代の陶芸作家による「現代茨城の陶芸展」も合わせて開催されています。陶芸の火を絶やさすことなく今も続く、焼き物の町笠間ならではの企画と言えるのかもしれません。(また企画展示室では「人間国宝 荒川豊蔵展」を6月22日まで開催中です。下はそのちらしです。)
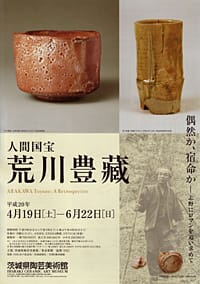
美術館を含む「笠間芸術の森公園」そのものが、一種の工芸のテーマパークのような様相を呈しています。隣接の工芸の丘では、陶芸体験なども随時行われているようでした。



最寄りの笠間駅から陶芸美術館へ歩くと、最短ルートを使ってもおおよそ30分以上はかかってしまいます。本数はかなり少なめですが、笠間市内を周遊する100円バス、もしくはタクシーを利用するか、駅前のレンタサイクルを借りるのが無難です。(自転車なら大通りを使っても10~15分程度でした。)
常設展示「近現代日本陶芸の巨匠たち」展は、6月1日までの開催です。
*関連エントリ
笠間、水戸、アートミニ紀行 2008/4
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )









