都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「伊庭靖子 - まばゆさの在処 - 」 神奈川県立近代美術館 鎌倉
神奈川県立近代美術館 鎌倉(神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-53)
「伊庭靖子 - まばゆさの在処 - 」
2/14-3/22

今一推しの展覧会です。「自ら撮影した果物、プリン、クッションなどの素材を絵画へと転換する」(ちらしより引用、一部改変。)、伊庭靖子の個展へ行ってきました。

対象を厳密な写実で表す絵画はそう珍しくありませんが、差し込む光や影、それに周囲の空気までを一種のフェイクとして平面におこす作家はあまり他にいません。限りなく現実に近い非現実の創出こそ伊庭の本質です。光を纏い、そのプルンとした感触までも表したプリンは本物よりもより瑞々しく、白いシーツに包まれたクッションのフカフカとした様は、もはや視覚だけでは捉えきれない触覚の世界にまで絵を立ち入らせていました。虚空に置かれ、うっすらとした青みを帯びた皿は、全く澱みない清潔感を醸し出しながら、冷ややかでかつ凛とした佇まいを演出しています。シーツで揺らめく光の陰影、または果実の熟れる高い質感は、それ自体の持つ美しさをもゆうに超えてはいないでしょうか。フェルメールのコンテンポラリー版としても差し支えありません。
フェイクとしての美しさは、対象を一時写真に収め、それから絵画におこす作業そのものにも由来しているのでしょうか。ファインダーを通すことで表れるブレは、例えば最新作の陶器の表面を描いた作品でも見て取ることが出来ます。青い文様の描かれた器の表面には白い光の反射する痕跡が残り、それの揺らめきまでをも再現することで、一種の像としてのモチーフを生み出していました。被写体にカメラを近づけ、焦点の定まらなくなった時に開ける未知のイメージが描かれています。陶器は光に微睡み、何とも言えない静寂の気配も呼び寄せていました。

ある程度定まったモチーフのみを描き続けているストイックな姿勢にも好感が持てます。椿会、BASEの個展と見続けてきましたが、今回もじわじわと余韻の残るような深い感銘を味わえました。写実の観点からすれば足りない部分には、むしろ見る側の自由な想像力で補われるわけです。
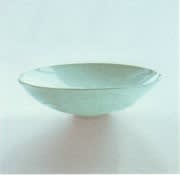
22日までの開催されています。改めてお見逃しなきよう強くおすすめします。
「伊庭靖子 - まばゆさの在処 - 」
2/14-3/22

今一推しの展覧会です。「自ら撮影した果物、プリン、クッションなどの素材を絵画へと転換する」(ちらしより引用、一部改変。)、伊庭靖子の個展へ行ってきました。

対象を厳密な写実で表す絵画はそう珍しくありませんが、差し込む光や影、それに周囲の空気までを一種のフェイクとして平面におこす作家はあまり他にいません。限りなく現実に近い非現実の創出こそ伊庭の本質です。光を纏い、そのプルンとした感触までも表したプリンは本物よりもより瑞々しく、白いシーツに包まれたクッションのフカフカとした様は、もはや視覚だけでは捉えきれない触覚の世界にまで絵を立ち入らせていました。虚空に置かれ、うっすらとした青みを帯びた皿は、全く澱みない清潔感を醸し出しながら、冷ややかでかつ凛とした佇まいを演出しています。シーツで揺らめく光の陰影、または果実の熟れる高い質感は、それ自体の持つ美しさをもゆうに超えてはいないでしょうか。フェルメールのコンテンポラリー版としても差し支えありません。
フェイクとしての美しさは、対象を一時写真に収め、それから絵画におこす作業そのものにも由来しているのでしょうか。ファインダーを通すことで表れるブレは、例えば最新作の陶器の表面を描いた作品でも見て取ることが出来ます。青い文様の描かれた器の表面には白い光の反射する痕跡が残り、それの揺らめきまでをも再現することで、一種の像としてのモチーフを生み出していました。被写体にカメラを近づけ、焦点の定まらなくなった時に開ける未知のイメージが描かれています。陶器は光に微睡み、何とも言えない静寂の気配も呼び寄せていました。

ある程度定まったモチーフのみを描き続けているストイックな姿勢にも好感が持てます。椿会、BASEの個展と見続けてきましたが、今回もじわじわと余韻の残るような深い感銘を味わえました。写実の観点からすれば足りない部分には、むしろ見る側の自由な想像力で補われるわけです。
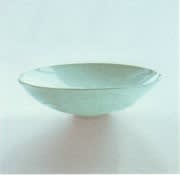
22日までの開催されています。改めてお見逃しなきよう強くおすすめします。
コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )










