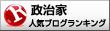こんにちは、三連休でありながら消防関係によって肉体的にも精神的にも厳しい週末を過ごした石井伸之です。
本日は、松嶋議員と共に城山南土地区画整理に関係する方より、区画整理について様々なご意見をいただきました。もちろん様々な話しといっても、組合設立準備会時点でのものですから確定ではなく流動的なところがあり、これからも変化していくことと思います。
この城山南土地区画整理は、ヤクルト中央研究所が広い土地を求めて、調布市の飛行場跡地に移転しようとしたところ、当時の上原前市長が周辺の土地区画整理を行うので、何とか留まっていただけるように要請したという経緯もある中で、地権者の方々による気運が盛り上がり、大変な苦労を重ねた末に組合設立の一歩手前まで漕ぎ付けているところです。
それでも、昨年は関口市長が土地区画整理に関して、用水を開渠にするというこだわりから、土地区画整理準備会そのものの存続が危ぶまれたこともありました。
正直なところ、こういった地権者の窮状を知る中で、ついつい感情的になってしまい、9月議会の城山南土地区画整理に関する一般質問では関口市長へ厳しい言葉の中で礼を失した発言をしてしまったことは反省せねばならないと思っております。
結果的には、地権者・関口市長・ヤクルト研究所が話し合う中で、柴崎体育館脇から立川市営球場の脇を流れ、多摩川へ注ぎ込む根川のような「小川の回廊」でヤクルト研究所周辺を取り囲む計画だそうです。
土地区画整理の経過を聞けば聞くほど、絶妙なバランスの上に成り立つものであると分ります。ここまでまとまったものを、少し動かすだけであらゆる方面で均衡が崩れてしまい、地権者の意見がまとまらなくなるのは必至の状況であることが分ります。
また、国立市において区画整理が必要な地域があるものの、地権者同士で発起する気運がなかなか高まらない地域もあります。それでも、将来的には間違いなく相続によって土地の活用が必要になり、地域の景観に配慮しない形でミニ開発が行われてしまうと、取り返しがつかなくなってしまいますので、少しずつでも地権者同士において、将来的な土地活用の方向性を定めておく必要性があると感じました。
さらに、水と緑の保全と言いながらも、自然の動物や植生などに配慮するならば人の立ち入りを禁止しなければなりませんが、人が全く手を掛けずに野放しにしておくと、貴重な植生は野性種によって駆逐されてしまい、逆に子供達が遊べる場所を作ればその部分は貴重な植生を植えても荒らされてしまいます。
どうも自然保護団体のスタンスによって、人が全く手を掛けないことを至上のものとしているところもありますが、結果的には人が手を入れなければ根川のような自然は守れないという事実があります。そういった意味で、国立市としてどの部分はどういったスタンスで自然を保護するのか事前に決めておく必要があるのではないでしょうか?
まだまだ谷保地域の区画整理について学ぶべきことは多々あると感じましたので、将来的な土地利用に向けて様々な角度から検討して行きたいと思います。
本日は、松嶋議員と共に城山南土地区画整理に関係する方より、区画整理について様々なご意見をいただきました。もちろん様々な話しといっても、組合設立準備会時点でのものですから確定ではなく流動的なところがあり、これからも変化していくことと思います。
この城山南土地区画整理は、ヤクルト中央研究所が広い土地を求めて、調布市の飛行場跡地に移転しようとしたところ、当時の上原前市長が周辺の土地区画整理を行うので、何とか留まっていただけるように要請したという経緯もある中で、地権者の方々による気運が盛り上がり、大変な苦労を重ねた末に組合設立の一歩手前まで漕ぎ付けているところです。
それでも、昨年は関口市長が土地区画整理に関して、用水を開渠にするというこだわりから、土地区画整理準備会そのものの存続が危ぶまれたこともありました。
正直なところ、こういった地権者の窮状を知る中で、ついつい感情的になってしまい、9月議会の城山南土地区画整理に関する一般質問では関口市長へ厳しい言葉の中で礼を失した発言をしてしまったことは反省せねばならないと思っております。
結果的には、地権者・関口市長・ヤクルト研究所が話し合う中で、柴崎体育館脇から立川市営球場の脇を流れ、多摩川へ注ぎ込む根川のような「小川の回廊」でヤクルト研究所周辺を取り囲む計画だそうです。
土地区画整理の経過を聞けば聞くほど、絶妙なバランスの上に成り立つものであると分ります。ここまでまとまったものを、少し動かすだけであらゆる方面で均衡が崩れてしまい、地権者の意見がまとまらなくなるのは必至の状況であることが分ります。
また、国立市において区画整理が必要な地域があるものの、地権者同士で発起する気運がなかなか高まらない地域もあります。それでも、将来的には間違いなく相続によって土地の活用が必要になり、地域の景観に配慮しない形でミニ開発が行われてしまうと、取り返しがつかなくなってしまいますので、少しずつでも地権者同士において、将来的な土地活用の方向性を定めておく必要性があると感じました。
さらに、水と緑の保全と言いながらも、自然の動物や植生などに配慮するならば人の立ち入りを禁止しなければなりませんが、人が全く手を掛けずに野放しにしておくと、貴重な植生は野性種によって駆逐されてしまい、逆に子供達が遊べる場所を作ればその部分は貴重な植生を植えても荒らされてしまいます。
どうも自然保護団体のスタンスによって、人が全く手を掛けないことを至上のものとしているところもありますが、結果的には人が手を入れなければ根川のような自然は守れないという事実があります。そういった意味で、国立市としてどの部分はどういったスタンスで自然を保護するのか事前に決めておく必要があるのではないでしょうか?
まだまだ谷保地域の区画整理について学ぶべきことは多々あると感じましたので、将来的な土地利用に向けて様々な角度から検討して行きたいと思います。