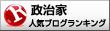こんにちは、防災士の資格を取得している石井伸之です。
本日は午後2時より府中市「府中の森芸術劇場どりーむホール」で第55回東京都市議会議員研修会が行われました。

研修会の講師は、跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科教授 鍵屋一(かぎや はじめ)氏です。
演題は「地域防災の課題と災害時の議会、議員の役割」となっています。
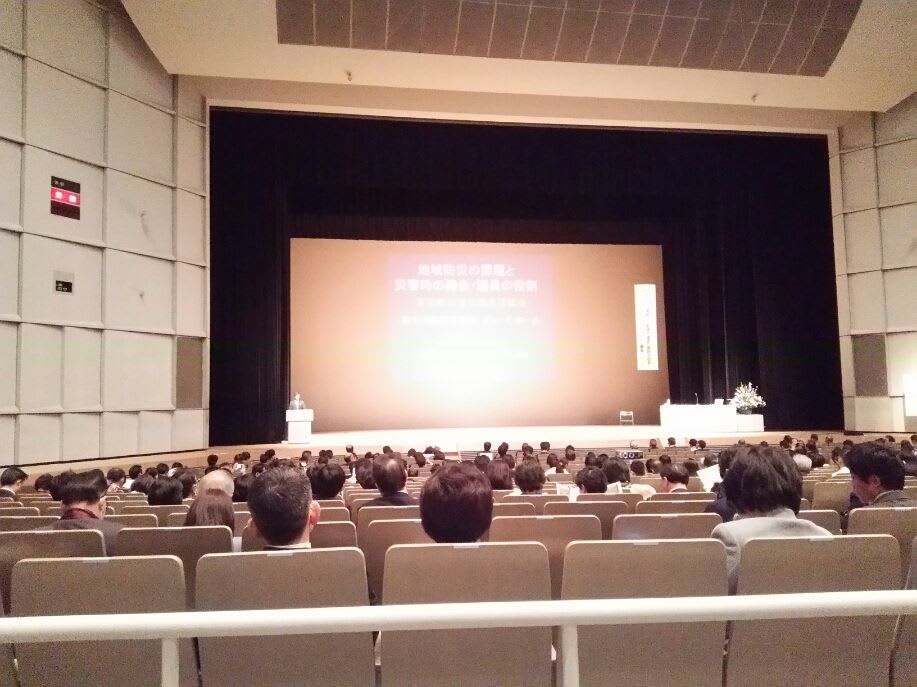
歯に衣を着せぬ、超直球の話し方は、胸の奥に「ズシン」と響きます。
大規模災害時に議員は絶対に「行政の邪魔」をしてはならないとのこと。
確かに、個別の案件をねじ込み、自分や自分の周囲だけを優先させるようなことは絶対に控えるべきです。
そういった中で、災害対策本部が立ち上がり、復旧復興の当たっている3か月は「議会のサイレントタイム」という言葉がしっくり来ます。
つまり、災害復旧時に議員が行政の動きを止めるような「あれがダメ」「これはダメ」「これを先にしろ」等ということをしてはならないということです。
各議員がそれぞれの地域で、出来ることを行うべきと言われていました。
その中で、実際に東松島市が東日本大震災で被災した時の様子を、鍵屋教授が当時の議長に聞いたものを資料としていただきました。
平成23年3月11日は東松島市議会最終日でした。
地震発生直後に市議会の閉会を宣言し、全議員が帰宅後に津波が押し寄せるということから、庁舎に戻ったそうです。
すると、災害対策本部が立ち上がっていたものの、当時の佐藤議長は災害対策本部のメンバーとなっておらず、何をすべきか迷います。
議長の行動マニュアルが無いと、どう動いてよいか分からないという点は、見習うべきです。
まずは、全議員の安否確認を行った後に、議会の責任者として自問自答を繰り返しながら「自らすべきこと考えるしかない」との結論に至ります。
可能なことは、自分の人脈を使って、他の地域の議会から国や自衛隊を動かして、支援の輪を広げることだったそうです。
そう考えると、如何に人脈が大切なものであるか分かります。
また、佐藤議長は議員として絶対にやってはダメということは「スタンドプレー」で分をわきまえることや地域のリーダーを尊重することだそうです。
鍵屋教授の話によると、平時にこそ想像力を発揮して、行政に対して言うべきことを厳しく追求すべきだが、緊急時は地域住民支援に徹するべきと言われました。
その言葉を背に受け、今後とも国立市の防災力向上に向けて、様々な場所で得た知識を分析する中で取捨選択をし、議会や委員会で厳しく訴えていきます。
本日は午後2時より府中市「府中の森芸術劇場どりーむホール」で第55回東京都市議会議員研修会が行われました。

研修会の講師は、跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科教授 鍵屋一(かぎや はじめ)氏です。
演題は「地域防災の課題と災害時の議会、議員の役割」となっています。
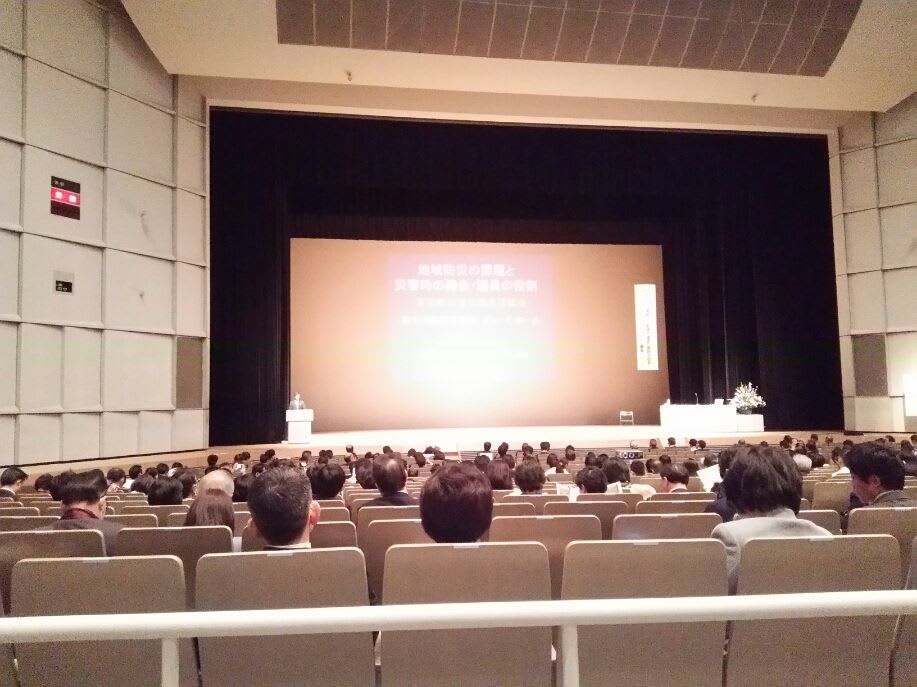
歯に衣を着せぬ、超直球の話し方は、胸の奥に「ズシン」と響きます。
大規模災害時に議員は絶対に「行政の邪魔」をしてはならないとのこと。
確かに、個別の案件をねじ込み、自分や自分の周囲だけを優先させるようなことは絶対に控えるべきです。
そういった中で、災害対策本部が立ち上がり、復旧復興の当たっている3か月は「議会のサイレントタイム」という言葉がしっくり来ます。
つまり、災害復旧時に議員が行政の動きを止めるような「あれがダメ」「これはダメ」「これを先にしろ」等ということをしてはならないということです。
各議員がそれぞれの地域で、出来ることを行うべきと言われていました。
その中で、実際に東松島市が東日本大震災で被災した時の様子を、鍵屋教授が当時の議長に聞いたものを資料としていただきました。
平成23年3月11日は東松島市議会最終日でした。
地震発生直後に市議会の閉会を宣言し、全議員が帰宅後に津波が押し寄せるということから、庁舎に戻ったそうです。
すると、災害対策本部が立ち上がっていたものの、当時の佐藤議長は災害対策本部のメンバーとなっておらず、何をすべきか迷います。
議長の行動マニュアルが無いと、どう動いてよいか分からないという点は、見習うべきです。
まずは、全議員の安否確認を行った後に、議会の責任者として自問自答を繰り返しながら「自らすべきこと考えるしかない」との結論に至ります。
可能なことは、自分の人脈を使って、他の地域の議会から国や自衛隊を動かして、支援の輪を広げることだったそうです。
そう考えると、如何に人脈が大切なものであるか分かります。
また、佐藤議長は議員として絶対にやってはダメということは「スタンドプレー」で分をわきまえることや地域のリーダーを尊重することだそうです。
鍵屋教授の話によると、平時にこそ想像力を発揮して、行政に対して言うべきことを厳しく追求すべきだが、緊急時は地域住民支援に徹するべきと言われました。
その言葉を背に受け、今後とも国立市の防災力向上に向けて、様々な場所で得た知識を分析する中で取捨選択をし、議会や委員会で厳しく訴えていきます。