 「都合のいいときだけ、自分の力を信じるんじゃねえよ」
「都合のいいときだけ、自分の力を信じるんじゃねえよ」八頭大の言葉。
八頭大はまだ高校生ながら、世界トップレベルのトレジャー・ハンターで、彼自身が手に入れた財宝だけで時価数千兆円、各国の政財界トップに与える影響も小さくない。授業中、そんな彼の元に姿を現し、そのまま死んだ老人は世界でも三本の指に入るトレジャー・ハンターだった太宰先蔵。彼の残した言葉と手がかりに財宝の臭いをかぎつけた八頭大は、彼の居所を訪ね、そこで太宰老人の孫娘のゆきと出会う……。
『吸血鬼ハンターD』と並んで作者の出世作であるソノラマ文庫のエイリアン・シリーズから、初期2作『エイリアン秘宝街』『エイリアン黙示録』に書き下ろし『エイリアン旋風譚』を収録した合本。
この作品は日本のトレジャー・ハンターものの先駆け。それまでも隠された財宝や埋蔵金探索をテーマにした作品は少なくなかったですし『レイダース/失われたアーク』の公開が1981年公開ですが、組織化されたトレジャー・ハンターという仕事が出てきたのは、1983年の『エイリアン秘宝街』あたりからです。そう思うと、冒険者ギルドの原点の1つかな。
時系列で並べてみると、
アメリカ製の西部劇が日本でもテレビ放映されるなどして、酒場には賞金稼ぎのポスターが貼ってあり、噂を集める場所という認識がされるようになったのが1960年代。
冒険者の宿「踊る小馬亭」が登場する『指輪物語』が翻訳されたのが1972年。ただし、ここではまだ冒険者が待ち合わせに使う宿の意味。
フリッツ・ライバーの小説「ファファード&グレイ・マウザー」が翻訳され、裏の仕事を斡旋したり情報が手に入る盗賊ギルドが登場したのが1970年。
1981年『レイダース/失われたアーク』公開。トレジャー・ハンターの概念が広まる。
1983年の『エイリアン秘宝街』に情報交流機関として「ITHA(インターナショナル・トレジャー・ハンター・アソシエーション)が登場。
後にグループSNEを立ち上げる安田均がRPG「トラベラー」を翻訳したのが1984年で、そこに「トラベラー協会」という組織が登場。
パソコン雑誌『コンプティーク』でD&Dを使った誌上リプレイ「ロードス島戦記」が始まり、魔法使いのスレインたちが「冒険者ギルド」という組織を立ち上げたというエピソードが登場するのが1987年から始まった第2部の冒頭。
当時ヒットしていた「ドラゴンクエスト」も1988年発売の3作目「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」からパーティ・メンバーの組み替えができるようになり、「ルイーダの酒場」が登場。
権利問題で「ロードス島戦記」の誌上リプレイでD&Dが使用できなくなり、その代替システムを発展させたソードワールドRPGが世に出たのが1989年で、そこで「冒険者ギルド」が採用。以後、コンピュータRPGを中心に、ファンタジー世界の冒険者たちに仕事を斡旋したり情報を提供する組織としての「冒険者ギルド」が定着。
同じく1989年にスタートしたファンタジー小説『フォーチュン・クエスト』には、冒険者を支援する組織として「冒険者支援グループ」が登場。レベルアップの際に冒険者カードが光って音が鳴るなど、コンピュータRPGを意識している描写多し。
とりあえず、こんな流れとメモ。
【トレジャー・ハンター八頭大 ファイルI】【エイリアン秘宝街】【エイリアン黙示録】【エイリアン旋風譚】【菊地秀行】【ソノラマノベルス】【地下鉄】【触手】【天人】【アポカリプス】【ハルマゲドン】【ストップひばりくん】【アカシック・レコード】














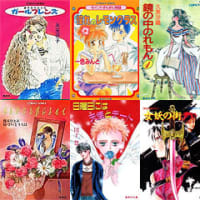

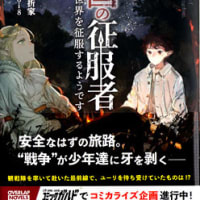

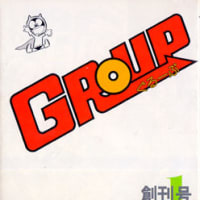
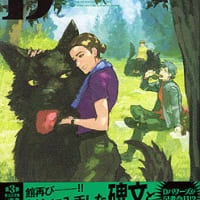
![「水路の夢[ウォーターウェイ]」 早見裕司](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/08/0c/ebdbd76e1b746940033530b209963446.jpg)






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます