 この10年ほど、具体的に言えば『ビブリア古書堂の事件手帖』(2011)のヒットあたりから、喫茶店とか古書店とか雑貨屋とかの主人や店番がちょっとした日常系の謎を解くミステリを、ちょっと落ち着いたタッチのマンガ風イラストで売り出すことが増えたのです。その代表が『珈琲店タレーランの事件簿』(2012)となります。
この10年ほど、具体的に言えば『ビブリア古書堂の事件手帖』(2011)のヒットあたりから、喫茶店とか古書店とか雑貨屋とかの主人や店番がちょっとした日常系の謎を解くミステリを、ちょっと落ち着いたタッチのマンガ風イラストで売り出すことが増えたのです。その代表が『珈琲店タレーランの事件簿』(2012)となります。他には骨董品店で客の依頼をこなしたり預かり品の真贋鑑定したりする『京都寺町三条のホームズ』(2015)。覧強記の天才女医が患者にかかわる謎を解く『天久鷹央の推理カルテ』(2015)。美貌の宝石商と大学生のコンビが宝石に潜む謎を解く『宝石商リチャード氏の謎鑑定』(2015)。大学の教授が化学の力で謎解きする『化学探偵Mr.キュリー』(2013)あたりが売上げ上位となります。
このあたりまで来ると、もう一般的にはライトノベルとは見てもらえないかもしれませんし、たいてい売り場も別になりますが、ライトノベルコーナーに面陳でポンと置かれても、表紙イラストだけでは区別できそうにありません。
つまり、こういう装丁にした、軽く読めそうなミステリは売れる!と出版サイドが購読者層を想定して判断しているということですね。










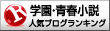
 一般にライトノベルと呼ばれている文芸作品群には、従来のジュブナイルの延長である少年少女が主人公であるものと、かつてのサラリーマン夢小説の変化系が混在しているという論に従って、もうちょいリストを見てみることとした。
一般にライトノベルと呼ばれている文芸作品群には、従来のジュブナイルの延長である少年少女が主人公であるものと、かつてのサラリーマン夢小説の変化系が混在しているという論に従って、もうちょいリストを見てみることとした。 文芸全体だと埋没しちゃうので、対象をライトノベル・ライト文芸に絞ってみた。
文芸全体だと埋没しちゃうので、対象をライトノベル・ライト文芸に絞ってみた。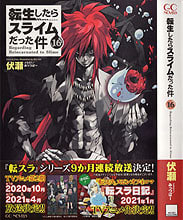 統計的に見て、ウェブ小説の4割くらいがジュブナイルとはちょっと違うということになった。おっさんやら少女になったおっさん、はたまた悪役令嬢になったおばさんが主役の物語を少年少女向きと言うには無理があると判断したからだ。
統計的に見て、ウェブ小説の4割くらいがジュブナイルとはちょっと違うということになった。おっさんやら少女になったおっさん、はたまた悪役令嬢になったおばさんが主役の物語を少年少女向きと言うには無理があると判断したからだ。 「宇宙計画が安全であることを証明したければ、ロケットが女性を乗せられるほど安全であることを誇示すべきなのよ」
「宇宙計画が安全であることを証明したければ、ロケットが女性を乗せられるほど安全であることを誇示すべきなのよ」 だいたいスローライフという言葉が広まってきたのは21世紀になってから。ウィキペディアを見たりしてみたけれど定義は曖昧です。
だいたいスローライフという言葉が広まってきたのは21世紀になってから。ウィキペディアを見たりしてみたけれど定義は曖昧です。 念を入れてみよう。「小説家になろう」の総合ランキングの累計順位を200位までチェックするようにしてみた。
念を入れてみよう。「小説家になろう」の総合ランキングの累計順位を200位までチェックするようにしてみた。 ランキングに名前の挙がった作品のほとんどは、書籍化だけではなくアニメ化までされている。
ランキングに名前の挙がった作品のほとんどは、書籍化だけではなくアニメ化までされている。 では、本当にティーンエイジャー以外が主役の作品は増えているのだろうか?
では、本当にティーンエイジャー以外が主役の作品は増えているのだろうか? ときおり「若いときの趣味嗜好と老後の趣味嗜好」は違うと思われがちだが、肉体的条件の変化に依るものを除けば、その差はさほど多くないのではなかろうか。日本では三味線や編み物は年寄りの趣味と考えられそうだが、それは若い頃から三味線や編み物をしていた若者がそのまま歳を重ねただけだ。パンク・ロックは第二次大戦後に生まれた若者文化の代表だが、その代表とも言えるセックス・ピストルズは75年のデビュー以来、解散と再結成を繰り返しながら30年以上演奏していた。
ときおり「若いときの趣味嗜好と老後の趣味嗜好」は違うと思われがちだが、肉体的条件の変化に依るものを除けば、その差はさほど多くないのではなかろうか。日本では三味線や編み物は年寄りの趣味と考えられそうだが、それは若い頃から三味線や編み物をしていた若者がそのまま歳を重ねただけだ。パンク・ロックは第二次大戦後に生まれた若者文化の代表だが、その代表とも言えるセックス・ピストルズは75年のデビュー以来、解散と再結成を繰り返しながら30年以上演奏していた。 人口分布は急速には変化しない。生まれた子供がいきなり大人になるわけではない。戦争で成人男性がいきなり数を減らしたりすることも現状ではあまり考えられない。人口ピラミッドが逆三角形を描いているなら、年数が経てば経つほど高齢者が増え、若い世代は減っていく。読者の層としても執筆者の層としても若い世代が減っていくのだから、いつまでも少年少女向けだけに文芸作品を書いていても売っていても販売戦略としては先細りである。
人口分布は急速には変化しない。生まれた子供がいきなり大人になるわけではない。戦争で成人男性がいきなり数を減らしたりすることも現状ではあまり考えられない。人口ピラミッドが逆三角形を描いているなら、年数が経てば経つほど高齢者が増え、若い世代は減っていく。読者の層としても執筆者の層としても若い世代が減っていくのだから、いつまでも少年少女向けだけに文芸作品を書いていても売っていても販売戦略としては先細りである。 「ライトノベル」と呼ばれる文芸作品群がある。1980年代にニフティサーブの会議室で生まれた言葉で、表紙イラストとしてマンガ家のイラストやアニメのような一枚絵(以下「アニメ絵))を使い、挿画もふんだんに盛り込んだ本のパッケージスタイルを指す言葉である。当時、想定されていたのはソノラマ文庫やコバルト文庫といった、ティーンエイジャーの少年少女向けのレーベルであったため、ライトノベルという言葉についても今風に出版されたジュブナイル小説とイコールになる一面があった。ジュブナイル小説では、物語の主人公はあくまで同世代の少年少女であって、大人はそれを横から助ける存在か立ちはだかる壁に留まることが多い。それゆえに、ジュブナイル小説=ライトノベルと判断してもさほどおかしくはない。
「ライトノベル」と呼ばれる文芸作品群がある。1980年代にニフティサーブの会議室で生まれた言葉で、表紙イラストとしてマンガ家のイラストやアニメのような一枚絵(以下「アニメ絵))を使い、挿画もふんだんに盛り込んだ本のパッケージスタイルを指す言葉である。当時、想定されていたのはソノラマ文庫やコバルト文庫といった、ティーンエイジャーの少年少女向けのレーベルであったため、ライトノベルという言葉についても今風に出版されたジュブナイル小説とイコールになる一面があった。ジュブナイル小説では、物語の主人公はあくまで同世代の少年少女であって、大人はそれを横から助ける存在か立ちはだかる壁に留まることが多い。それゆえに、ジュブナイル小説=ライトノベルと判断してもさほどおかしくはない。 戦前のユーモア小説の流れで、戦後になってサラリーマン小説と呼ばれる娯楽小説が1950年代になると発表されるようになった。その代表は、源氏鶏太『三等重役』(1951)である。『三等重役』は前社長の追放でいきなり社長昇格したサラリーマンの奮闘譚だが、このように会社組織の中で、創業者一族でも何でもないサラリーマンが出世したり、恋愛に花を咲かせるのがサラリーマン小説の醍醐味だった。
戦前のユーモア小説の流れで、戦後になってサラリーマン小説と呼ばれる娯楽小説が1950年代になると発表されるようになった。その代表は、源氏鶏太『三等重役』(1951)である。『三等重役』は前社長の追放でいきなり社長昇格したサラリーマンの奮闘譚だが、このように会社組織の中で、創業者一族でも何でもないサラリーマンが出世したり、恋愛に花を咲かせるのがサラリーマン小説の醍醐味だった。 「だって、これはもう、ただの屍よ」
「だって、これはもう、ただの屍よ」





