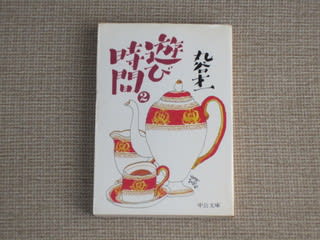丸谷才一 昭和五十八年 中公文庫版
これは去年7月に地元の古本屋で買った文庫。単行本は1980年らしい。
あとがきに「一人の小説家の遊び時間が、どういふものなのか、わりによく判つていただけるはずだと思つてゐます」とあるが、読んでて非常に楽しい、「書く以上、おもしろがつて書くのでなければ意味がないからです」といってるので、書いてるほうが楽しいからそうなるんだろう。
もしかすると、読みやすいのは書評がない構成だからかもしれないけど。
文学に関して勉強になることは、いっぱい。
>ハードボイルド小説の登場人物、殊に私立探偵が、気のきいた台詞をしきりに口にするのは、根本的にはアメリカ社会の反映である。あれは何しろ極端に都市的な、数多くの民族から成る、そして孤立した個人の束とも言ふべき社会だから、お互ひに気心が知れない。そのなかでうまくやつてゆかうとすれば、わたしは危険な人間ではありませんよといふことを相手に対して示す必要がある。(p.61-62「角川映画とチャンドラーの奇妙な関係」)
とかね、それにしても、そういう立派な理由があるにせよ、スペンサーなんかはしゃべりすぎだとは思うけど。
日本のことでは、江戸の俳人で偉いのは、芭蕉、蕪村、一茶の三人ということだが、四人目は昔は其角と決まってたのに、最近ではあまり評価されてない、
>それがさつぱり人気がなくなつたのは、関東大震災で江戸の遺風が消え失せたせいである。これは其角の俳諧を成立させてゐた文明の条件がきれいに亡んだことを意味する。(p.71「菊なます」)
とかね、1976年の文章だけど、江戸をかえりみることが流行ってるのは明治維新以後の価値観が行き詰まったからぢゃないかなんて、そのあとに書いてある、日本の文明も事件によっていろいろ転換する。
翻訳にたずさわることで見つけた、日本語についての意見もあって、
>わたしはイギリスの長編小説を翻訳することで長編小説の書き方を学び、イギリスの批評を翻訳することで批評の書き方を習つた。(p.103「文章を学ぶ」)
で始まる一編では、たとえば森鷗外なんかも西洋の短編小説を日本語ではどうやって書けばなじむのか研究した人だろうとしてるんだけど、
>いちばん困るのは、西洋の小説といふのはいざとなると朗々と歌ひあげる、おめず臆せず高揚するといふことである。これを現代に本文でやるとひどくキザになるんですね。そこのところを困つて、何とか処理しながら、しかしわたしは、むしろ現代日本小説の文体的欠陥について考へてゐたのですが、あれは概して言へば、平板な精神状態を書くのに向く文体しか持つてゐない小説なんですね。(略)
>これと関係がありますけど、第二に、現代日本文では屈曲した論理構造の内容が提出しにくい。(p.105同)
とかって言ってて、「やはり文学者は自分の文明の条件を生きるしかないのです」と覚悟を決めてる、なるほど。
小説は風俗を重視すべしというのは、これまでにも読んできたけど、
>だが、小説の本道はロマン・ピカレスクではなく風俗小説であつて、そこには安定した社会と風俗がなければならない。早い話、首相は首相らしく、土建屋は土建屋らしく、大工は大工らしく、八百屋は八百屋らしいといふのでなければ、登場人物を簡潔に描写することができなくて、文士はすつかり困つてしまふのである。土建屋の社長のやうな総理大臣がゐる国では、どういふ具合に書く登場人物を描けばいいのか、途方に暮れるしかない。(p.303「田中角栄による文学論」)
なんて書いた一編がある、しょうがないねえ、そういう国なんだから、いまもたいして変わらんかな、イギリスの小説なんかとくらべると、どうしても日本には階級がないと思わざるをえないようだし。
言葉に対する感覚はきびしい著者なんだけど、1971年の総評のなかで、
>いちばんきれいな新語は「星おくり」。衛星中継のことをテレビ局ではかう言ふ由。(p.256「惣まくり」)
なんて一節があるが、こういう言葉はすぐ失われちゃって、へんなカタカナとかアルファベットなんかだけが残るんだよね、なぜか。
本書のなかでは、特に読んでみようと思わされるような本の題名にはぶちあたらなかったんだけど、杉本秀太郎の『大田垣蓮月』(淡交社)という本に関しては、篠田一士が絶讃してたと紹介して、実際読んだところ、
>第一に文章がいい。第二に見識が高く、第三に心が優しくてあたたかい。わたしはずいぶん久しぶりに、信頼するに足る批評家の出現を喜ぶことになつた。そしてまた、現代日本文明といふのはこれで案外高級なものなのだなどと安心することになつた。『大田垣蓮月』はさういふ思ひさへいだかせてくれる評伝なのである。これはひよつとすると、一九七五年の最上の本かもしれない。(p.289-290「紅のゆかり」)
なんて言ってるんで、もしかしたら読んでみたくなるかもしれない。
大きな章立ては以下のとおり。新聞に書いたコラムについて「小さな長方形のなかで」なんてタイトルをつけるのはシャレてる。
I 過去への散歩
II 短い文学論と藝術論
III イギリス文学知つたかぶり
IV 引札一束
V 小さな長方形のなかで
VI 政治的? ちよつと政治的?