仕事で、札幌に行ったので、その勢い(?)で、乗馬もすることにした。
このブログは、札幌に住んでたときから始めてたんだけど、札幌での乗馬については、当時思うところあったせいでか、書いてない。
とは言え、そもそも改めて乗馬(っていうか、馬?)のおもしろさを教わったのは、札幌なんである。
なので、今回も当時慣れ親しんだ馬たちとの再会は楽しかった。

↑すっかり誘導馬も板についてきたサンキンバスター。

↑同じくヒノデツートン。
ほかレギュラー陣の誘導馬たち、フサイチピアレス、ロングキングダム、ショウナンターボ、シルバーデュークも元気でした。

↑そして毎度おなじみミニチュアポニーの「ゴルゴ」と「トニー」
それはともかく、月曜朝8時には乗馬センターに行って、コーヒーなんか飲んでると、なんと、夏休みで来ると思ってた、高校生たちが来ないという

ゲストなんだから遊んでていいだろうと、すっとぼけてたら、「おらおら、働かざるもの乗るべからず!」とか言われて、結局、馬房ふたつ寝ワラあげする破目になってしまった

休日なのに、なにいつもより働いてんだ、俺?
だいたい、きょうは気温が30度まで上がるっていうぢゃない? なんのために暑い美浦に帰らず北海道で乗ろうとしてんのか、意味がない。
で、ファンドリロバリーに、騎乗。

彼が私の“愛馬”だってみんな言いますが、まあ、そうです。ただし馬がどう思ってるかは知りませんが。
20頭くらいの馬がいるんで、常に平等に接するようにしてたんだけど、最後の一年は、もういいやってことで、思いっきりエコヒイキしてました

(って言っても、乗らないときでもリンゴやるくらいなんだけど。)
ただ、私に限らず、彼を愛馬にしてる人は多くて、「俺のロバリー」「私のロバリー」と称する人がいっぱいいます。んで札幌乗馬センターを去るときは、彼と記念写真を撮ってったりします。
今回は、ひさしぶりで忘れられて冷たくされたらヤなので、おととい・きのうと夕方にリンゴをやっときました。
リンゴとか角砂糖とか隠し持ってるの知ってるんで、よくハナと口でひとのポケットを探りにくるんで困ったもんです。
で、私と面と向かって一対一でいるときは、何かもらえること分かってるんで、前がきとかうるさいこと一切しません。ところが、ほかの馬房にいる馬たちにもおすそわけをしてると、とたんに「ブヒヒヒ

」と低くハナを鳴らして、こっちを見ます。
そういうところが、まあ、かわいいってば、かわいい

べつに一般的な意味では、特別乗りやすいということもないんでしょうが、この馬に乗ったときの私は、いつもよりうまく乗ってます、たぶん。
下腿部が動かないのが、自分でもわかります(あくまで当社比)。
障害なんか飛ぶと、よくわかる。どうしていつもこう飛べないのかと自分でも思う。ヒザから下がぴったり馬にくっついた状態で、馬が持ち上がってくるのを待ってられるのは、とても楽しい。
この日も「重いかもよ」と言われたけど、拍車なんか無しで、せっせと歩かせたら、とても反応がよかった。基本的に常歩ではノンビリして置いてかれて、速歩ではさっさと追いつくようなとこあるんだけど、常歩からよく歩いた。
駈歩では、なぜか外向いた状態で走ってたんで、ちょっとだけ強引に内を向かせたら、あとは何もすることなし。手綱伸ばしたままでも、きれいに駈歩してくれてました。以前の、左によれてくようなとこ、無くなったの?

昨日おとといと暑いなか誘導馬とか体験乗馬でがんばってた馬たちはお休みだったので、4頭での練習でした。
ファンドリロバリー乗り終わって、ポンポンポンとベタ誉めして降りて、そしたら「これも、乗ってみ?」ってことで、ベイズウォーターにも騎乗。

ベイズウォーターは、私が札幌を去ったあとに来た馬で、半血の8歳。父・パンサー、母・多摩妃という標茶産の乗用馬。
なんでも来週から誘導馬としてデビューするらしい。元競走馬っていうのは、コースに出た瞬間にエキサイトする(幼少のころから、ここでは走れって洗脳されてるから…)んだけど、はたしてこういう馬はどうなのか、まあがんばっていただきましょう。
広い背中だけど、上下に揺れる駈歩で、みんな「馬酔い」(?)するらしいんですが、私は最近、こうやってヒザとか足首とかで柔らかく対処しなきゃいけない馬の揺れ、練習になるんで、けっこう好きです。
乗馬のあとは、午後から、さっぽろ東急でやってる「有賀幹夫写真展 KING OF ROCK'N ROLL 忌野清志郎」という写真展を観に行く。

1986年以降のRCのライブとか、「COVERS」のレコーディング風景とか。
どうでもいいけど、札幌行くのに、おみやげとか持ってくんだけど、所詮食べ物では北海道にかなわない。
この日も帰りに、逆におみやげとして、“いま佐藤水産でイチオシ”らしい「さけっぴ」を貰ってしまった。
“あきあじ”(鮭のことだよね)の皮をカレー味で揚げてあります、ビールなんかに最高、某ジャガイモ系お菓子なんかより、私も気に入りました。













 )おもしろい。
)おもしろい。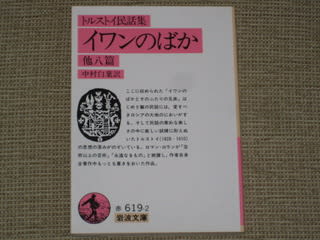




 休日なのに、なにいつもより働いてんだ、俺?
休日なのに、なにいつもより働いてんだ、俺?
 (って言っても、乗らないときでもリンゴやるくらいなんだけど。)
(って言っても、乗らないときでもリンゴやるくらいなんだけど。) 」と低くハナを鳴らして、こっちを見ます。
」と低くハナを鳴らして、こっちを見ます。









