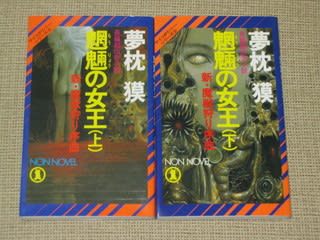村上龍 1991年 講談社文庫
ぢゃあ昨日のつづきということで、こちらは村上龍のエッセイ集。
エッセイとはいうものの、短いものだけぢゃなく、1982年に「写楽」という媒体で毎月連載してたらしい「コックサッカー・ブルース」なんて、文庫で90ページもある長いルポもある。
これは国内でSM撮影の現場に立ち会うだけぢゃなくて、ニューヨークまで行ってゲイとか乱交とかクスリとかがあふれてるクラブに入ってったりする。
そういうとこを見て回って、著者は、
>男達は疲れている。この取材を始めてから、多くの男達に会った。カメラマン、編集者、助手、モデルの手配師、縄師……みな一様に疲れている印象を受けた。(略)社会全体が疲れているのだ。それも、男性的部分、父性的部分が極度に披露している。それは、いいことでも悪いことでもなく、事実なのだ。(略)(p.75)
>女は違う。いきいきとしている。エネルギーが余っている。多勢のモデルに会ったが、暗い女は一人もいなかった。(略)(p.76)
という観察をしている。ふーむ、30年前からそうだったんだ。
>「男性の疲弊」の原因ははっきりしている。家畜化である。
>私たちは、生きのびるために、いつからか、家畜化の道を選んだのだ。(略)いいことでも悪いことでもない。事実なのだ。(p.77)
って結論を持ってるのが、ただ漠然と眺めた感想を言ってるだけぢゃないんで、たいしたものである。
1984年の「ロス・オリンピック」の章では、日本の水泳や陸上が弱くなったことについて、
>(略)昔の栄光とは、欧米のスイマーが楽しんで泳いでいた間隙を盗んで、ヒステリックな練習の末に勝ったものだから、比べようがないのである。(p.206)
と言って、次のような独自の日本論も披露している。
>日本は同じサイクルを歩んでいる。欧米からの新しいテクノロジー(イデオロギーを含む)の導入、日本的平準化によるノウハウの習得、ヒステリックな猛練習、つかの間の勝利、ミッドウェイでの決断力不足による致命的敗北、大玉砕、そしてまたテクノロジーの導入……こういうサイクルだ。(p.206)
著者のスポーツを観戦してのいろいろな感想はおもしろく、同じ1984年の「全仏オープンテニス」のとこでは、かの有名な一節(と思ってるのは私だけ?)、
>コナーズはアニマル、ボルグはマシン、と称される。と来ると、ここで、当然、アーティストが登場する。それが、ジョン・パトリック・マッケンロー・ジュニアである。(略)
>(略)当然後に続くのは、ロボットであるが、これがチェコスロヴァキアが生んだ怪物イワン・レンドルだ。(p.195)
ってやつが出てくる。
ちなみに、著者のテニス論は
>(略)テニスこそはおぞましく文化的なスポーツなのである。退屈しないために、貴族が考えたものなのだ。首狩り族の遊びから発生したスポーツとは違う。(略)原っぱや運動場での獲得形質が役に立たない。(略)
というものである。
もうひとつ、1984年のとこにある「水に遊ぶ 水に学ぶ」というのも95ページにわたる長編。「サムアップ」という媒体に84年4月号から翌年6月号まで掲載されてたらしい。
ここでハンターの斎藤令介氏と出会って、いっしょにカナダを旅したりする。なので、このなかには『愛と幻想のファシズム』で炸裂する、ハンターというか生態系というかの論理があちこちに現れる。
ズバズバ断言していく、いろんなフレーズが読んでて、きもちいい。
>だが私はとんでもない強運の持ち主なので最初にやった釣り、ハワイのトローリングで220ポンドのブラックマリンをあげた。(略)強運を得るコツは、絶対にあきらめないこと、それだけだ。(p.224)
とか、
>本当にいい思いを味わった人間は、もう一度それを得るために努力するのだ。生まれてから一度もいい思いをしたことがない、かわいそうな人間は、結局、「現実」と「記憶」のギャップにも気づかず、努力もせずに、つまらない一生を終えるのである。(p.228)
とか、
>例えば山を見るとする。大人はすぐに、その名前を知りたがる。山についての知識が情報だと考えているからだ。幼児は違う。知識などではなく、全知覚を山に集中する。その結果は明白である。山に関する深い情報を得るのは幼児の方だ。(略)知識が情報だと思っている人が多い。そんな人は絶対に出世しない。(p.235)
とか、
>(略)一攫千金の夢を持つ青年の顔はいつの時代にも明るいのだ。保障を与えられて毎日同じことを地道にやり続けなければならない青年の顔は、見るも無残に暗い。(p.237)
とか、
>(略)苦労が人間を磨くというのは大嘘だ。大成・出世した人だけが、そういう台詞を吐く。苦労だけの人間は、かわいそうな顔になって、みじめにさよならするだけなのである。(p.243)
とか、
>(略)遊んでばかりの奴は、後できっとだめになる、苦しくてもせっせとお勉強すれば後できっといいことがある、そういうことだが、これは嘘だ。これは資本主義の発想だ。私は社会主義者じゃないから、誤解を避けるために言うと、農耕民的発想なのだ。ものごとはもっとリアルだ。残酷だが、しようがない。だめな奴はアリになってもだめで、だめじゃないやつはキリギリスでも大丈夫というのが本当である。(p.261)
とか、
>そんなものは考えてもわからない。自分でやってみるしかない。何だって同じだ。実際にやった人間だけが快楽と情報を得ることができる。カタログや、他人の話から、快楽と情報を望むのは、奴隷への第一歩である。(p.286)
とか、枚挙にいとまがない。ちょっと若いサラリーマンへの苦言めいた匂いがするのは、そういう読者層をターゲットにもつ雑誌だったからぢゃなかろうか、そりゃしかたない、編集の意向もあるだろうさ。
どうでもいいけど、もうひとつ、このなかに私にえらく影響を与えた一節があったのを再発見した。
>もうひとつ、忘れられない言葉がある。アメリカのミステリー、たぶん「ペリー・メイスン」シリーズだったと思うが、タイトルもストーリーもまったく思い出せないが、その一節だけは憶えている。
>「自分が欲しいものがなにかわかっていない奴は、欲しいものを手に入れることができない」というものである。(p.279)
ってやつ、これは私も好きで、原典を見つけるべくメイスンのシリーズをぜんぶ読むはめになった。

ぢゃあ昨日のつづきということで、こちらは村上龍のエッセイ集。
エッセイとはいうものの、短いものだけぢゃなく、1982年に「写楽」という媒体で毎月連載してたらしい「コックサッカー・ブルース」なんて、文庫で90ページもある長いルポもある。
これは国内でSM撮影の現場に立ち会うだけぢゃなくて、ニューヨークまで行ってゲイとか乱交とかクスリとかがあふれてるクラブに入ってったりする。
そういうとこを見て回って、著者は、
>男達は疲れている。この取材を始めてから、多くの男達に会った。カメラマン、編集者、助手、モデルの手配師、縄師……みな一様に疲れている印象を受けた。(略)社会全体が疲れているのだ。それも、男性的部分、父性的部分が極度に披露している。それは、いいことでも悪いことでもなく、事実なのだ。(略)(p.75)
>女は違う。いきいきとしている。エネルギーが余っている。多勢のモデルに会ったが、暗い女は一人もいなかった。(略)(p.76)
という観察をしている。ふーむ、30年前からそうだったんだ。
>「男性の疲弊」の原因ははっきりしている。家畜化である。
>私たちは、生きのびるために、いつからか、家畜化の道を選んだのだ。(略)いいことでも悪いことでもない。事実なのだ。(p.77)
って結論を持ってるのが、ただ漠然と眺めた感想を言ってるだけぢゃないんで、たいしたものである。
1984年の「ロス・オリンピック」の章では、日本の水泳や陸上が弱くなったことについて、
>(略)昔の栄光とは、欧米のスイマーが楽しんで泳いでいた間隙を盗んで、ヒステリックな練習の末に勝ったものだから、比べようがないのである。(p.206)
と言って、次のような独自の日本論も披露している。
>日本は同じサイクルを歩んでいる。欧米からの新しいテクノロジー(イデオロギーを含む)の導入、日本的平準化によるノウハウの習得、ヒステリックな猛練習、つかの間の勝利、ミッドウェイでの決断力不足による致命的敗北、大玉砕、そしてまたテクノロジーの導入……こういうサイクルだ。(p.206)
著者のスポーツを観戦してのいろいろな感想はおもしろく、同じ1984年の「全仏オープンテニス」のとこでは、かの有名な一節(と思ってるのは私だけ?)、
>コナーズはアニマル、ボルグはマシン、と称される。と来ると、ここで、当然、アーティストが登場する。それが、ジョン・パトリック・マッケンロー・ジュニアである。(略)
>(略)当然後に続くのは、ロボットであるが、これがチェコスロヴァキアが生んだ怪物イワン・レンドルだ。(p.195)
ってやつが出てくる。
ちなみに、著者のテニス論は
>(略)テニスこそはおぞましく文化的なスポーツなのである。退屈しないために、貴族が考えたものなのだ。首狩り族の遊びから発生したスポーツとは違う。(略)原っぱや運動場での獲得形質が役に立たない。(略)
というものである。
もうひとつ、1984年のとこにある「水に遊ぶ 水に学ぶ」というのも95ページにわたる長編。「サムアップ」という媒体に84年4月号から翌年6月号まで掲載されてたらしい。
ここでハンターの斎藤令介氏と出会って、いっしょにカナダを旅したりする。なので、このなかには『愛と幻想のファシズム』で炸裂する、ハンターというか生態系というかの論理があちこちに現れる。
ズバズバ断言していく、いろんなフレーズが読んでて、きもちいい。
>だが私はとんでもない強運の持ち主なので最初にやった釣り、ハワイのトローリングで220ポンドのブラックマリンをあげた。(略)強運を得るコツは、絶対にあきらめないこと、それだけだ。(p.224)
とか、
>本当にいい思いを味わった人間は、もう一度それを得るために努力するのだ。生まれてから一度もいい思いをしたことがない、かわいそうな人間は、結局、「現実」と「記憶」のギャップにも気づかず、努力もせずに、つまらない一生を終えるのである。(p.228)
とか、
>例えば山を見るとする。大人はすぐに、その名前を知りたがる。山についての知識が情報だと考えているからだ。幼児は違う。知識などではなく、全知覚を山に集中する。その結果は明白である。山に関する深い情報を得るのは幼児の方だ。(略)知識が情報だと思っている人が多い。そんな人は絶対に出世しない。(p.235)
とか、
>(略)一攫千金の夢を持つ青年の顔はいつの時代にも明るいのだ。保障を与えられて毎日同じことを地道にやり続けなければならない青年の顔は、見るも無残に暗い。(p.237)
とか、
>(略)苦労が人間を磨くというのは大嘘だ。大成・出世した人だけが、そういう台詞を吐く。苦労だけの人間は、かわいそうな顔になって、みじめにさよならするだけなのである。(p.243)
とか、
>(略)遊んでばかりの奴は、後できっとだめになる、苦しくてもせっせとお勉強すれば後できっといいことがある、そういうことだが、これは嘘だ。これは資本主義の発想だ。私は社会主義者じゃないから、誤解を避けるために言うと、農耕民的発想なのだ。ものごとはもっとリアルだ。残酷だが、しようがない。だめな奴はアリになってもだめで、だめじゃないやつはキリギリスでも大丈夫というのが本当である。(p.261)
とか、
>そんなものは考えてもわからない。自分でやってみるしかない。何だって同じだ。実際にやった人間だけが快楽と情報を得ることができる。カタログや、他人の話から、快楽と情報を望むのは、奴隷への第一歩である。(p.286)
とか、枚挙にいとまがない。ちょっと若いサラリーマンへの苦言めいた匂いがするのは、そういう読者層をターゲットにもつ雑誌だったからぢゃなかろうか、そりゃしかたない、編集の意向もあるだろうさ。
どうでもいいけど、もうひとつ、このなかに私にえらく影響を与えた一節があったのを再発見した。
>もうひとつ、忘れられない言葉がある。アメリカのミステリー、たぶん「ペリー・メイスン」シリーズだったと思うが、タイトルもストーリーもまったく思い出せないが、その一節だけは憶えている。
>「自分が欲しいものがなにかわかっていない奴は、欲しいものを手に入れることができない」というものである。(p.279)
ってやつ、これは私も好きで、原典を見つけるべくメイスンのシリーズをぜんぶ読むはめになった。