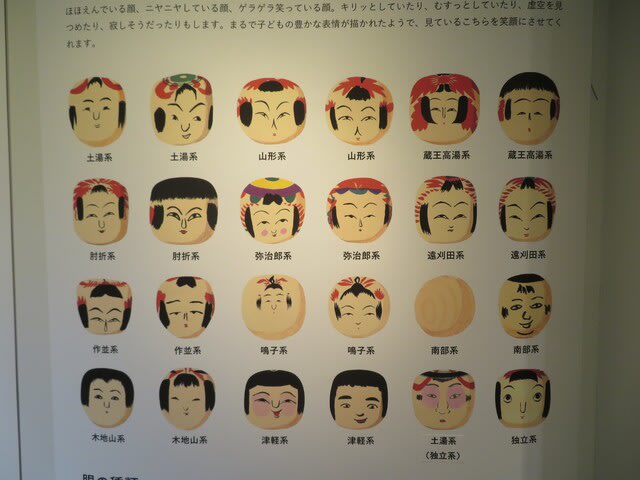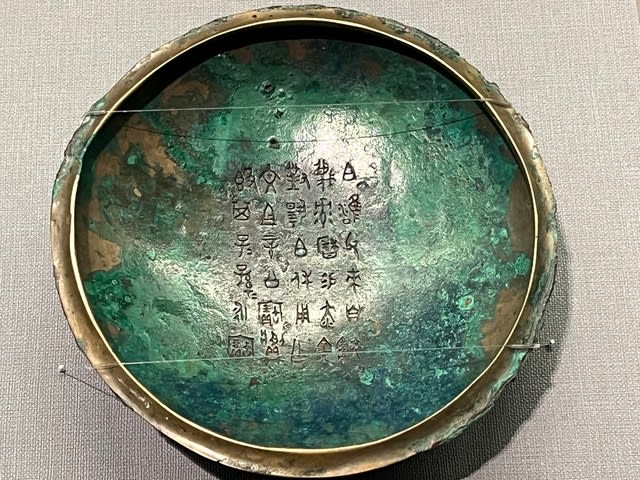阪神・淡路大震災から、28年という。
当日は、私は、出勤後、午後から、神戸に出張予定。
出張準備をして出勤したものの断念。
3月に延期して行ったが、その時点でも、まだ鉄道寸断、倒壊家屋多数という状況だった。
とにかく、当日の情報伝達の遅かったこと。
危機管理に弱い政権だったことも災いした。
3.11の時も。

今日は、泉屋博古館の、不変/普遍の造形展へ。
青銅器の住友コレクション。
リニューアル記念第3弾という。
第1弾には行ったが、洋画中心の展示で、それも良かった。

青銅器展には、何度か行ったが、似たような青銅器がただただ並んでいるという印象が強かった。
本展では、少数精鋭で、その時代や用途毎に特徴のある青銅器を、わかりやすく展示してくれていて、ひじょうによかった。
本展に合わせて、とんぼの本も出ていて、本書片手に見ると、理解が進む。
もちろん、中国本土には、もっとすごいものがあるが、日本にあるものの中では、一級品が並んでいる。
順不同だが、写真撮影可だったので、ちょっと紹介したい。
漢字が、PCで出ないものが多いので、ひらがなで紹介することをお許し願いたい。

いきなりこの太鼓型青銅器。
初めて見たが、世界に2例しかないという。
重さ71kg!
これが、今から3,000年以上前に作られたというから、あきれるしかない。
”きじんこ”と名付けられている。
青銅器の名前は、文字が刻まれている場合は、わかるが、その他は、後代の推測という。
北宋時代に、研究が進んだ。

青銅器の魅力というと、まずその造形、そして、デザインの繊細さと、不思議さ、そして、その中の文字と言えるだろうか。
これは、”ちょうがいここ”。
すばらしい造形。
酒器という。
傾けると、鳥の頭の姿をした蓋が開くという。
さぞ、酒宴も盛り上がったろう。
後代の正倉院に収められた酒器にも、似ている。

これは、高校の漢文でも習った”鼎”。
肉入りスープを煮込んだ。
権威の象徴だった。
どっしり感大。

これは、”ほ”。
穀物を盛るための器というが、上半分が蓋なのだという。
初めて見た。
上側にも、下側にも、足がついている。

このスタイルも初めて。
”豆(とう)”という。
高坏だが、様々な食物が盛られたという。
”豆” の文字の形も、この姿から来ているというか驚きだ。

これまた違った趣向で”神獣”。
何かの台座に取り付けられていたと思われるが、詳細は不明。
表情は、ユーモラスだ。
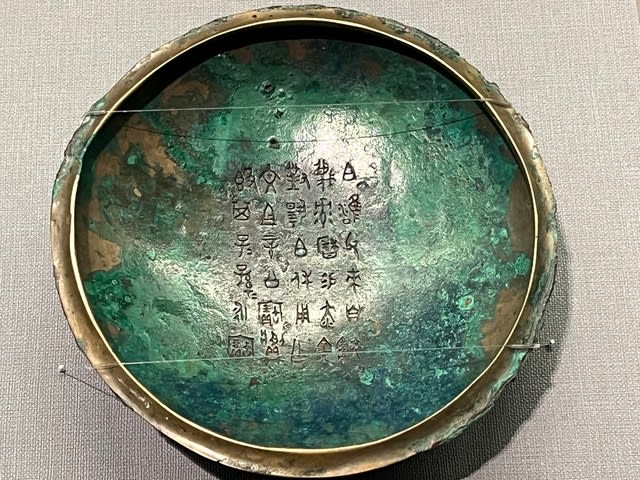
これは、文字がはっきり分かる例。
金文と言われるが、これも鋳型から作ったというから驚き。
凄い執念であったことがわかる。

これは、まさに名品。
青銅器でよく見られるデザイン。
勘違いしていたのだが、二つの目に見えるのは、左右2匹の神獣の目なのだという。
”とうてつもんほうい”と呼ばれるが、”とうてつ”は、伝説上の怪獣の名という。
見事だ。

これまた不思議な形をしているが、”こきょうじこう”と言われ、題材は、虎とミミズクの融合体という。

これは、”こはく”といって、釣鐘の一種という。
紀元禅1世紀のもので、最も古い作例という。
横の飾りが、虎であることから、この名になった。

これまた見事。
”とうてつもんゆうがいほう”という。
龍の当時の姿が、遺されている。
その後の龍の姿とはかなり違う。

これも目玉。虎がメインで、人間、蛇、龍、獏、鹿などが、配されている。
”こゆう”と呼ばれる。

これは、ミミズク。
”しきょうそん”。
ミミズクは、不吉な鳥として忌み嫌われていたという。
それにしても、堂々とした造形だ。

これは、ユーモラスなミミズクかフクロウ。
”かゆう”と呼ばれるが、何ともユニーク。
2匹が、背中合わせにくっついている。

これは、楽器。
”ひょうきょうしょう”と呼ばれるが、14規セットという。
銘文もあり、紀元前5世紀の物と確認される。
銅鐸の原型であることは、明らか。

これも目玉の一つ。”ちもんほうろ”。
建物のように見えるが、下に火種を入れて、上部で、煮炊きをする。
下のドアは開くようになっている。
左右に門番がいるが、罪人で、逃げられないように、足を切り落とされていたという。

古鏡は、青銅器の範疇に入るかわからないが、この辺からは、日本の古代と被ってくる。
LTVのデザインは、ユニーク。
後代のものより、幾何学的なデザイン。

画文帯同向式神獣鏡。
重文指定。
神仙、神獣が同じ方向を向く同行式と呼ばれる。
中段に、東王公、西王母。
上代に、伯牙(はくが)。
伯牙は、伝説上の琴の名手。

三角縁四神四獣鏡。
中国で出土されたとされるが、どこで作られたか判然とはしていない。
日本で多く見つかり、中国産なのか、日本産なのか、議論になっている。
日本で、見つかるものより、厚い気がするが。
最下段には、東王公、西王母らしい姿も。
3世紀頃のものとされる。
これも、重文に指定されている。

最後は、住友コレクションの歴史。
本書は、清時代のものだが、ここに評されている逸品が、今目の前にある。

これが、最初に入手したもの。
きもんつつがたゆう。
茶会の鑑賞品として収集が始まったというが、今や、世界に冠たるコレクションとなっている。
清の崩壊により、中国のコレクターが取集品を手放したことも奏功したようだ。
訪れてよかった。