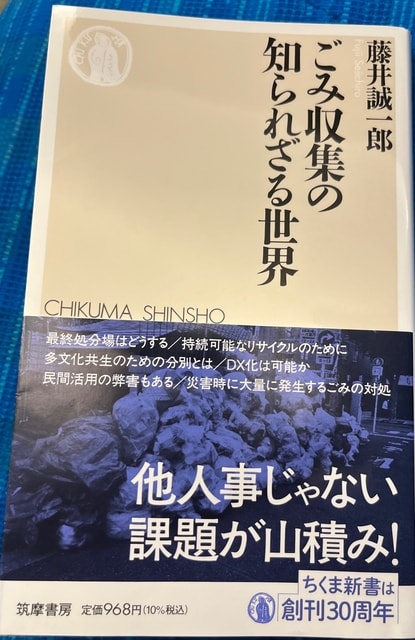今日は、大晦日。
気温は、低いが、穏やかな天気。
夜、家族が久しぶりに集合予定だったが、インフル懸念により、全員集合とはならなくなった。
とは言え、どうにか今年も無事大晦日を迎えることができた。
支えてくれたみなさんに感謝。

モンゴルシリーズは、年内に完結できなかったが、ほぼ、最終回近くまで来れた。
つぎに、チンギス・ハーン博物館から歩ける場所にあるスフバートル広場へ。
VIVANTでは、バルカ共和国の首都クーダンの中心地として何度も登場したから覚えていた。
役所さんたちへの馬に乗る指導などは、ガイドさんが、行ったとのこと。
ロケは許可の関係で、5時から7時という早朝にエキストラを集めて行われたとのこと。
許可が出ただけでも奇跡的?
早く再放送が見たい?

この建物は、国立ドラマ劇場。
タシケントと同様、日本兵の捕虜によって建設されたという。
VIVANTでは、バルカ国際銀行の外観として使われた。

広場の向かい側にある近代的なビル群。
ホテル・ブルースカイは、みなとみらいのビルにちょっと似てる?

向かって右側の建物。
文化宮殿だったかな?

スフバートル像。
モンゴルの革命家。
中国人を駆逐し、近代モンゴル軍の父と呼ばれる。

この建物も、VIVANTに出てきたと思う。

正面にチンギス、両脇を、オゴタイ、フビライが固める。
政府庁舎なので、中は、警備が厳しそう。
気温は、低いが、穏やかな天気。
夜、家族が久しぶりに集合予定だったが、インフル懸念により、全員集合とはならなくなった。
とは言え、どうにか今年も無事大晦日を迎えることができた。
支えてくれたみなさんに感謝。

モンゴルシリーズは、年内に完結できなかったが、ほぼ、最終回近くまで来れた。
つぎに、チンギス・ハーン博物館から歩ける場所にあるスフバートル広場へ。
VIVANTでは、バルカ共和国の首都クーダンの中心地として何度も登場したから覚えていた。
役所さんたちへの馬に乗る指導などは、ガイドさんが、行ったとのこと。
ロケは許可の関係で、5時から7時という早朝にエキストラを集めて行われたとのこと。
許可が出ただけでも奇跡的?
早く再放送が見たい?

この建物は、国立ドラマ劇場。
タシケントと同様、日本兵の捕虜によって建設されたという。
VIVANTでは、バルカ国際銀行の外観として使われた。

広場の向かい側にある近代的なビル群。
ホテル・ブルースカイは、みなとみらいのビルにちょっと似てる?

向かって右側の建物。
文化宮殿だったかな?

スフバートル像。
モンゴルの革命家。
中国人を駆逐し、近代モンゴル軍の父と呼ばれる。

この建物も、VIVANTに出てきたと思う。

正面にチンギス、両脇を、オゴタイ、フビライが固める。
政府庁舎なので、中は、警備が厳しそう。