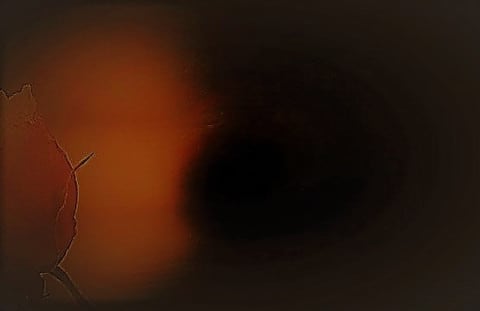
年末に 第八章「かえりみ」のところで終えたのは、 必ずしも切れの良い章だったから というわけではなくて、 出来れば半分の12章まで行けたら良かったのですけど、 年末に心慌ただしく「冬の旅」について考えるのもどうかなと思い あそこまでにしました。 …さて、 つづきです。
第9章「鬼火」
ボストリッジさんは まず《鬼火》という現象が近代になって化学的に研究されていった歴史を説明します。 現代でも プラズマだとか メタンガスだとか 様々言われているようですが、 ミュラーが詩作した時代 そしてシューベルトが作曲した時代には まだまだ《鬼火》は 人を惑わす妖しい火として怖れられていたことでしょう。。
前章「かえりみ」までで 旅人は凍った川を渡り 山深くへ登っていったと思われます。 そうして、 誘うような 惑わすような 《鬼火》を今 見ています。
ボストリッジさんは その《鬼火》の誘うような感じ、 追えばふっと逃げていくような感じを、 楽譜に沿ってとても詳細に解説を加えています。 その解説に助けられて 私にもこの《鬼火》と旅人の姿がなんとなく見えてきました… (本文には触れませんので、念の為)
***
追えば逃げる、、 でも 遠くでぼおっと幽かに燃える火… 、、これまでの歌の中で聞き覚えのある旋律の変容がこの9曲で表れているのも、 これが《幻惑》であることを意味しているようです。
けれども その姿は恐怖というより どこかおとぎ話的な可愛さもあり(ピアノの感じも) なんだか頭の中に オーギュスト・ルドンの描く《眼》のお化けみたいな感じが浮かびました、、 時代も場所もシューベルトとは違いますけれど…
でも その誘いに惑わされてついて行ってはいけないことは この旅人にも分かっているようです。 自分が見ているものが《鬼火》であることも 分かっているようです。 それなのに、、 (迷ってもいいさ)というような どこか投げやりな旅人の言葉(詞)が第一連、 第二連にあらわれます。
Life's but a walking shadow, a poor player
人生を影法師に喩え、 自らを哀れな役者 と詠ったのは シェイクスピアの「マクベス」ですが、、 ここでの旅人は《鬼火》と分かっていて その惑わしの中に自分を投じて、 そしてどこかでその自分を嗤っているかのようです。
Unsre Freuden, unsre Wehen,
alles eines Irrlichts Spiel!
《喜び》も 《悲しみ》も すべては《鬼火》の戯れ(ゲーム)…
鬼火を英語では 《will o’ the wisp》 直訳すれば 「たなびく煙の意志(のように当てにならないもの)」という感じ? 、、でも 旅人は《鬼火》の戯れについて当てのない方向へと歩いていきます…
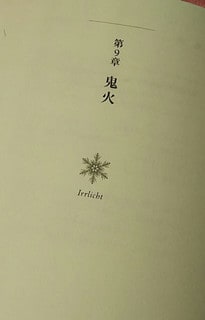
第6章「あふれ流れる水」Wasserflut で、 旅人は自分の流した涙の流れは やがて愛する人もとへ… と考えました。 しかし、 第9章の第3連で旅人が辿って行こうとしているのは 「水の涸れた谷」なのです。 その谷を下って行こう、、と。。
… 旅人さん 貴方は山へ向かっていたはずでは…?
涸れ谷を行ってはいけません、、 もう涙も涸れてしまったから…? 疲れ切ってしまったから…?
、、 でもそこには水は流れていないのよ、、
涸れ谷の先にあるのは…
「Grab」 = grave
、、 旅人は分かりつつ その谷を下っていこうとしているのでしょうか、、
***
ところで、、 《鬼火》が プラズマであれメタンガスの自然発火であれ、、 川も凍結するような真冬に鬼火って発生するものなのでしょうか… なんとなく 夏のイメージのある鬼火…
、、 それとも この旅人が見ている鬼火そのものが 幻の火 なのでしょうか…
そんなことを考えながら検索していたら こんな「真冬の鬼火」に出会いました。。 こんな素敵な鬼火ならば誘われてついて行ってみたいです、、 たとえ 「地獄」と名の付く谷がその先に待っていようとも…… 笑 美しい幻想的な鬼火ですね。。
鬼火の路 幻想と神秘の谷 (登別国際観光コンベンション協会)>>
…… 北では暴風雪の予報が出ています
暖かくして お気をつけてね …

























