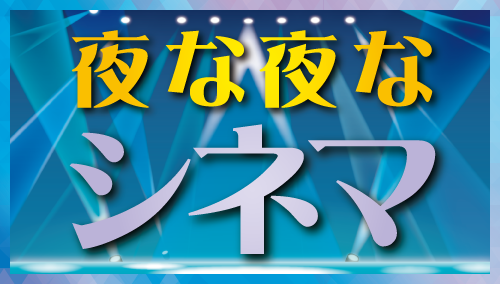『さあ帰ろう、ペダルをこいで』(英題:The World is Big and Salvation Lurks around the Corner)
監督:ステファン・コマンダレフ
出演:ミキ・マノイロヴィッチ,カルロ・リューベック,フリスト・ムタフチェフ,
アナ・パパドプル,ドルカ・グリルシュ,リュドミラ・チェシメジーエヴァ他
先週の土曜日はティム・バートン監督の新作封切り日。
しかし、諸般の事情からネット予約して出かけることはできず、
すでに満席かもしれないし、来月も上映しているだろうからと、
この日はあきらめてシネマート心斎橋へ。
結果、心からよかったと思える作品に出逢えました。
2008年のブルガリア/ドイツ/ハンガリー/スロヴェニア/セルビア作品です。
ドイツに暮らす30歳のアレックスは、両親と車で移動中、事故に遭う。
運転していた父ヴァスコと助手席に座っていた母ヤナは死亡。
病院に搬送されたアレックスは意識を取り戻すが、何も思い出せない。
ブルガリアに住むヤナの両親であるバイ・ダンとスラドカは、
娘と婿の訃報を聞くとともに、孫が無事であることを知る。
孫のことが心配でならないバイ・ダンは、ブルガリアからドイツへ。
25年ぶりの再会を果たすのだが……。
病院のベッドの上で自分の名前すら思い出せないアレックスは、
バイ・ダンに「ブルガリアのおじいちゃんだよ」と言われて不信感をあらわにします。
幼い頃、バックギャモンの名手であるバイ・ダンにくっついて離れなかったのに。
悲しみに暮れてはいられないバイ・ダンは、
記憶を呼び戻す手がかりをみつけようと、アレックスの自宅に不法侵入。
かいま見える孫の暮らしは、取説を翻訳する仕事で日銭を稼ぎ、
部屋にこもりっきりで、たまに隣のバーにひとりで飲みに行くぐらい。
アレックスの誕生日に贈ったバイ・ダン手製のバックギャモンは埃をかぶっていました。
バイ・ダンはそのバックギャモンを病院に持ち込むと、
生きる気力をまるで見せないアレックスをベッドから引きずり下ろします。
俺と話すのが嫌ならばそれでいい。勝負しろ。
バックギャモンのやり方がわかるのは、記憶がどこかにある証拠だと。
最初は疎ましそうだったアレックスに、やがて笑顔がこぼれ始めます。
医師たちは、無理に思い出させては混乱するだけだと、
ヴァスコとヤナが死亡したこともアレックスには伝えません。
そんな病院の治療法を疑問視するバイ・ダンは、アレックスに事実を暴露。
そして、故郷のブルガリアへとタンデム(二人乗り)自転車で向かいます。
1970年代後半~1980年代と現在が交錯して映し出されます。
共産党政権下、アレックス一家がバイ・ダンとスラドカにも内緒で
ブルガリアを離れなければなかった理由が明らかにされ、
亡命希望者を待ち受ける過酷な日々も本作から知らされます。
イタリアの難民キャンプでの食事はパスタ、パスタ、パスタ。
しかも365日でろんでろんのミートソースなんて話も。
要所要所で必ず登場するのがバックギャモン。
人生はサイコロと同じ。どんな目が出るか、それは時の運と自分の才覚次第。
不運を嘆くな。サイコロを振るのは自分なんだから。
バイ・ダンのぶれないポリシーと生き方に勇気づけられます。
ラストシーンもお見事。きっと忘れられないでしょう。
世界は目の前に広がっている。救いはどこにでもある。
印象に残ったこの台詞が原題であることを後から知りました。
「記憶をなくすのも悪いことばかりじゃない、
だって、これが僕の初恋になる」という台詞も印象深く。
しかし、この監督の名前、「コマンタレブ~」って
からかわれそうやなぁと思うのは私だけ?
監督:ステファン・コマンダレフ
出演:ミキ・マノイロヴィッチ,カルロ・リューベック,フリスト・ムタフチェフ,
アナ・パパドプル,ドルカ・グリルシュ,リュドミラ・チェシメジーエヴァ他
先週の土曜日はティム・バートン監督の新作封切り日。
しかし、諸般の事情からネット予約して出かけることはできず、
すでに満席かもしれないし、来月も上映しているだろうからと、
この日はあきらめてシネマート心斎橋へ。
結果、心からよかったと思える作品に出逢えました。
2008年のブルガリア/ドイツ/ハンガリー/スロヴェニア/セルビア作品です。
ドイツに暮らす30歳のアレックスは、両親と車で移動中、事故に遭う。
運転していた父ヴァスコと助手席に座っていた母ヤナは死亡。
病院に搬送されたアレックスは意識を取り戻すが、何も思い出せない。
ブルガリアに住むヤナの両親であるバイ・ダンとスラドカは、
娘と婿の訃報を聞くとともに、孫が無事であることを知る。
孫のことが心配でならないバイ・ダンは、ブルガリアからドイツへ。
25年ぶりの再会を果たすのだが……。
病院のベッドの上で自分の名前すら思い出せないアレックスは、
バイ・ダンに「ブルガリアのおじいちゃんだよ」と言われて不信感をあらわにします。
幼い頃、バックギャモンの名手であるバイ・ダンにくっついて離れなかったのに。
悲しみに暮れてはいられないバイ・ダンは、
記憶を呼び戻す手がかりをみつけようと、アレックスの自宅に不法侵入。
かいま見える孫の暮らしは、取説を翻訳する仕事で日銭を稼ぎ、
部屋にこもりっきりで、たまに隣のバーにひとりで飲みに行くぐらい。
アレックスの誕生日に贈ったバイ・ダン手製のバックギャモンは埃をかぶっていました。
バイ・ダンはそのバックギャモンを病院に持ち込むと、
生きる気力をまるで見せないアレックスをベッドから引きずり下ろします。
俺と話すのが嫌ならばそれでいい。勝負しろ。
バックギャモンのやり方がわかるのは、記憶がどこかにある証拠だと。
最初は疎ましそうだったアレックスに、やがて笑顔がこぼれ始めます。
医師たちは、無理に思い出させては混乱するだけだと、
ヴァスコとヤナが死亡したこともアレックスには伝えません。
そんな病院の治療法を疑問視するバイ・ダンは、アレックスに事実を暴露。
そして、故郷のブルガリアへとタンデム(二人乗り)自転車で向かいます。
1970年代後半~1980年代と現在が交錯して映し出されます。
共産党政権下、アレックス一家がバイ・ダンとスラドカにも内緒で
ブルガリアを離れなければなかった理由が明らかにされ、
亡命希望者を待ち受ける過酷な日々も本作から知らされます。
イタリアの難民キャンプでの食事はパスタ、パスタ、パスタ。
しかも365日でろんでろんのミートソースなんて話も。
要所要所で必ず登場するのがバックギャモン。
人生はサイコロと同じ。どんな目が出るか、それは時の運と自分の才覚次第。
不運を嘆くな。サイコロを振るのは自分なんだから。
バイ・ダンのぶれないポリシーと生き方に勇気づけられます。
ラストシーンもお見事。きっと忘れられないでしょう。
世界は目の前に広がっている。救いはどこにでもある。
印象に残ったこの台詞が原題であることを後から知りました。
「記憶をなくすのも悪いことばかりじゃない、
だって、これが僕の初恋になる」という台詞も印象深く。
しかし、この監督の名前、「コマンタレブ~」って
からかわれそうやなぁと思うのは私だけ?