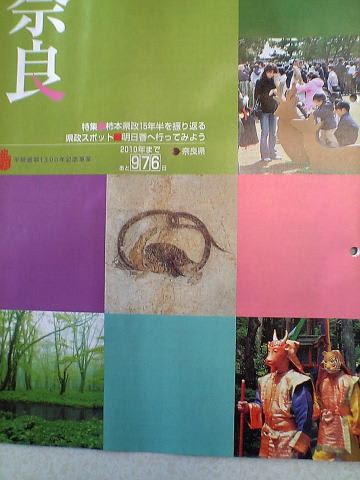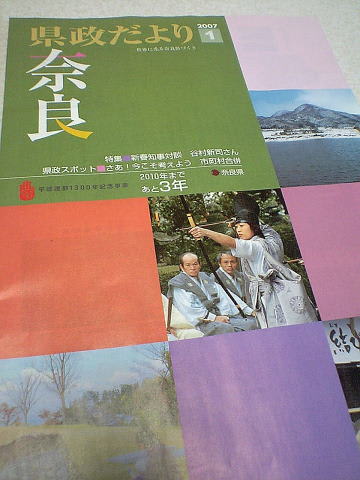3月末に発刊された「奈良・大和路まほろば巡礼」は県の企画編集本。
売れ行き具合はどうなんだろうと気にかかる。
奈良を知り尽くした17名の案内人が20のテーマに亘って解き明かす奈良・大和路の巡礼本は平城遷都1300年に向けて発刊された記念すべきガイドブック。
今まで取り上げられなかったテーマだけに読めば読むほど新鮮な感動を覚える。
地図も詳しく載っているので判りやすい。
えっ、こんな神社も載せてるんだと、編集の方々には頭を下げてしまう。
カラー写真が満載で見応えある本にできあがっています。
なにを隠そう、私も写真で協力したひとり。
「龍神の棲む聖地、室生」で掲載された一枚の写真は鮮明に覚えている。
秋祭りの下見にでかけた際、境内には氏子さんらが集まっていた。
尋ねれば、昼から龍神の勧請縄を作るという。
それならば、と急遽予定を変更して作るところから取材慣行させてもらった龍神を祀る
大木杉の勧請縄掛けの1シーンだ。
もう一枚は海神社の雨乞いの太鼓踊りである「
いさめ踊り」。
ストロボをあてずに、躍動的に太鼓を打ち鳴らすシーンが撮れないものかとシャッターを押しまくった記憶がある。
案内人には誌面をこんな写真で飾って申しわけないと低頭しましたのです。
掲載写真はこれだけで済まなかった。
○○テーマはないですか、□□テーマはないですかと注文多く。
そのたびに写真庫(?)から蔵出し作業。
ないようで出てくるのが不思議なくらいだと自分でも感心する。
これでいかがでしょうかとやりとりするも、著者の意向に沿わなかったのでしょうか、結果的に採用されず。
やれやれと思ったのもつかの間。
年中行事に使える写真がないやろかと、○○に□□に△△とご注文。
そのたびにありますねぇと回答。
次から次へのご注文に、一ヶ月間は確認、送付、確認、送付の連続日々。
締め切りが刻々と近づき、出版局の編集人はどれほど胃を痛めた(と思う)のでしょうか。
ようやく発刊されたときはこちらもほっとしました。
ちなみに掲載されたのは五條市篠原の「
篠原踊り」、河合町廣瀬神社の「
砂かけ祭」、天理市大和神社の「
ちゃんちゃん祭」、橿原市久米寺の「
練供養」、橿原市地黄町の「
すすつけ祭」、奈良市唐招堤寺の「中興忌梵綱会(
うちわまき)」、三郷町龍田大社の「
風鎮大祭」、吉野山金峯山寺の「
蓮華会・
蛙飛び」、橿原市坊城町の「
ほうらんや火祭」、桜井市談山神社の「
秋の蹴鞠祭」だ。
カット割りが上手いなぁと編集者に感心する。
(H20. 5.15 SB912SH撮影)