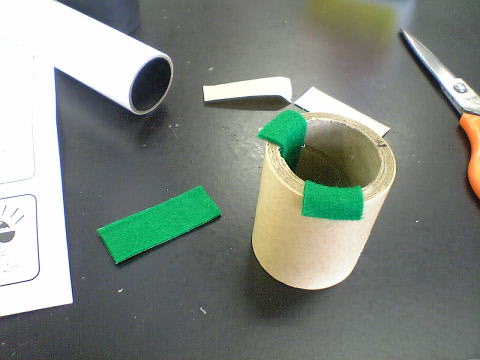カットシートを張ると個性豊かなオリジナル天体望遠鏡のできあがり。
そして太陽に向けてはは絶対いけませんと最後の勧告。
東大寺大仏殿の屋根を附小からとらえてみました。
ケータイデジカメなのでもやーっとしてますが肉眼では非常に綺麗に見えました。
本ちゃんの27日が楽しみです。
(H19.1.13 V603SH撮影)
そして太陽に向けてはは絶対いけませんと最後の勧告。
東大寺大仏殿の屋根を附小からとらえてみました。
ケータイデジカメなのでもやーっとしてますが肉眼では非常に綺麗に見えました。
本ちゃんの27日が楽しみです。
(H19.1.13 V603SH撮影)