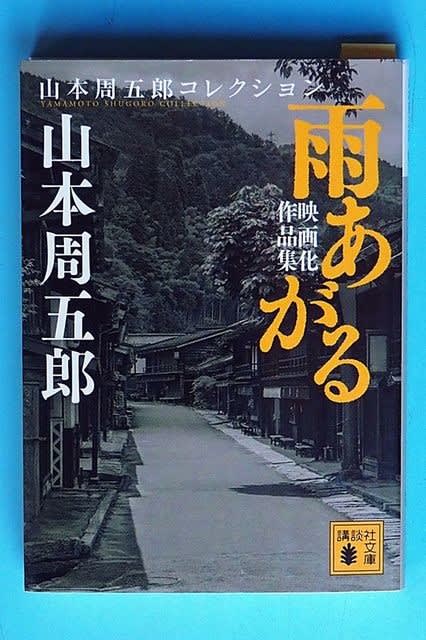(講談社学芸文庫に付された室生犀星の写真よりスキャンさせていただきました)
けふはえびのように悲しい
角やらひげやら
とげやら一杯生やしてゐるが
どれが悲しがつてゐるのか判らない。
ひげにたづねて見れば
おれではないといふ。
尖つたとげに聞いて見たら
わしでもないといふ。
それでは一体誰が悲しがつてゐるのか
誰に聞いてみても
さつぱり判らない。
生きてたたみを這うてゐるえせえび一疋。
からだじうが悲しいのだ。
タイトルにある通り、これは室生犀星の絶筆「老いたるえびのうた」の全編であります。
犀星はよく知られているように、金沢で生まれ、1962年(昭和37)に、肺がんにより死去。72歳だと、いまのわたしと同じ歳になります。
室生犀星については以前にも書いたことがあったはず。
講談社文芸文庫が手許にありますが、「蜜のあわれ」「われはうたえどもやぶれかぶれ」の2つが読みたくてね♬
「われはうたえどもやぶれかぶれ」を読むついでに、ササっと読み返しました、とても短い作品なので。
「われはうたえどもやぶれかぶれ」ははっきりいえば、“悪文”の典型。だけど、身に沁みる、身に沁みるんですなあ。
わたしがそれだけ歳を重ねたということでしょう。
おしっこが出ないと騒いでいる。カテーテを挿入するのが、痛い、痛いと。
文脈がひどく乱れているため、最後まで読み通すのが、いささか難儀。
ひと足さきにいった宇野浩二の記憶、入院中の看護婦やほかの患者のこと、そのほか気持ちのおもむくまま、あれやこれやと綴っています。
・・・というか、口述筆記なのかもしれません。
「うまく書いてやろう」なんて意識はほとんどない^ωヽ*
自身の病苦を、突き放してこのように書いた作家は、ほかにいないと思える。
彼には死期がせまっているのですよ、死期が。
元気だったころ、望郷あるいは恋のうたをたくさん書いてきた室生犀星が、最後に書き留めた詩だとかんがえると、痛切なものが、そくそくと身にせまってくるな。だれもが通らなければならない道ですから。
こんな悲しい詩を、これまで読んだ経験あったかなあ。
生きてたたみを這うてゐるえせえび一疋
老いたるえびはもちろん、病院のベッドに横たわる犀星自身。
究極の暗喩だと、あらためてかんがえてみるのです( -ω-)
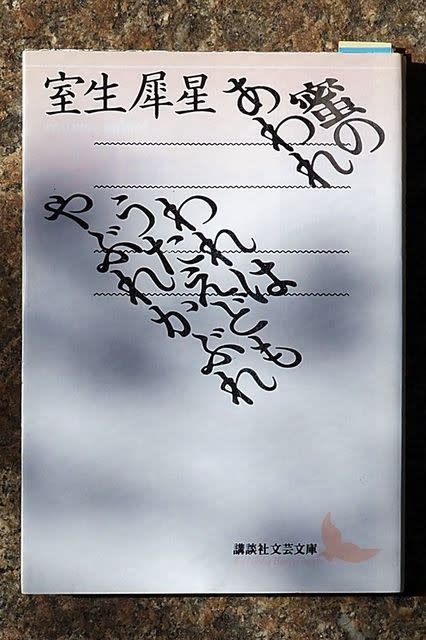
もう一つ取り上げておきたいのが、山本周五郎の「街へゆく電車」(「季節のない街」の一編、黒澤明が「どですかでん」として映画化)。
忘れることができない名編である。
「季節のない街」は、16-7年前、最後の1ページまで読んでいまする。ことに「街へゆく電車」はインパクトが大きかったなあ。
六ちゃんという人間のリアリティは、大抵の読者が感嘆を惜しまないだろう。いったいこういう作品の材料を、作者はどこから拾ってきたものかしら?
「どでどで、どでどで、どですかでん」
単なるどですかでんが、交差する線路の継ぎ目で軋り音が変わる。
この表現の凄み。
講談社文庫の映画化作品集「雨あがる」は、つぎの六編が収めてある。
1.狂女の話(「赤ひげの第一話」
2.五辨の椿(第六話)
3.深川安楽亭
4.街へゆく電車(「季節のない街」の一編)
5.ひとごろし
6.雨あがる
また「深川安楽亭」は、どん底でのたうつように生きる男たちが、離れたり近づいたり、同心円をえがくように構成された、奥行きの深い逸品。
わたしはこの作品の“異様な雰囲気”に浸り込んでしまった。
《その客は初めてきた晩に「おれはここを知っている」と云った。》
この冒頭の一言が、ラストに意味をもってくるのです。
ネットや手持ちの山本周五郎の本をひっくり返して調べてみたのですが、彼にはこういったレベルの作品が、短編で20-30編はあるようです、むろん評価の基準にもよりますが。
山本周五郎文学は、過去にずいぶんと読んできた・・・と思ったのですが、まったくといっていいほど、読めていなかったですなあ(;´д`)
2024年の現在から振り返ると、室生犀星は極めて少数ですが、山本周五郎を読みたがる読者は多数派に属するでしょうね。
新潮文庫の現行版だけで、何巻あるのかしら?
あちらこちらあふれて平積みとなったものやら、本棚の蔵書やらをひっくり返して眺めていまする。
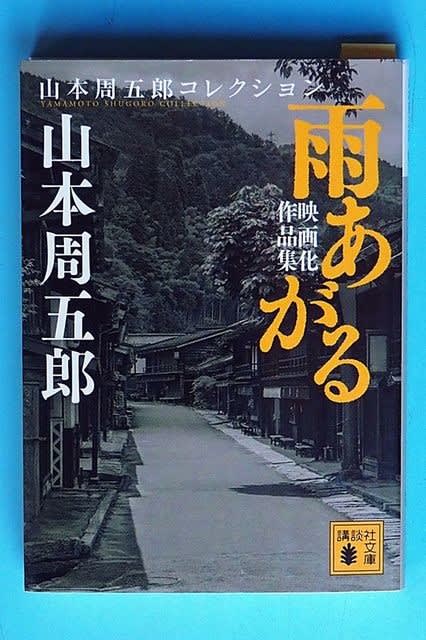
けふはえびのように悲しい
角やらひげやら
とげやら一杯生やしてゐるが
どれが悲しがつてゐるのか判らない。
ひげにたづねて見れば
おれではないといふ。
尖つたとげに聞いて見たら
わしでもないといふ。
それでは一体誰が悲しがつてゐるのか
誰に聞いてみても
さつぱり判らない。
生きてたたみを這うてゐるえせえび一疋。
からだじうが悲しいのだ。
タイトルにある通り、これは室生犀星の絶筆「老いたるえびのうた」の全編であります。
犀星はよく知られているように、金沢で生まれ、1962年(昭和37)に、肺がんにより死去。72歳だと、いまのわたしと同じ歳になります。
室生犀星については以前にも書いたことがあったはず。
講談社文芸文庫が手許にありますが、「蜜のあわれ」「われはうたえどもやぶれかぶれ」の2つが読みたくてね♬
「われはうたえどもやぶれかぶれ」を読むついでに、ササっと読み返しました、とても短い作品なので。
「われはうたえどもやぶれかぶれ」ははっきりいえば、“悪文”の典型。だけど、身に沁みる、身に沁みるんですなあ。
わたしがそれだけ歳を重ねたということでしょう。
おしっこが出ないと騒いでいる。カテーテを挿入するのが、痛い、痛いと。
文脈がひどく乱れているため、最後まで読み通すのが、いささか難儀。
ひと足さきにいった宇野浩二の記憶、入院中の看護婦やほかの患者のこと、そのほか気持ちのおもむくまま、あれやこれやと綴っています。
・・・というか、口述筆記なのかもしれません。
「うまく書いてやろう」なんて意識はほとんどない^ωヽ*
自身の病苦を、突き放してこのように書いた作家は、ほかにいないと思える。
彼には死期がせまっているのですよ、死期が。
元気だったころ、望郷あるいは恋のうたをたくさん書いてきた室生犀星が、最後に書き留めた詩だとかんがえると、痛切なものが、そくそくと身にせまってくるな。だれもが通らなければならない道ですから。
こんな悲しい詩を、これまで読んだ経験あったかなあ。
生きてたたみを這うてゐるえせえび一疋
老いたるえびはもちろん、病院のベッドに横たわる犀星自身。
究極の暗喩だと、あらためてかんがえてみるのです( -ω-)
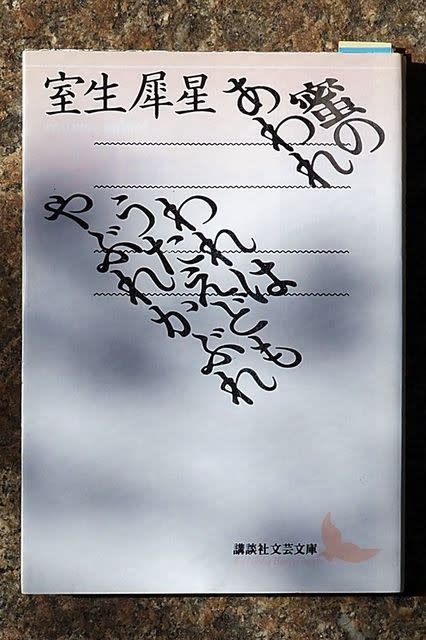
もう一つ取り上げておきたいのが、山本周五郎の「街へゆく電車」(「季節のない街」の一編、黒澤明が「どですかでん」として映画化)。
忘れることができない名編である。
「季節のない街」は、16-7年前、最後の1ページまで読んでいまする。ことに「街へゆく電車」はインパクトが大きかったなあ。
六ちゃんという人間のリアリティは、大抵の読者が感嘆を惜しまないだろう。いったいこういう作品の材料を、作者はどこから拾ってきたものかしら?
「どでどで、どでどで、どですかでん」
単なるどですかでんが、交差する線路の継ぎ目で軋り音が変わる。
この表現の凄み。
講談社文庫の映画化作品集「雨あがる」は、つぎの六編が収めてある。
1.狂女の話(「赤ひげの第一話」
2.五辨の椿(第六話)
3.深川安楽亭
4.街へゆく電車(「季節のない街」の一編)
5.ひとごろし
6.雨あがる
また「深川安楽亭」は、どん底でのたうつように生きる男たちが、離れたり近づいたり、同心円をえがくように構成された、奥行きの深い逸品。
わたしはこの作品の“異様な雰囲気”に浸り込んでしまった。
《その客は初めてきた晩に「おれはここを知っている」と云った。》
この冒頭の一言が、ラストに意味をもってくるのです。
ネットや手持ちの山本周五郎の本をひっくり返して調べてみたのですが、彼にはこういったレベルの作品が、短編で20-30編はあるようです、むろん評価の基準にもよりますが。
山本周五郎文学は、過去にずいぶんと読んできた・・・と思ったのですが、まったくといっていいほど、読めていなかったですなあ(;´д`)
2024年の現在から振り返ると、室生犀星は極めて少数ですが、山本周五郎を読みたがる読者は多数派に属するでしょうね。
新潮文庫の現行版だけで、何巻あるのかしら?
あちらこちらあふれて平積みとなったものやら、本棚の蔵書やらをひっくり返して眺めていまする。