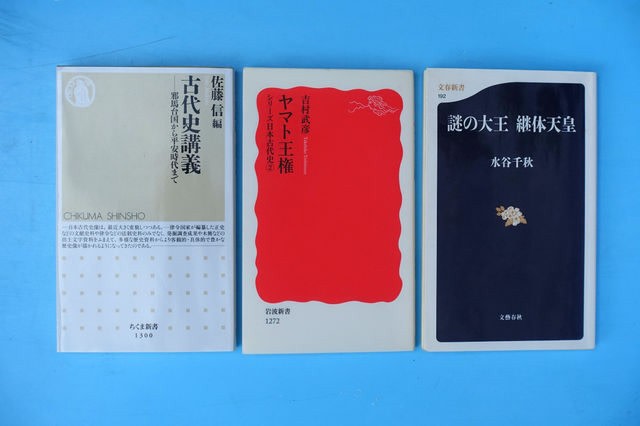
(いろいろな本が集まってきた。その多くは新書版)
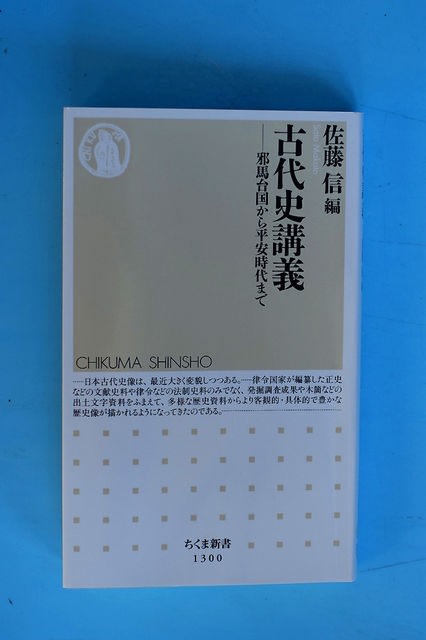
■「古代史講義 ―邪馬台国から平安時代まで」佐藤信編(ちくま新書 2018年刊)
古代史はジグソーパズルに似ている。
仮に1000個で完成するパネルだとして、ピースはその1/3もない。そこから本来の絵を推測し、組み立てる。
文献や発掘資料だけではなく、著者の想像力の問題だし、思想や生まれ育ちその他の問題である。
1/3しかないから、研究者、歴史家の独断、偏見も横行する。多かれ少なかれ推理小説的な“謎解き”のおもしろさを持っているのが古代史を特異な分野にしていると、わたしは思う。これは世界史の場合でもいえることである。
ただし、梅原猛さんのように想像力ばかり突っ走りすぎると、歴史ではなく「歴史読み物」、すなわちフィクションになってしまいかねない。
本書は15人の執筆者による、15の講義から成り立っている。執筆者は研究員、大学教授等の専門家。一番高齢なのは編者の佐藤信さんで、1952年生まれ、ほかは最前線にいるもっと若い錚々たる専門家。
第1講「邪馬台国から古墳の時代へ」からスタートし、第15講「平泉と奥州藤原氏」で終っている。
刊行が新しいだけに、最新の知見を盛り込んだ講義といっていいだろう。
講義は紙数がかぎられているだけに、要点のみがまとめられ、新幹線に乗って移動しているようなスピード感がある(^ー^)
忙しいビジネスマン向けの本といっていいだろう。
《昨今の研究の進展を受けて、かつての古代史の通説は覆され、学校教科書での古代史の記述も様変わりしつつある。大化の改新は六四五年のクーデタではない、「聖徳太子」は厩戸王でありその役割は限定的であった、東北の城柵は行政官庁だった、などはその一部である。
そこで十五人の研究者が集い、古代史の最新の研究成果と研究動向を一般読者にわかりやすく伝える。
一般読者が誤解しがちな点やかつての教科書で書かれていたために広まっている誤解などを正す、最新・最良の入門書。》(BOOKデータベースより ただし引用にあたって改行)
本書には「戦乱編」という姉妹版が用意されているが、これを読んだあと、そちらも手に入れた。
これはヒット作といえる。本書を第1ステップとして、つぎの段階にすすむのに具合がいいのだ。講義の末尾に“さらに詳しく知るための参考文献”が掲げられているのがアイデアである。講義の内容をオープンな場でおこなっているということにもなる。
良書である。
評価:☆☆☆☆
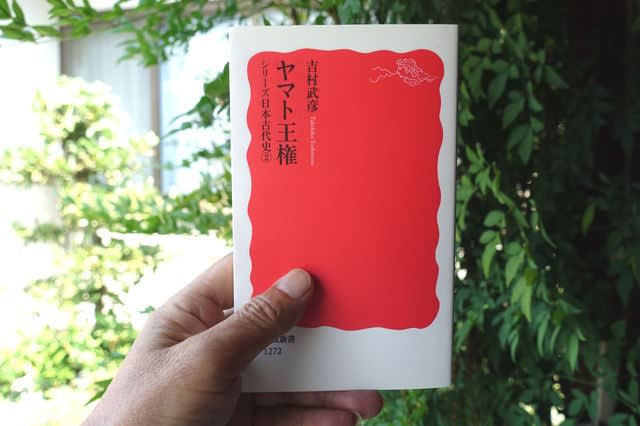
■「ヤマト王権」シリーズ日本古代史② 吉村武彦著(岩波新書 2010年刊)
古代史像をいかにとらえ、再構成するかで、本書にも苦労の跡がうかがえる。先学たちの諸説や“新発見”を紹介し、古事記、日本書紀を批判的に、いかに読み解いたらいいのか、神経を使っている。
そのため、慎重になりすぎて、何が結論なのかよくわからず、あいまいな叙述におわっているところが目につく。
吉村さんはよく研究し、鋭いテキスト批判をしているが、見方を変えると、右顧左眄しているような姿勢があぶり出されているように見える。古代史の持っている、現時点での“歯がゆさ”たるや、相当なもので、途中で読むのをやめてしまおうかと思ったほど(=_=)
専門の歴史家だけに、結局は慎重居士だし、テキスト批判が武器なのである。
シニカルにいわせてもらうなら、アカデミックに見えるその姿勢が、岩波の流儀とうまくマッチしている(^○^)/
叙述にはくり返しが多く、鮮明さとはほど遠いものがある。
しかし、これはシリーズ日本古代史全6巻の中の第2巻にあたる。そういう配慮が、吉村さんの姿勢を慎重なものにしているのかもしれない。
実在した初代の大王(のちの天皇)を崇神とはっきり断定していて、そのあたりは印象に残った。
評価:☆☆☆☆
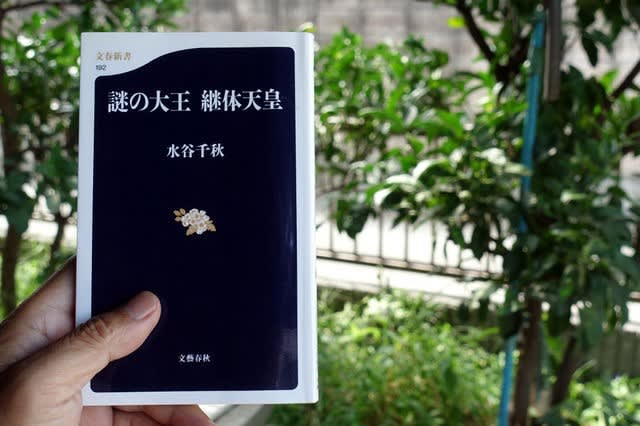
■「謎の大王 継体天皇」水谷千秋(文春新書 2001年刊)
《武烈天皇が跡継ぎを残さずに死んだあと、畿内を遠く離れた近江・越前を拠点とし、「応神天皇五世の孫」と称する人物が即位した。
継体天皇である。
この天皇にまつわるさまざまな謎―血統・即位の事情、蘇我・物部・葛城などの大氏族との関係、治世中に起きた「筑紫君磐井の乱」との関わり、「百済本記」に記録された奇怪な崩御のありさまなどを徹底的に追究し、さらに中世の皇位継承にその存在があたえた影響までをも考察した、
歴史ファン必読の傑作。》(BOOKデータベースより 引用者による改行あり)
歴史ファン必読の傑作というこの表現はCMのためにコピーではない。
以前も読みはじめたことがあったが、30ページあまりで挫折。だが今回はたいへんおもしろく読めた。
継体天皇は、まさしく“謎の”天皇なのである。
この天皇(大王)の即位は、本書がいうように古代史における画期であった。
なぜなら、天皇位を継ぐものは、その血筋でなければならないという皇統の大原則が、このとき確立したからである。
《この日本国は初めより王胤は外へ移る事なし》(愚管抄)
論証の手続きは入念におこなわれており、信頼がもてる。構想力もあり、読者をぐいぐい引っぱっていく。
参考までに目次を掲げておこう。
第一章 継体新王朝説
第二章 継体出現前史 ―雄略天皇、飯豊女王の時代
第三章 継体天皇と王位継承
第四章 継体天皇の即位と大和定着
第五章 磐井の反乱 ―地方豪族との対決
第六章 辛亥の変 ―二朝並立はあったのか
終 章 中世以降の継体天皇観
この終章がまことにスリリングで、ある意味正統的な天皇論となっている。
左翼系の歴史家、思想家が「天皇制」に対し、さまざまなアプローチを試みてはいるが、こういう本を読んでしまうと、それらがいかに思弁的な観念論に陥っているかよくわかる。
平成から令和へと元号があらたまるとき、われわれ日本人の多数の者は、日本人のルーツについて、思いをひそめたに違いない。
今回は天皇の薨去によるものではないから、昭和がおわったときのような暗雲はたちこめなかったが・・・。
日本人にとって、天皇とは何か!?
古代史を現代の視点から照射し、謎といわれる部分を解き明かし、読者にあらためて深い問いを投げかける。
古代は「わかっていること」より、「わかっていないこと」の方が、はるかに大きい。だから推定、推測が幅を利かしているのはやむをえない。
源頼朝、足利義満、織田信長、徳川家康。
彼らは日本を支配したが、みずからが“王位”を簒奪しようとはしなかった。それはなぜか?
わたしもこの問いに悩まされてきた一人である。
あとがきをふくめ、新書でわずか227ページだが、予想したより、はるかに濃密な内容が盛り込まれている。
水谷さんの日本古代史は、もっと読まなければいかんな(ノ_σ)
この国の在りようは、古代というその根源まで遡らないと見えてこないものがある。
読みおえたいま、著者の卓越した歴史観に脱帽である。疑いなく歴史書の傑作。
おすすめですぞ!
評価:☆☆☆☆☆
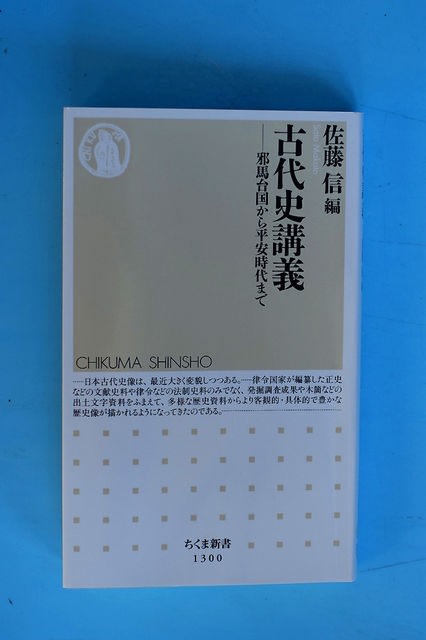
■「古代史講義 ―邪馬台国から平安時代まで」佐藤信編(ちくま新書 2018年刊)
古代史はジグソーパズルに似ている。
仮に1000個で完成するパネルだとして、ピースはその1/3もない。そこから本来の絵を推測し、組み立てる。
文献や発掘資料だけではなく、著者の想像力の問題だし、思想や生まれ育ちその他の問題である。
1/3しかないから、研究者、歴史家の独断、偏見も横行する。多かれ少なかれ推理小説的な“謎解き”のおもしろさを持っているのが古代史を特異な分野にしていると、わたしは思う。これは世界史の場合でもいえることである。
ただし、梅原猛さんのように想像力ばかり突っ走りすぎると、歴史ではなく「歴史読み物」、すなわちフィクションになってしまいかねない。
本書は15人の執筆者による、15の講義から成り立っている。執筆者は研究員、大学教授等の専門家。一番高齢なのは編者の佐藤信さんで、1952年生まれ、ほかは最前線にいるもっと若い錚々たる専門家。
第1講「邪馬台国から古墳の時代へ」からスタートし、第15講「平泉と奥州藤原氏」で終っている。
刊行が新しいだけに、最新の知見を盛り込んだ講義といっていいだろう。
講義は紙数がかぎられているだけに、要点のみがまとめられ、新幹線に乗って移動しているようなスピード感がある(^ー^)
忙しいビジネスマン向けの本といっていいだろう。
《昨今の研究の進展を受けて、かつての古代史の通説は覆され、学校教科書での古代史の記述も様変わりしつつある。大化の改新は六四五年のクーデタではない、「聖徳太子」は厩戸王でありその役割は限定的であった、東北の城柵は行政官庁だった、などはその一部である。
そこで十五人の研究者が集い、古代史の最新の研究成果と研究動向を一般読者にわかりやすく伝える。
一般読者が誤解しがちな点やかつての教科書で書かれていたために広まっている誤解などを正す、最新・最良の入門書。》(BOOKデータベースより ただし引用にあたって改行)
本書には「戦乱編」という姉妹版が用意されているが、これを読んだあと、そちらも手に入れた。
これはヒット作といえる。本書を第1ステップとして、つぎの段階にすすむのに具合がいいのだ。講義の末尾に“さらに詳しく知るための参考文献”が掲げられているのがアイデアである。講義の内容をオープンな場でおこなっているということにもなる。
良書である。
評価:☆☆☆☆
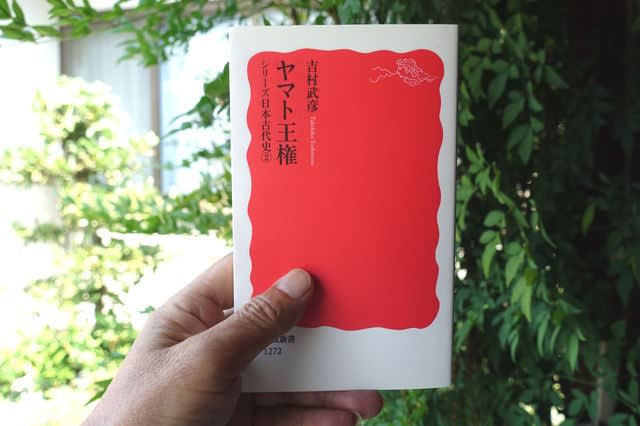
■「ヤマト王権」シリーズ日本古代史② 吉村武彦著(岩波新書 2010年刊)
古代史像をいかにとらえ、再構成するかで、本書にも苦労の跡がうかがえる。先学たちの諸説や“新発見”を紹介し、古事記、日本書紀を批判的に、いかに読み解いたらいいのか、神経を使っている。
そのため、慎重になりすぎて、何が結論なのかよくわからず、あいまいな叙述におわっているところが目につく。
吉村さんはよく研究し、鋭いテキスト批判をしているが、見方を変えると、右顧左眄しているような姿勢があぶり出されているように見える。古代史の持っている、現時点での“歯がゆさ”たるや、相当なもので、途中で読むのをやめてしまおうかと思ったほど(=_=)
専門の歴史家だけに、結局は慎重居士だし、テキスト批判が武器なのである。
シニカルにいわせてもらうなら、アカデミックに見えるその姿勢が、岩波の流儀とうまくマッチしている(^○^)/
叙述にはくり返しが多く、鮮明さとはほど遠いものがある。
しかし、これはシリーズ日本古代史全6巻の中の第2巻にあたる。そういう配慮が、吉村さんの姿勢を慎重なものにしているのかもしれない。
実在した初代の大王(のちの天皇)を崇神とはっきり断定していて、そのあたりは印象に残った。
評価:☆☆☆☆
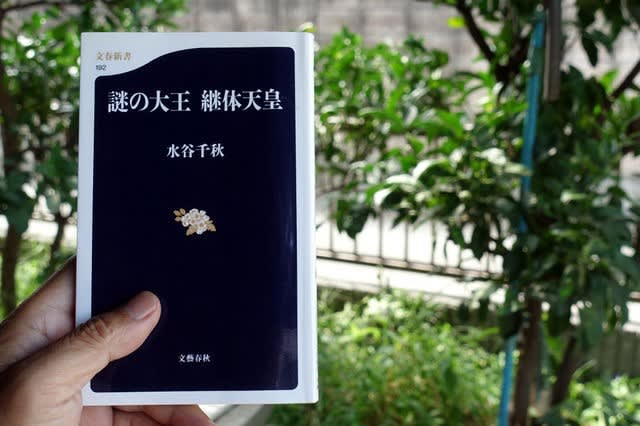
■「謎の大王 継体天皇」水谷千秋(文春新書 2001年刊)
《武烈天皇が跡継ぎを残さずに死んだあと、畿内を遠く離れた近江・越前を拠点とし、「応神天皇五世の孫」と称する人物が即位した。
継体天皇である。
この天皇にまつわるさまざまな謎―血統・即位の事情、蘇我・物部・葛城などの大氏族との関係、治世中に起きた「筑紫君磐井の乱」との関わり、「百済本記」に記録された奇怪な崩御のありさまなどを徹底的に追究し、さらに中世の皇位継承にその存在があたえた影響までをも考察した、
歴史ファン必読の傑作。》(BOOKデータベースより 引用者による改行あり)
歴史ファン必読の傑作というこの表現はCMのためにコピーではない。
以前も読みはじめたことがあったが、30ページあまりで挫折。だが今回はたいへんおもしろく読めた。
継体天皇は、まさしく“謎の”天皇なのである。
この天皇(大王)の即位は、本書がいうように古代史における画期であった。
なぜなら、天皇位を継ぐものは、その血筋でなければならないという皇統の大原則が、このとき確立したからである。
《この日本国は初めより王胤は外へ移る事なし》(愚管抄)
論証の手続きは入念におこなわれており、信頼がもてる。構想力もあり、読者をぐいぐい引っぱっていく。
参考までに目次を掲げておこう。
第一章 継体新王朝説
第二章 継体出現前史 ―雄略天皇、飯豊女王の時代
第三章 継体天皇と王位継承
第四章 継体天皇の即位と大和定着
第五章 磐井の反乱 ―地方豪族との対決
第六章 辛亥の変 ―二朝並立はあったのか
終 章 中世以降の継体天皇観
この終章がまことにスリリングで、ある意味正統的な天皇論となっている。
左翼系の歴史家、思想家が「天皇制」に対し、さまざまなアプローチを試みてはいるが、こういう本を読んでしまうと、それらがいかに思弁的な観念論に陥っているかよくわかる。
平成から令和へと元号があらたまるとき、われわれ日本人の多数の者は、日本人のルーツについて、思いをひそめたに違いない。
今回は天皇の薨去によるものではないから、昭和がおわったときのような暗雲はたちこめなかったが・・・。
日本人にとって、天皇とは何か!?
古代史を現代の視点から照射し、謎といわれる部分を解き明かし、読者にあらためて深い問いを投げかける。
古代は「わかっていること」より、「わかっていないこと」の方が、はるかに大きい。だから推定、推測が幅を利かしているのはやむをえない。
源頼朝、足利義満、織田信長、徳川家康。
彼らは日本を支配したが、みずからが“王位”を簒奪しようとはしなかった。それはなぜか?
わたしもこの問いに悩まされてきた一人である。
あとがきをふくめ、新書でわずか227ページだが、予想したより、はるかに濃密な内容が盛り込まれている。
水谷さんの日本古代史は、もっと読まなければいかんな(ノ_σ)
この国の在りようは、古代というその根源まで遡らないと見えてこないものがある。
読みおえたいま、著者の卓越した歴史観に脱帽である。疑いなく歴史書の傑作。
おすすめですぞ!
評価:☆☆☆☆☆



























