前回記事「阿曽原温泉」の続きです。
阿曽原温泉小屋に宿泊した翌日、私は裏剱の秘湯「仙人温泉」を目指した。阿曽原から仙人温泉へは2007年に開かれた「雲切新道」を登ってゆく必要があるのだが、事前に調べる限りでは、この道の評判がとてつもなく悪い。ハシゴやロープ場・鎖場が連続する急勾配をひたすら登ってゆく地獄のような道で、北アルプス三大急登よりも勾配がきつく、あたかも獣道の如き酷い路面であり、リッジ状の痩せ尾根の上であるため滑落したら命が無い、などなどネット上では散々な悪評なのである。しかも阿曽原温泉の露天風呂に入りながら、仙人池方面から下りてきた登山客数人にこの道について訊いてみると、みな口々に「二度とあんな道は歩きたくない」「どうしてあんなルートにしたのか」「俺は下りだったからよかったけど、登りには絶対に使いたくない」「悪名高いとは聞いていたけど納得したよ」「あの道で完全に膝がおかしくなった」などと次々に酷評するのである。そんな道を登山初心者の私が単独行で歩いて良いものだろうか。不安に苛まれながら、出発することにした。
ルート図や勾配断面はルートラボをご覧ください(かなり適当ですが)
・装備
ゴアテックス使用の登山靴・雨具(上下セパレート、上はウインドブレーカー兼用)・35Lザック・ザックカバー・帽子・足元まわりのスパッツ・ヘッドライト(※1)・熊除け鈴(※2)・設備工事用の皮手袋(※3)・地図・コンパス・笛・救急用具(絆創膏は何かと便利)・サロメチール(※4)・ポイズンリムーバー(毒抜き)・ツェルト・非常用ブランケット・ダウンジャケット(※5)・フリース・使い捨てカイロ・軽アイゼン(全く使用せず)・コッヘル&ガスバーナー(全く使用せず)・非常食・ミネラル補給用の飴・マグカップ・水筒・着替えの下着類・洗面用具・タオル類・コンビニの小ビニール手提げ袋数枚(ごみ袋として利用)・ティッシュペーパー(緊急時のキジ打ち用)・スマホ・携帯電話用予備バッテリー・デジカメ(メインと予備機の2台)・デジカメ用予備バッテリー・デジカメ用ミニ三脚・乾電池・ipod・筆記具・文庫本・トロッコ列車の時刻表(ハードコピー)・ザックの肩ベルトに装着する小物入れ(※6)
・行動中の服装
アンダーウエアとしてユニクロのクールドライTシャツ、そして化繊半袖Tシャツとアウトドア向けの化繊のロンTで問題なし。朝方寒い時は雨具上を羽織った。首にはタオルを巻く。小屋ではユニクロのヒートテックの上にロンTを着て、さらにフリースを着用。


【7:10 阿曽原温泉 出発】
定員いっぱいに泊まった阿曽原温泉の客はほぼ全て欅平へ下ってゆき、逆方向へ登ってゆくのは私一人だけ。それを知った主人の佐々木さんは、私に仙人温泉の主人への業務的な伝言を託した。
阿曽原の小屋をスタートしてから約10分間はジグザグの登りが続き、いきなり息が切れる。

登りきると水平歩道に戻る。


【7:28 権現峠(トンネル)】
トンネルを通過。中途半端な長さで、照明をつけながら歩いて、ようやく洞内の暗さに目が慣れてきたころでトンネルから出てしまう。照明類はあった方が良い。

高度感溢れる道。前日このような道を散々歩いてきたので、もう怖くない。

水平歩道が切れたところで左に折れると、谷底へ向かって一気に下ってゆく。ジグザグの下りで結構長い。


【7:50 人見平 関西電力人見寮】
坂を下りきると木々の向こうに突然視界が開け、山の奥とは思えない場違いな要塞が現れる。人見平に築かれた関電の施設だ。ここには黒部峡谷鉄道の上部軌道が通じているから、建築資材の運搬が容易なのだろう。


2棟建ち並ぶ施設を通過すると、登山道は山にポッカリ口をあけるトンネルへと導かれてゆく。入口には柵が設けられており、そこに貼られている案内を読むと、柵の扉を開けて中に入るように指示されている。この柵はクマ侵入防止のためのものらしい。鍵を開けて中へと入る。

トンネルから案内に従い冬期歩道を歩く。

隧道内では軌道用のトンネルも分岐しており、線路上には無蓋車がとまっていた。高熱隧道ゆえ、隧道内は熱気の蒸気でサウナのような状態で、硫黄の匂いも漂っている。画像が曇っているのは、レンズが汚れているのではなく、隧道内の蒸気が原因。



先程の無蓋車がとまっていた線路は引き込み線であり、やがて関西電力黒部専用鉄道(上部軌道)の本線との踏切を直角に交差する。遮断機こそないものの一応列車接近を知らせる警報機器類は備え付けられているので、第三種踏切と言えるかもしれない。このあたりはちょうど仙人谷駅付近にあたる。上部軌道はほぼ全区間が地下だが、唯一地上に出てくるのがこの仙人谷を渡る箇所である。

踏切から先はいかにも高熱隧道らしい湯気に満たされたトンネルを歩く。

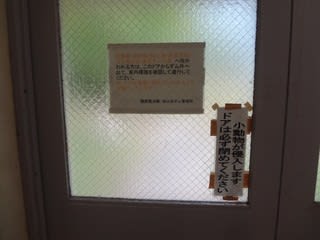
トンネルはそのまま仙人谷ダムの事務所へと直結しており、いかにも事務所らしいスチールのドアを開けて外へ出る。

ドアから外へ出てダム本体の階段をあがると…


【8:00 仙人谷ダム 雲切新道の始点】
ダム上が旧日電歩道と雲切新道との分岐点になっていた。旧日電歩道はダム上を歩いて黒部川の右岸へと出るが、雲切新道は事務所上の屋根をハシゴで登って越えてゆく。登山というより建築関係業者になったような気分だ。

川下を望むと、谷を渡る上部軌道の橋が見える。

湖は宝石のようなエメラルドブルーの水を湛えていた。自然の色とは思えない美しさに思わずうっとり。

冬期隧道と思しき古いコンクリの擁壁に沿って川を遡る。

上高地にも十分対抗できる美しさだ。景色に見とれていると…

【8:05 湖の真上に立つハシゴ】
目の前にほぼ垂直に上がるハシゴが登場。いよいよ雲切新道の急な登りがスタートするのだ。滑り止めの皮手袋を装着してハシゴを登る。

登り切ったところから梯子を見下ろすと、万有引力によってダム湖へ真っ逆さまに落ちてゆくかのように思われる。でもハシゴは真っ直ぐではなく、互い違いになっているところに、この道を切り拓いた関係各位の配慮が感じられる。というのも、互い違いならば、途中で何とか行き違いができ、一気に転落することもなく、途中でちょっと歩みをとめることもできるからだ。

ハシゴを登り切ったら、ダム湖から離れ、黒部川の支流である仙人谷に沿って川を遡る。河原の草には朝露がたくさん付着してビショビショになったので、足回りにスパッツを装着していて正解だった。


【8:10/20 仙人谷(橋)】
谷川に架かる丸太の橋で対岸へ。暑いので服を脱いで長袖シャツ一枚になり、その場でちょっと休憩。


急な坂が続くが、要所要所にフィックスロープが張られており、このロープに掴まりながら上半身をうまく使えば、ちょっとは楽に上り下りできる。特に雨の日にこのロープは必須だろう。
また、木の根が出っ張っていて歩きにくい(あるいは滑りやすい)箇所も連続しており、たしかに獣道のようであるが、極端に歩きにくいわけではなく、同様に根っこの出っ張りで登りにくい新潟県の苗場山腹の秘湯「赤湯温泉」へ伸びる登山道をちょっと荒々しくしたような険しさで、それほど大騒ぎするような程ではないように感じた。

ある程度登ったら尾根の腹の等高線上をトラバースする。


【8:37 「これより急登」プレート】
トラバース道を軽快に歩いていたら、目の前に突如現れたのがこの「これより急登」プレート。あれれ? 今までも十分急勾配だけど、これから更に険しくなるのか。気を引き締め、「よしっ」と自分に声を掛けて、未知なる険阻艱難へと挑む。


金属製のハシゴや木の階段を次々に登ってゆく。こんなところに頑丈なハシゴを設置するご苦労たるや、想像を絶する。

梢の向こうには細い滝が落ちていた。

見難い画像で申し訳ないが、枝の上ではサルのファミリーがブレックファスト中。秋はクマ被害が多発するシーズンなので、坂の上の森でゴソゴソと怪しい音が聞こえてきたときには思わず警戒してしまったが、よく耳を澄ますと音が聞こえてくる方向はかなり上方で、しかも軽めの響きだったので、サルの姿を確認した時にはホッとした。往路でも復路でもサルと遭遇したが、黒部のニホンザルは他地域よりひとまわり大きな体格をしているように見えた。

原生林に包まれた爽やかな道。登り道だが清々しい・・・


なんて呑気なことを考えていたら、木々の間を縫ってゆくジグザグの急登が目の前に立ちはだかり、一転して樹林が鬱陶しく感じる。ジグザグが終わったら、今度は木の根や跨いで進む足元の悪い道が続く。


【9:22 雷に打たれた2本の木】
勾配が一時的に緩やかになる箇所があり、そこには雷に打たれて幹だけが残った2本の木が無残な姿を晒していた。
振り返ると今まで歩いてきた阿曽原方面の谷合が望めた。ここで数分腰を下ろして呼吸を整える。

まだまだ急登は続く。木々に覆われて気づきにくいが、尾根の上の道なので、ところどころ見晴らしの良い箇所があり、そうした場所で足を止めて景色を眺めてみると、なかなか爽快だ。

振り返ると五竜や唐松などの後立山連峰が一望。


路傍の木々も少しずつ色づき始めている。今年の紅葉は平年より一週間遅れ、しかも色づきもいまいちのようだ。

【9:43 「阿曽原・池の平」プレート】
たまにこのような人工物を見つけると、今まで辿ってきた道が間違いでなかったことを確認でき、ちょっと安心する。
またこの辺りで仙人池ヒュッテから下りてくる登山者と何人かすれ違う。みなさん曰くまだまだ登りは続くぞ、とのこと。その言葉を受け、なお一層気を引き締める。

灌木に隠れてわかりにくいが、リッジ状の痩せ尾根の上を通る区間では、左右どちらに足を滑らせても谷底へ転落してしまう。幅は極めて狭く、しかも木の根が出っ張っているので、慎重に進んでゆく。


ハシゴも連続する。泥濘や根っこ道の連続よりもハシゴの方が進みやすく、一気に高さも稼げるので、私はハシゴ場を見るたびに嬉しくなった。


連続するハシゴを登りきると、木の瘤に「裏剱ロード安全祈願」と書かれた札が提げられていた。どうやらここで急登はおしまいのようだ。ネットでこの付近の様子を紹介している記事には、この札ではなくてチベット風のタルチョー(祈祷旗)がはためいていたようだが、現在ではその姿は見られず、木の札のみとなっていた。

さすがに標高が高くなると木の色づきも濃くなってくる。

道が平坦に近いほどのゆるゆるな勾配になると・・・


【10:25/11:25 尾根頂上(1629m) 昼食】
あれれ、もう尾根の頂上に着いちゃった。頂上と言っても眺望が良いわけではなく、ピーク感もなく、単なる通過点としか思えない凡庸なポイントであった。

昭文社の『山と高原地図 剱・立山 2011年版』 によれば、阿曽原からこのピークまで標準タイムで5時間20分を要するはずだが、私はなんと3時間15分で登ってきてしまった。ハイペースすぎる。ここから今日の宿泊先である小屋まで約30分だが、今から行ったのでは早く着きすぎて、小屋に迷惑をかけてしまう。このため、やや早めだがここでお弁当を広げることにした。
によれば、阿曽原からこのピークまで標準タイムで5時間20分を要するはずだが、私はなんと3時間15分で登ってきてしまった。ハイペースすぎる。ここから今日の宿泊先である小屋まで約30分だが、今から行ったのでは早く着きすぎて、小屋に迷惑をかけてしまう。このため、やや早めだがここでお弁当を広げることにした。

食後も時間をつぶすため、ここでのんびり。登山道を振り返ると、木々の間から後立山連峰が姿を覗かせていた。

坊主尾根は本来なら紅葉真っ盛りなはずだが、数日前に降った雪のため、葉が色づく前に茶色く朽ちてしまっていた。それでも山肌は紅・黄・緑のトリコロールに彩られていた。

1時間ほど潰していい加減に退屈になったので、ちょっと早いが再び歩き出すことにした。下り坂を辿って黄色くなった樹林へと突っ込んでゆく。


やがて「小屋のぞき」と朱書きされた札が目に入ると…

俄然視界が開けて仙人谷上部の全貌が見晴らせた。そして…

谷の斜面にポツンと佇む小屋を発見。ものすごくささやかで可愛らしい小屋だ。見渡す限り人工物はこの小屋しかない。まさに仙境だ。

小屋へは谷に下りて対岸へと向かう。前方にはその道筋が明瞭に確認できる。

谷へ下りる途中にはこんな水場があった。清冽な水はとっても美味い。


【11:40/55 仙人温泉元湯(1550m)】
やがて左手の山腹から白い湯気が立ち上るのが確認できる。仙人温泉の源泉である噴気帯だ。ゴーゴーと音を響かせながら、蒸気が勢いよく上がっている。

噴気帯のガレ場をちょっと登ってみると、たちまち湯気に覆われてしまった。足元ではフツフツと音を立てて熱湯が煮えたぎっている。こういう場所は大抵ぬかるんでおり、下手に泥へ足を突っ込むと火傷するかもしれないので要注意だ。


いくつかの湯溜まりがあり、温度を計測してみたら71.3℃もあった。入浴なんてできるわけない。

噴気帯から流れる熱湯は沢の河床を紅色に染めながら谷へと落ちていた。
ちなみに仙人温泉小屋はこの源泉から黒いホースで谷の対岸にある小屋までお湯を引いて利用している。画像に写っている黒いホースはまさにその引湯ホースだ。

噴気帯を出て間もなく、下方に丸太橋を確認。ゴール間近である安心感が災いしたか、この付近のぬかるみで、今回の行程で初めて大胆に滑ってしまった。


【11:58 仙人谷の橋】
仙人谷に架かる橋を渡る。水が少ない時期ならば、橋を使わずとも対岸へ渡れるだろう。

対岸の坂道を登る。あと200mも歩かずに済むかと思うと、足取りがとっても軽くなる。画像中央には、谷を横断する黒い筋が写っているのがわかるだろうか。


途中でケーブルを跨ぐのだが、これは対岸の噴気帯からこちらがわの小屋へ引湯するためのホースを吊るためのもので、上の画像で写っていた谷を跨ぐ黒い筋がそのホースである。お湯は空中を渡ってやってくるのである。

木々の間から建造物が見えて…

【12:05 仙人温泉小屋 到着】
無事に小屋へ到着。『山と高原地図 剱・立山』 によれば、阿曽原から仙人温泉への登りの標準タイムは5時間55分であるが、私の場合は無理矢理休んだ1時間休憩を入れても4時間55分で辿りつきことができ、もし休憩を入れなければ3時間55分で到達できた計算になる。スタート前にはかなり警戒していた雲切新道であったが、医者から「内蔵脂肪を減らさなきゃダメですよ」と注意されるほど運動不足な私ですら、意外にもサクサク登ることができ、我ながらビックリしてしまった。
によれば、阿曽原から仙人温泉への登りの標準タイムは5時間55分であるが、私の場合は無理矢理休んだ1時間休憩を入れても4時間55分で辿りつきことができ、もし休憩を入れなければ3時間55分で到達できた計算になる。スタート前にはかなり警戒していた雲切新道であったが、医者から「内蔵脂肪を減らさなきゃダメですよ」と注意されるほど運動不足な私ですら、意外にもサクサク登ることができ、我ながらビックリしてしまった。
登山道でよくある話として「新道に楽な道は無い」と言われることがある。今回登った雲切新道もそのひとつに該当するだろう。阿曽原~仙人温泉間は従来は仙人谷に沿ったルートが利用されていたが、この道では事故が多発していたために、これ以上の事故を防ぐべく、2007年に新たな道として雲切新道が切り開かれた。この道は従来より遠回りをするため所要時間が1~2時間程増えてしまったことに加え、切り立った危ない尾根の上をなぞり、かつ梯子やロープ・鎖が連続する急勾配の連続であるため、登山者からはマイナス評価されることが多い。しかし、幸いにして私は天候に恵まれた状態でこの道を往復利用したが、それでも事前に調べたり聞いたりしていたような程の酷い道には思えなかったのが正直な実感だ。
ではなぜこの道が悪評されてしまうのか、その理由を考えてみると…
・はしご・ロープ場・鎖場などビジュアル的に険しい箇所が多い
・従来の道と比べて遠回りな上にアップダウンが激しすぎる
・新しいため、道としてまだこなれていない。
・登山者の多くは中高年
・大抵の場合は入山してから2~3日にこの道を通過するが、中高年登山者の多くはちょうど疲れが溜まってくるタイミングなので、急な勾配が中高年の膝や腰を痛めつけてしまう。ツアーの場合は大抵下りでこの道を利用するが、下りは関節への負担が大きい。かといって登りに使うと、途中で挫折するツアー参加者が出てくる可能性がある。
このなかで私は一番下の事項が悪評を高くする最も大きな理由ではないかと推測する。つまり山行のうち一番疲れている頃でこの険しい道を通らなくてはいけないので、どうしてもその部分の記憶がマイナス方向に傾いてしまうのではないかと思うのだ。たしかに険しく常に緊張感が求められ、そして体力も必要だろう。雨の日は特に注意が必要で、全身泥だらけになるのを覚悟せねばならないだろう。しかし天気さえ悪くなければ、決して酷い道だとは思わない。関係各位の配慮により、随所にロープが用意されているので、これを上手く利用すれば転倒の可能性は大幅に減る。そして、伝聞ではあるが、事実としてこの新道の開通以降は富山県警山岳警備隊の出動件数が激減しているらしいので、多少険しく厳しい道であっても、疲労や体力消耗や恐怖感と引き換えに安全性が担保されていると言っても過言ではないのだろう。
余計な能書きはここまでとして、次回は小屋や温泉の様子をレポートしてみます。
阿曽原温泉小屋に宿泊した翌日、私は裏剱の秘湯「仙人温泉」を目指した。阿曽原から仙人温泉へは2007年に開かれた「雲切新道」を登ってゆく必要があるのだが、事前に調べる限りでは、この道の評判がとてつもなく悪い。ハシゴやロープ場・鎖場が連続する急勾配をひたすら登ってゆく地獄のような道で、北アルプス三大急登よりも勾配がきつく、あたかも獣道の如き酷い路面であり、リッジ状の痩せ尾根の上であるため滑落したら命が無い、などなどネット上では散々な悪評なのである。しかも阿曽原温泉の露天風呂に入りながら、仙人池方面から下りてきた登山客数人にこの道について訊いてみると、みな口々に「二度とあんな道は歩きたくない」「どうしてあんなルートにしたのか」「俺は下りだったからよかったけど、登りには絶対に使いたくない」「悪名高いとは聞いていたけど納得したよ」「あの道で完全に膝がおかしくなった」などと次々に酷評するのである。そんな道を登山初心者の私が単独行で歩いて良いものだろうか。不安に苛まれながら、出発することにした。
ルート図や勾配断面はルートラボをご覧ください(かなり適当ですが)
・装備
ゴアテックス使用の登山靴・雨具(上下セパレート、上はウインドブレーカー兼用)・35Lザック・ザックカバー・帽子・足元まわりのスパッツ・ヘッドライト(※1)・熊除け鈴(※2)・設備工事用の皮手袋(※3)・地図・コンパス・笛・救急用具(絆創膏は何かと便利)・サロメチール(※4)・ポイズンリムーバー(毒抜き)・ツェルト・非常用ブランケット・ダウンジャケット(※5)・フリース・使い捨てカイロ・軽アイゼン(全く使用せず)・コッヘル&ガスバーナー(全く使用せず)・非常食・ミネラル補給用の飴・マグカップ・水筒・着替えの下着類・洗面用具・タオル類・コンビニの小ビニール手提げ袋数枚(ごみ袋として利用)・ティッシュペーパー(緊急時のキジ打ち用)・スマホ・携帯電話用予備バッテリー・デジカメ(メインと予備機の2台)・デジカメ用予備バッテリー・デジカメ用ミニ三脚・乾電池・ipod・筆記具・文庫本・トロッコ列車の時刻表(ハードコピー)・ザックの肩ベルトに装着する小物入れ(※6)
(※1)一般的な登山用ヘッドライトの他、手元を照らすために私は「GENTOS 閃 325 SG-325」 というハンディライトを携行し、ストラップをつけてカラビナで引っかけてズボンのポケットに入れています。このライトは2000円+αという安価にもかかわらず150ルーメンという強力な光を発するので、とってもお得。しかも防滴仕様。同等のルーメン数で登山用ヘッドライトを購入しようとすると、かなり高額になるはずです。今回の山行では、小屋滞在中は勿論のこと、志合谷など水平歩道でのトンネルでも大活躍しました。
というハンディライトを携行し、ストラップをつけてカラビナで引っかけてズボンのポケットに入れています。このライトは2000円+αという安価にもかかわらず150ルーメンという強力な光を発するので、とってもお得。しかも防滴仕様。同等のルーメン数で登山用ヘッドライトを購入しようとすると、かなり高額になるはずです。今回の山行では、小屋滞在中は勿論のこと、志合谷など水平歩道でのトンネルでも大活躍しました。
(※2)雲切新道では必須。私のように早朝に単独行する人は絶対必要。
(※3)設備工事用の皮手袋は安価でありかつグリップ力が強いので、見た目はダサいが使い勝手は良い。たとえば「ノンスリップライト」などは、作業着専門店などで安く購入できる。フィックスロープやハシゴが連続する雲切新道では大活躍した。ボロボロになっても比較的安いので心おきなく捨てられる。素手でロープ握って下ると、掌を擦り切っちゃいますよ。
(※4)筋肉疲労ケアの他、痒みや虫さされ対処にも使えるので、何かと便利。
(※5)ユニクロやしまむらなどの安物で十分。しかも軽くてコンパクトで暖かい。安いので荒く扱っても気にならない。
(※6)雲切新道などハシゴ場・ロープ場が連続する箇所では、足元や下方の視界を確保する必要があるため、小物入れとしてウエストポーチは不適(下方の視界を邪魔するので)。デジカメや筆記具などは肩ベルトなどに装着するポーチに入れ、落下を防ぐためカラビナやストラップを併用した。
個人的に登山用具で金をかけるべきは、雨具・靴・下着の3点であるかと思っています。あとは工夫して安物で代用すればいいかと…。登山用品店の言いなりになって買っていると、お金がいくらあっても足りません。
(※2)雲切新道では必須。私のように早朝に単独行する人は絶対必要。
(※3)設備工事用の皮手袋は安価でありかつグリップ力が強いので、見た目はダサいが使い勝手は良い。たとえば「ノンスリップライト」などは、作業着専門店などで安く購入できる。フィックスロープやハシゴが連続する雲切新道では大活躍した。ボロボロになっても比較的安いので心おきなく捨てられる。素手でロープ握って下ると、掌を擦り切っちゃいますよ。
(※4)筋肉疲労ケアの他、痒みや虫さされ対処にも使えるので、何かと便利。
(※5)ユニクロやしまむらなどの安物で十分。しかも軽くてコンパクトで暖かい。安いので荒く扱っても気にならない。
(※6)雲切新道などハシゴ場・ロープ場が連続する箇所では、足元や下方の視界を確保する必要があるため、小物入れとしてウエストポーチは不適(下方の視界を邪魔するので)。デジカメや筆記具などは肩ベルトなどに装着するポーチに入れ、落下を防ぐためカラビナやストラップを併用した。
個人的に登山用具で金をかけるべきは、雨具・靴・下着の3点であるかと思っています。あとは工夫して安物で代用すればいいかと…。登山用品店の言いなりになって買っていると、お金がいくらあっても足りません。
・行動中の服装
アンダーウエアとしてユニクロのクールドライTシャツ、そして化繊半袖Tシャツとアウトドア向けの化繊のロンTで問題なし。朝方寒い時は雨具上を羽織った。首にはタオルを巻く。小屋ではユニクロのヒートテックの上にロンTを着て、さらにフリースを着用。


【7:10 阿曽原温泉 出発】
定員いっぱいに泊まった阿曽原温泉の客はほぼ全て欅平へ下ってゆき、逆方向へ登ってゆくのは私一人だけ。それを知った主人の佐々木さんは、私に仙人温泉の主人への業務的な伝言を託した。
阿曽原の小屋をスタートしてから約10分間はジグザグの登りが続き、いきなり息が切れる。

登りきると水平歩道に戻る。


【7:28 権現峠(トンネル)】
トンネルを通過。中途半端な長さで、照明をつけながら歩いて、ようやく洞内の暗さに目が慣れてきたころでトンネルから出てしまう。照明類はあった方が良い。

高度感溢れる道。前日このような道を散々歩いてきたので、もう怖くない。

水平歩道が切れたところで左に折れると、谷底へ向かって一気に下ってゆく。ジグザグの下りで結構長い。


【7:50 人見平 関西電力人見寮】
坂を下りきると木々の向こうに突然視界が開け、山の奥とは思えない場違いな要塞が現れる。人見平に築かれた関電の施設だ。ここには黒部峡谷鉄道の上部軌道が通じているから、建築資材の運搬が容易なのだろう。


2棟建ち並ぶ施設を通過すると、登山道は山にポッカリ口をあけるトンネルへと導かれてゆく。入口には柵が設けられており、そこに貼られている案内を読むと、柵の扉を開けて中に入るように指示されている。この柵はクマ侵入防止のためのものらしい。鍵を開けて中へと入る。

トンネルから案内に従い冬期歩道を歩く。

隧道内では軌道用のトンネルも分岐しており、線路上には無蓋車がとまっていた。高熱隧道ゆえ、隧道内は熱気の蒸気でサウナのような状態で、硫黄の匂いも漂っている。画像が曇っているのは、レンズが汚れているのではなく、隧道内の蒸気が原因。



先程の無蓋車がとまっていた線路は引き込み線であり、やがて関西電力黒部専用鉄道(上部軌道)の本線との踏切を直角に交差する。遮断機こそないものの一応列車接近を知らせる警報機器類は備え付けられているので、第三種踏切と言えるかもしれない。このあたりはちょうど仙人谷駅付近にあたる。上部軌道はほぼ全区間が地下だが、唯一地上に出てくるのがこの仙人谷を渡る箇所である。

踏切から先はいかにも高熱隧道らしい湯気に満たされたトンネルを歩く。

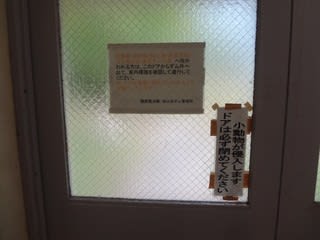
トンネルはそのまま仙人谷ダムの事務所へと直結しており、いかにも事務所らしいスチールのドアを開けて外へ出る。

ドアから外へ出てダム本体の階段をあがると…


【8:00 仙人谷ダム 雲切新道の始点】
ダム上が旧日電歩道と雲切新道との分岐点になっていた。旧日電歩道はダム上を歩いて黒部川の右岸へと出るが、雲切新道は事務所上の屋根をハシゴで登って越えてゆく。登山というより建築関係業者になったような気分だ。

川下を望むと、谷を渡る上部軌道の橋が見える。

湖は宝石のようなエメラルドブルーの水を湛えていた。自然の色とは思えない美しさに思わずうっとり。

冬期隧道と思しき古いコンクリの擁壁に沿って川を遡る。

上高地にも十分対抗できる美しさだ。景色に見とれていると…

【8:05 湖の真上に立つハシゴ】
目の前にほぼ垂直に上がるハシゴが登場。いよいよ雲切新道の急な登りがスタートするのだ。滑り止めの皮手袋を装着してハシゴを登る。

登り切ったところから梯子を見下ろすと、万有引力によってダム湖へ真っ逆さまに落ちてゆくかのように思われる。でもハシゴは真っ直ぐではなく、互い違いになっているところに、この道を切り拓いた関係各位の配慮が感じられる。というのも、互い違いならば、途中で何とか行き違いができ、一気に転落することもなく、途中でちょっと歩みをとめることもできるからだ。

ハシゴを登り切ったら、ダム湖から離れ、黒部川の支流である仙人谷に沿って川を遡る。河原の草には朝露がたくさん付着してビショビショになったので、足回りにスパッツを装着していて正解だった。


【8:10/20 仙人谷(橋)】
谷川に架かる丸太の橋で対岸へ。暑いので服を脱いで長袖シャツ一枚になり、その場でちょっと休憩。


急な坂が続くが、要所要所にフィックスロープが張られており、このロープに掴まりながら上半身をうまく使えば、ちょっとは楽に上り下りできる。特に雨の日にこのロープは必須だろう。
また、木の根が出っ張っていて歩きにくい(あるいは滑りやすい)箇所も連続しており、たしかに獣道のようであるが、極端に歩きにくいわけではなく、同様に根っこの出っ張りで登りにくい新潟県の苗場山腹の秘湯「赤湯温泉」へ伸びる登山道をちょっと荒々しくしたような険しさで、それほど大騒ぎするような程ではないように感じた。

ある程度登ったら尾根の腹の等高線上をトラバースする。


【8:37 「これより急登」プレート】
トラバース道を軽快に歩いていたら、目の前に突如現れたのがこの「これより急登」プレート。あれれ? 今までも十分急勾配だけど、これから更に険しくなるのか。気を引き締め、「よしっ」と自分に声を掛けて、未知なる険阻艱難へと挑む。


金属製のハシゴや木の階段を次々に登ってゆく。こんなところに頑丈なハシゴを設置するご苦労たるや、想像を絶する。

梢の向こうには細い滝が落ちていた。

見難い画像で申し訳ないが、枝の上ではサルのファミリーがブレックファスト中。秋はクマ被害が多発するシーズンなので、坂の上の森でゴソゴソと怪しい音が聞こえてきたときには思わず警戒してしまったが、よく耳を澄ますと音が聞こえてくる方向はかなり上方で、しかも軽めの響きだったので、サルの姿を確認した時にはホッとした。往路でも復路でもサルと遭遇したが、黒部のニホンザルは他地域よりひとまわり大きな体格をしているように見えた。

原生林に包まれた爽やかな道。登り道だが清々しい・・・


なんて呑気なことを考えていたら、木々の間を縫ってゆくジグザグの急登が目の前に立ちはだかり、一転して樹林が鬱陶しく感じる。ジグザグが終わったら、今度は木の根や跨いで進む足元の悪い道が続く。


【9:22 雷に打たれた2本の木】
勾配が一時的に緩やかになる箇所があり、そこには雷に打たれて幹だけが残った2本の木が無残な姿を晒していた。
振り返ると今まで歩いてきた阿曽原方面の谷合が望めた。ここで数分腰を下ろして呼吸を整える。

まだまだ急登は続く。木々に覆われて気づきにくいが、尾根の上の道なので、ところどころ見晴らしの良い箇所があり、そうした場所で足を止めて景色を眺めてみると、なかなか爽快だ。

振り返ると五竜や唐松などの後立山連峰が一望。


路傍の木々も少しずつ色づき始めている。今年の紅葉は平年より一週間遅れ、しかも色づきもいまいちのようだ。

【9:43 「阿曽原・池の平」プレート】
たまにこのような人工物を見つけると、今まで辿ってきた道が間違いでなかったことを確認でき、ちょっと安心する。
またこの辺りで仙人池ヒュッテから下りてくる登山者と何人かすれ違う。みなさん曰くまだまだ登りは続くぞ、とのこと。その言葉を受け、なお一層気を引き締める。

灌木に隠れてわかりにくいが、リッジ状の痩せ尾根の上を通る区間では、左右どちらに足を滑らせても谷底へ転落してしまう。幅は極めて狭く、しかも木の根が出っ張っているので、慎重に進んでゆく。


ハシゴも連続する。泥濘や根っこ道の連続よりもハシゴの方が進みやすく、一気に高さも稼げるので、私はハシゴ場を見るたびに嬉しくなった。


連続するハシゴを登りきると、木の瘤に「裏剱ロード安全祈願」と書かれた札が提げられていた。どうやらここで急登はおしまいのようだ。ネットでこの付近の様子を紹介している記事には、この札ではなくてチベット風のタルチョー(祈祷旗)がはためいていたようだが、現在ではその姿は見られず、木の札のみとなっていた。

さすがに標高が高くなると木の色づきも濃くなってくる。

道が平坦に近いほどのゆるゆるな勾配になると・・・


【10:25/11:25 尾根頂上(1629m) 昼食】
あれれ、もう尾根の頂上に着いちゃった。頂上と言っても眺望が良いわけではなく、ピーク感もなく、単なる通過点としか思えない凡庸なポイントであった。

昭文社の『山と高原地図 剱・立山 2011年版』

食後も時間をつぶすため、ここでのんびり。登山道を振り返ると、木々の間から後立山連峰が姿を覗かせていた。

坊主尾根は本来なら紅葉真っ盛りなはずだが、数日前に降った雪のため、葉が色づく前に茶色く朽ちてしまっていた。それでも山肌は紅・黄・緑のトリコロールに彩られていた。

1時間ほど潰していい加減に退屈になったので、ちょっと早いが再び歩き出すことにした。下り坂を辿って黄色くなった樹林へと突っ込んでゆく。


やがて「小屋のぞき」と朱書きされた札が目に入ると…

俄然視界が開けて仙人谷上部の全貌が見晴らせた。そして…

谷の斜面にポツンと佇む小屋を発見。ものすごくささやかで可愛らしい小屋だ。見渡す限り人工物はこの小屋しかない。まさに仙境だ。

小屋へは谷に下りて対岸へと向かう。前方にはその道筋が明瞭に確認できる。

谷へ下りる途中にはこんな水場があった。清冽な水はとっても美味い。


【11:40/55 仙人温泉元湯(1550m)】
やがて左手の山腹から白い湯気が立ち上るのが確認できる。仙人温泉の源泉である噴気帯だ。ゴーゴーと音を響かせながら、蒸気が勢いよく上がっている。

噴気帯のガレ場をちょっと登ってみると、たちまち湯気に覆われてしまった。足元ではフツフツと音を立てて熱湯が煮えたぎっている。こういう場所は大抵ぬかるんでおり、下手に泥へ足を突っ込むと火傷するかもしれないので要注意だ。


いくつかの湯溜まりがあり、温度を計測してみたら71.3℃もあった。入浴なんてできるわけない。

噴気帯から流れる熱湯は沢の河床を紅色に染めながら谷へと落ちていた。
ちなみに仙人温泉小屋はこの源泉から黒いホースで谷の対岸にある小屋までお湯を引いて利用している。画像に写っている黒いホースはまさにその引湯ホースだ。

噴気帯を出て間もなく、下方に丸太橋を確認。ゴール間近である安心感が災いしたか、この付近のぬかるみで、今回の行程で初めて大胆に滑ってしまった。


【11:58 仙人谷の橋】
仙人谷に架かる橋を渡る。水が少ない時期ならば、橋を使わずとも対岸へ渡れるだろう。

対岸の坂道を登る。あと200mも歩かずに済むかと思うと、足取りがとっても軽くなる。画像中央には、谷を横断する黒い筋が写っているのがわかるだろうか。


途中でケーブルを跨ぐのだが、これは対岸の噴気帯からこちらがわの小屋へ引湯するためのホースを吊るためのもので、上の画像で写っていた谷を跨ぐ黒い筋がそのホースである。お湯は空中を渡ってやってくるのである。

木々の間から建造物が見えて…

【12:05 仙人温泉小屋 到着】
無事に小屋へ到着。『山と高原地図 剱・立山』
登山道でよくある話として「新道に楽な道は無い」と言われることがある。今回登った雲切新道もそのひとつに該当するだろう。阿曽原~仙人温泉間は従来は仙人谷に沿ったルートが利用されていたが、この道では事故が多発していたために、これ以上の事故を防ぐべく、2007年に新たな道として雲切新道が切り開かれた。この道は従来より遠回りをするため所要時間が1~2時間程増えてしまったことに加え、切り立った危ない尾根の上をなぞり、かつ梯子やロープ・鎖が連続する急勾配の連続であるため、登山者からはマイナス評価されることが多い。しかし、幸いにして私は天候に恵まれた状態でこの道を往復利用したが、それでも事前に調べたり聞いたりしていたような程の酷い道には思えなかったのが正直な実感だ。
ではなぜこの道が悪評されてしまうのか、その理由を考えてみると…
・はしご・ロープ場・鎖場などビジュアル的に険しい箇所が多い
・従来の道と比べて遠回りな上にアップダウンが激しすぎる
・新しいため、道としてまだこなれていない。
・登山者の多くは中高年
・大抵の場合は入山してから2~3日にこの道を通過するが、中高年登山者の多くはちょうど疲れが溜まってくるタイミングなので、急な勾配が中高年の膝や腰を痛めつけてしまう。ツアーの場合は大抵下りでこの道を利用するが、下りは関節への負担が大きい。かといって登りに使うと、途中で挫折するツアー参加者が出てくる可能性がある。
このなかで私は一番下の事項が悪評を高くする最も大きな理由ではないかと推測する。つまり山行のうち一番疲れている頃でこの険しい道を通らなくてはいけないので、どうしてもその部分の記憶がマイナス方向に傾いてしまうのではないかと思うのだ。たしかに険しく常に緊張感が求められ、そして体力も必要だろう。雨の日は特に注意が必要で、全身泥だらけになるのを覚悟せねばならないだろう。しかし天気さえ悪くなければ、決して酷い道だとは思わない。関係各位の配慮により、随所にロープが用意されているので、これを上手く利用すれば転倒の可能性は大幅に減る。そして、伝聞ではあるが、事実としてこの新道の開通以降は富山県警山岳警備隊の出動件数が激減しているらしいので、多少険しく厳しい道であっても、疲労や体力消耗や恐怖感と引き換えに安全性が担保されていると言っても過言ではないのだろう。
余計な能書きはここまでとして、次回は小屋や温泉の様子をレポートしてみます。















