朝夕は幾分秋らしく感じられるようになりましたが、日中はまだ30℃超えの
厳しい暑さが残るこの頃、昨日(9/16土)には、約2か月ぶりの園芸友の会
オンライン例会がありました。
関東を中心として、北は札幌から、南は福岡、それに関西と広域にまたがる
例会が出来るのは、オンラインならではの効用と考え、手軽にそれぞれの皆
さんの自宅から参加されています。PCやスマホを持参すれば、どこか観光地
や温泉地からの参加も可能なんですね。
ネットワークの整備と、このようなシステムアプリケーションのお陰で、
少し前には考えられなかった利便が手に入っているのですね。
ところが今回は、オンライン参加メールの手違い?で、メンバー1人が入室
出来なくなり、例会進行途中で、ホスト画面から割り込み操作が出来ず結果
として、折角の参加が出来なくなってしまうアクシデントがありました。
参加メンバー

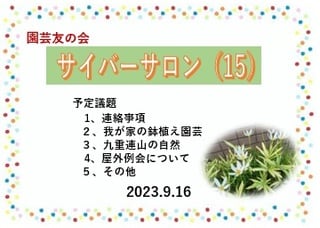
(メンバー一人参加できませんでした。)
そんな状況の中、心を残したまま例会は進み、予定した議題の会員からの
発表2件は、質問、コメント、アドバイスなどが飛び交う活発で賑やかに盛り
上がるうちに進行しました。
1点目の発表、「我が家の鉢植え園芸」では、5年前からチャレンジされて
いるラビットアイ系ブルーベリー栽培、レモン、ゴーヤカーテン、草花たちを
取上げ、特にブルーベリーに関する栽培方法、施肥、水遣りなどによる成長の
観察と結果について発表されました。
ブルーベリーについては、3鉢の内、1鉢(ブライトブルー)は、購入後成長
が止まり、掘り上げたところ根が張っていないことが分かり、そのうちに枯れ
てしまった。この原因については不明のままですが、恐らく病気か何らかの
致命的な要因ではないか。残る2鉢は成長はよく、ブライトウエルは果実も
豊作ではあったが、肝心の果実に「味がない」ということで、水、肥料など
の話題が沸騰しました。水のやりすぎも考えられる。雨水は、ミネラルやその
他の栄養分も含まれているが、水道水は薬品による浄化が施されている違いが
あること、さらには散水の量にも大きな影響があるのではないか。
ブライトウエル

残るプレミア種は、植え替えにより元気が出てきたとのことで、様子を見る
ことに。
プレミア

成長が良い鉢の写真では、枝葉が成長しすぎているようにも見え、鉢の大き
さが比較して小さめなこと、肥料も窒素系が多いのでは?などのコメントが
ありました。
レモンへの挑戦は、1年目にしては果実も出来上出来とのことですが、樹形
を見るとまだ若すぎる感じで、果実は捨ててもう少し木を育てた方がよさそう
にも見えます。
レモン

ゴーヤは、今年は、グリーンカーテンを主体として、果実は採らない。し
たがって早めに花芽を欠いたことが成功して、立派な設計通りのゴーヤカー
テンが出来ました。
成功したゴーヤカーテン

草花たちも、片手間の感じでやってみたが、鉢植えに比べてやはり地植え
の力をまざまざと見たようでした。
全体的に実のなる種類も、鉢の大きさがもう少し大きい方が土の力が発揮
できるのではないかとの意見が多かったようです。しかし、これまで園芸に
手を染めてこなかったご本人にとっては、新しい試行錯誤の繰り返しと熱心
な観察、成長の姿に生物の不思議にも似た側面を捉え、これからもチャレンジ
して行く気迫をみなぎらせているようでした。

2件目の発表は、「九重連山の自然」と題して、これまで もう何年も、
毎年、くじゅう山開きの6月第一日曜日を基本に、大学の仲間と久住山登山を
してきた懐かしい想い出と共に、雄大な久住高原を望むその中にミヤマキリ
シマの群生の紹介、さらにはドウダンツツジ、紅サラサドウダンの気品を感じ
る大ぶりの花木などを懐かしむように紹介がありました。
ミヤマキリシマ

ドウダンツツジ(紅サラサドウダン)

ミヤマキリシマは、なぜこの地に咲くか?・・それは、この樹木は火山活動
により生態系が撹乱された山肌で優占種として生存でき、亜硫酸ガスにも強い
からだとありました。
登山の時期が、山開きに合わせているため、どうしても晴れた日が少なく、
紹介された写真も多くがガスの中のくじゅう高原、ミヤマキリシマでした。
見晴るかす 久住高原

また周辺の、耶馬渓、福貴野の滝や東洋のナイアガラとして有名な、豊後
大野の原尻の滝などの紹介もありました。原尻の滝は、阿蘇山の大噴火(9万
年前)の火砕流によってもたらされたといい、平野の中に忽然と現れるのです。
関東の富士山の裾野や鬼押し出しの近くにある白糸の滝にも似ているとの声
がありました。
原尻の滝

話題はそれますが、「九重」という呼び方と「久住」と呼ぶところがある
そして、登山口などの注意書きには「くじゅう」と書かれていました。
これについても質問が出ていましたが、調べてみると『くじゅう山の一体を
「くじゅう」と呼び、北側に九重町(ここのえまち)、南側に久住町(くじゅ
うまち:現、竹田市)がある。山は久住山、火山群や周辺地域全体は九重山、
九重連山と呼ぶ。 最近は地区として「くじゅう」と表記されることが多い。』
とありましたが、にわかには理解しずらい面があります。
また、1934年12月4日に阿寒国立公園、日光国立公園、中部山岳国立公園、
大雪山国立公園、さらに阿蘇国立公園が誕生しましたが、1986年の改称の
ときに、九重、久住両町で決めた結果「阿蘇くじゅう国立公園」に落ち着いた
と追記をいただきました。
最後に、自作の花たちの紹介もありました、タマアジサイの大ぶりやラン
タナなど、そして亡きおふくろさんを忍んで植えた、きれいに咲きそろった
花しょうぶが、短歌と共に紹介されました。

会員からの上記2件の発表のほか、この夏の話題として、八ヶ岳・清里方面
に行かれ、かって行かれた「萌木の村」がすっかり変わって、大変すばらしい
庭園になっていたとのお話がありました。英国人園芸家を招き日本の原生植物
を基本に見事な花に包まれていたそうです。 よく見る「ぎぼうし」なども、
これまで見たこともないほど大きな見ごたえのある群生が植生されていたなど
の感動の発表がありました。

今回、冒頭に述べました参加手続きに不備が生じたため、お一人の参加が
出来ない結果となりましたが、例会そのものは楽しい意見の飛び交う中で賑や
かなうちに終了しました。
次回例会は、屋外リアル例会で、11月17日(金)を予定し、場所は、駒込
駅近くの「六義園」が候補に挙がり、近く幹事会で検討することとなり、14時
から2時間半近くにおよぶ例会が無事終了しました。おつかれさまでした。
Guadalupe Pineda - Historia De Un Amor
















