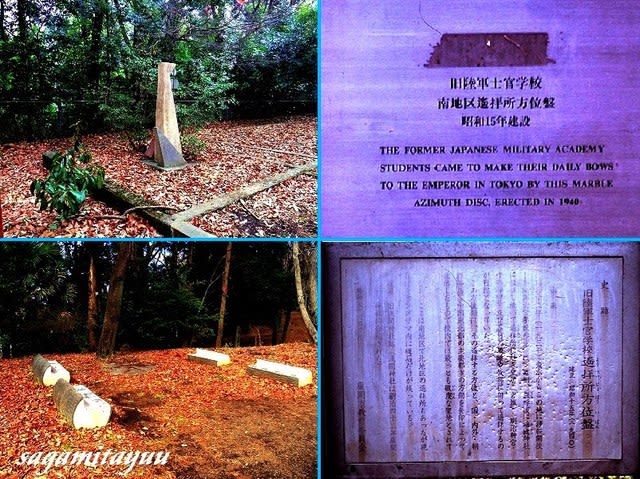烏山寺町通りの更に一本奥に4寺がありその一番手前に浄土真宗寺院「八丁山妙善寺」はある。親鸞の弟子となった菅原正円が伊勢国安濃郡大別保村に「草庵」を建立したのが興りとされる。その後同じ伊勢国の桑名郡蒔田村、江戸初期に武蔵国豊島郡八丁堀に移転。明暦3年(1657)の振袖火事により本堂その他を焼失し、50年で伊勢国を離れ築地に移転の経緯を辿る。関東大震災後、昭和2年現在の烏山に移転再建。本尊は阿弥陀如来。手入れの行き届いた前庭に構えられた「山門」の奥に入母屋造りの「本堂」がある。左右対称の花頭窓が印象的で、2層屋根はどことなく奈良の大仏殿を思い起こさせる。本堂右手に庫裡。当寺には永井荷風の作風にも影響を与えたという江戸時代の人情本作家「為永春水」のお墓がある。(1701)