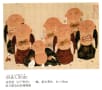「若冲」(狩野博幸、角川ソフィア文庫)を読み終えた。
私としてはとても勉強になったと思う本であった。
この本では、若冲の生きていた当時の京の文化人、その中でも黄檗宗の禅僧である「売茶翁」「相国寺住職である大典和尚」「萬福:寺住持で渡来層の伯珣」との交流を軸に、若冲という人物を描いている。
あとがきに
「筆者は人生というものは人と人との交友の中でだけかたち作られてゆくと考えている。売茶翁は禅自体にに幻滅したのではなく、僧という存在にいっさいの疑問を持たず商人を軽蔑することの虚妄を静かな行動で示したのであり、大典ははじめ黄檗禅に入るも‥洛中洛外を転々とする生活を続けながら詩作に耽り思索を深め、ついに相国寺に復帰することを選ぶ。伯珣はいわば鑑真と変わらぬ決意をもって日本に渡ってきた。彼らが若冲という画家を見出し、出会ったときに発生したのは、大袈裟に言えば人と人とのあいだに生じた核融合のようなものだったのではなかろうか。」
と記している。
また、最近の研究で若冲が単に「絵画オタク」ではなく、錦市場の営業停止の町奉行の方針の撤回に向け、剛直な一面を発揮し粘り強く再開を果たしたことが明らかとなっている。確かNHKの日曜美術館でも取り上げられていたと思う。
そのことに関して筆者は、
「江戸表へ訴え出ることを決意した若冲は、万が一の場合を考えて、錦小路市場に累が及ばぬように平屋となったのである。‥仮にも幕府の一組織である奉行所に対する訴えであることから、訴え出た本人の命は保証されない。若冲の行動はひたすら冷静だ。自分の命をも賭すことを心に秘めながら、奉行所はもとより仲介者や村々の百姓への根回しを続けた。」「日頃は、隠居して作画三昧の生活に満足げな人物が、いざとなれば、“社会”をこわだかに論じながら実践する胆力のない輩をはるかに凌駕する行動派へと変身する。しかも、落としどころを遠くに見据えながら、慌てることなく着実に歩を進めてゆく。‥若冲がそういう人物であったことを知ったいま、これまで何となく見過ごされてきたことが異なった色彩を帯びて見えるようになる。」
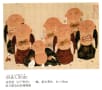
「若沖70歳のとき、伏見奉行や役人らの暴政に立ちあがった伏見町人の代表たちが江戸表へ訴え出て勝訴したが、町人たちにも犠牲が出る。牢死したもの7人は“伏見(天明)義民”として今に至るも土地の人びとの尊崇を受けている。‥若冲の画題のジャンルのひとつに伏見人形図がある。‥若冲が7人の布袋に別の意味を込めた可能性を指摘しておきたい。‥若冲であればこそ「伏見義民事件」の「7人の町人」はひとごとではなかった。」
と記している。
私は若冲の「伏見人形図」という作品の意味合いがようやく解けた思いがした。
この本全体はこのように筆者の「知識人論」でもあり、そしてそれに私が共感する場面が多々あった。その中で1968年の九州大学へのF4ファントム墜落事故のエピソードなどもあり、同時代の空気を感じ取りながら読み進めた。