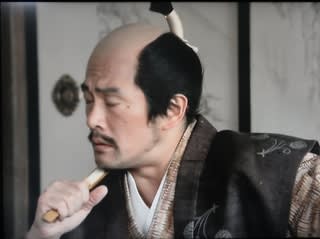五郎丸と真田丸?
丸がいっしょなだけ?

おなじみ、五郎丸さんのルーティン、クライマックスポーズ
大河ドラマ「真田丸」 で私が期待を寄せているのが忍者の登場です
猿飛佐助、出浦昌相(いでうらまさすけ)、服部半蔵
今はまだ活躍というには遠いのですが…
以前「真田丸船賃六文波枕 五」 で忍者について書かせて頂きましたが
今回はその忍者のおなじみのあのポーズについて
どろん!
忍術をかける時と五郎丸さんのポーズは同じに見えますが
あれはどんな意味を持つのか?
知りたくなりました
九字護身法 ( くじごしんぼう )
元は日本密教にある「大日経」の実践法のための呪文が、
陰陽道、修験道などにも伝わり、やがて
民間に簡単な形となって、広まったもので、
邪気を払うための呪術です
この呪文が、
臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前
( りん・ぴょう・とう・しゃ・かい・じん・れつ・ざい・ぜん )
この一文字ずつが神仏を意味します
例えば「臨」
普賢三摩耶印(ふげんさんまやいん) 仏格:毘沙門天 神格:天照皇大神
「臨」と唱え、左右の手を組み、人差し指を立てて合わせる。
「臨」が五郎丸さんのルーティンに近いかな?
この、手を組むことを
「印を結ぶ」
その後、「印を切る」 ことが続くのですが…
どちらも漢字の数だけありますが、すみません省略させて頂きます
忍者の場合、それが次第に簡略化された形で
「印を切る」
この部分だけを行います
あの、どろん!の時に
それを、 「早九字護身法・はやくじごしんぼう」 と言います
(九字法とも)
そのポーズですが
右手が刀、左手は鞘(さや)を表します
まず刀は鞘に納めます
呪文を唱えながら鞘から刀を抜き、九字を切る
切る方向も決められていますね
鞘から抜き放たれた刀は邪悪を切り裂くのです
印を切ることによって描かれた格子模様は結界、
結界によって邪悪の侵入を防ぐ
これが忍者のポーズクライマックスでした
五郎丸さんは、もちろん忍者ではありませんが、
” 臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前 ”
りん・ぴょう・とう・しゃ・かい・じん・れつ・ざい・ぜん
” 臨める兵、闘う者、皆前列に陣取っている
(なので、簡単にはそこから進ませないぞ) ”
という呪文を唱えるかどうかは分かりませんが、
精神を統一し
『 大丈夫だ、私なら出来る 』
と気持ちを奮い立たせておられるのでしょうか
それとも、無心に
ただ、あの時のお顔、随分と力の抜けた表情と思われませんか?
南半球、オーストラリアのレッズですか、
スーパーラグビー公式戦でも、見事決まりましたね、五郎丸さん
世界の五郎丸への道をどんどん歩んでおられます
ラグビー選手には、長い間待ち続けた日本のラグビー熱でしょうね
どうぞ、更に強くなって楽しませて下さいね
あ、忍者が隠れてしまってる?
いえいえ、「真田丸」 注目しています
これからの忍者さんの活躍、熱望しております ニンニン













 箕輪城
箕輪城


 猿飛佐助 (真田丸では藤井隆が演じる) は
猿飛佐助 (真田丸では藤井隆が演じる) は
 ではありませぬ
ではありませぬ 素破(すっぱ) 居合抜きの達人
素破(すっぱ) 居合抜きの達人