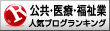「介護支援専門員のための主治医意見書の上手な活用法」財団法人日本公衆衛生協会が掲載されていることを書きましたが、その中を少し紹介します。
「第1章 主治医との連携の重要性」を市川市医師会会長土屋正彦氏が書いている内容に「介護支援専門員が主治医と連携することは、要介護者等に適切なケアプランを作成するうえで大変重要なことであるが、現場では困難な状況が多い」その主な要因として「①医師が他の職種との連携に慣れていない。②介護支援専門員の医療に対する知識や認識が不十分」」と、さらに「在宅での患者さんの生活を十分に把握することが困難な病院勤務の医師に連携を理解してもらうのは、なかなか難しい」と困難なことを指摘している。ただ連携の方法もあわせて紹介しており、それは緊急性の高い低いで情報を伝達する方法が異なることを述べ「メールは、診療で多忙な医師にとっては手が空いた時に対応すればよいことから、緊急性が低い場合の連格方法として適当」であり、緊急時には電話だが「外来診療中は対応が出来ないこともあり配慮を要する」「一般的には午前中の診療時間の早いうちに、要件を簡潔に伝えるのが望ましい」と具体的な方法を述べている。
他にも意見書を読み解く方法やケアプランに活用するポイントも記載されているので一読を勧めたい資料です。
「第1章 主治医との連携の重要性」を市川市医師会会長土屋正彦氏が書いている内容に「介護支援専門員が主治医と連携することは、要介護者等に適切なケアプランを作成するうえで大変重要なことであるが、現場では困難な状況が多い」その主な要因として「①医師が他の職種との連携に慣れていない。②介護支援専門員の医療に対する知識や認識が不十分」」と、さらに「在宅での患者さんの生活を十分に把握することが困難な病院勤務の医師に連携を理解してもらうのは、なかなか難しい」と困難なことを指摘している。ただ連携の方法もあわせて紹介しており、それは緊急性の高い低いで情報を伝達する方法が異なることを述べ「メールは、診療で多忙な医師にとっては手が空いた時に対応すればよいことから、緊急性が低い場合の連格方法として適当」であり、緊急時には電話だが「外来診療中は対応が出来ないこともあり配慮を要する」「一般的には午前中の診療時間の早いうちに、要件を簡潔に伝えるのが望ましい」と具体的な方法を述べている。
他にも意見書を読み解く方法やケアプランに活用するポイントも記載されているので一読を勧めたい資料です。