都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト 「交響曲第4番」 井上道義
ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト2007(Concert 6)
ショスタコーヴィチ 交響曲第4番
指揮 井上道義
管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団
2007/12/1 17:00~ 日比谷公会堂 階下
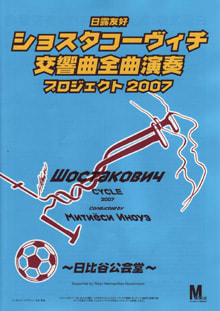
ミッチーこと指揮者の井上道義がヘビメタシンフォニーと呼ぶ、「交響曲第4番」一曲勝負のプログラムです。前回の広響より、オーケストラを東フィルに変えての「ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト」を聴いてきました。
私にはこの曲を咀嚼出来るほどの力は全くありませんが、一連のショスタコーヴィチの交響曲の中でどれが一番好きかと問われれば、現時点では多分これを挙げると思います。そしてこの日は、普段、どこか大人しい印象もある東フィルが一線を越えた、非常に充実した力演を披露してくれました。細かい粗などもろともしない、それこそ車が荒れ地を行くかの如くゴリゴリとうねる低弦、そしてまさにヘビメタのノリで抜群のリズム感を示すティンパニ、さらには美しくも安定感のあるファゴットをはじめとした管楽器群など、どれも力を出し切ったような演奏の様子がとても印象に残ります。またさながらショスタコーヴィチに心の全てを捧げているかのようなコンマス、荒井英治の熱演にも強く引き込まれるものがありました。いつも以上に体を揺らし、椅子からずれ落ちてしまわんというばかりに全身で音楽を表現する様子は、まさに何かが憑依しているかのような鬼気迫る凄みが感じられます。この日の主役を挙げるとすれば間違いなく彼ではないでしょうか。あとは全体にもう一歩、各パート毎の響きを越えるまとまりの意識があればとも思いましたが、それは無い物ねだりのことかもしれません。ここまで熱い東フィルに接したのは初めてだと言えるほどでした。新国ピットの時とはわけが違います。
この4番は私にとってヘビメタというよりも、どちらかと言うとブルックナーと特にマーラーの面白い部分を合わせてさらに高めたような印象を与えてきます。静かに進行するスケルツォや最終楽章で一時、高みへと進む階段はブルックナーのようであり、また目まぐるしく曲想の変化する様や最後のチェレスタなどはマーラーの調べを思い出させました。とは言え、第二楽章の無調の部分やあちこちの音楽からとられたパロディーは、まさに手品を繰り広げるように音楽を展開するショスタコーヴィチならではものです。4番が好きと言っておきながら、実はこの日初めて生に接したわけですが、改めてこれが大変に密度の濃い名曲であることを確認出来ました。
さて既に多くの方もご指摘されておられますが、演奏のラスト、つまりは第三楽章終結部でのチェレスタが鳴り渡る中を弦がピアニッシモで消え行く部分にて悲しい出来事が起りました。フライングの拍手やブラボーなどはこれまでにも何度と体験してきましたが、今回ほど暗澹たる気持ちにさせられたこともありません。背筋のゾクゾクするような彼岸の境地を思わせる、もしくは意味深に、まるで曲が終わらずに永遠に続いていくかのようなこの美しい部分で、それを完全に打ち破る邪魔とも言える行為が入ってしまったわけです。本当に残念でした。
次回は最終日のコンサートを予定していますが、出来れば水曜の公演にも行ってみたいと思います。
ショスタコーヴィチ 交響曲第4番
指揮 井上道義
管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団
2007/12/1 17:00~ 日比谷公会堂 階下
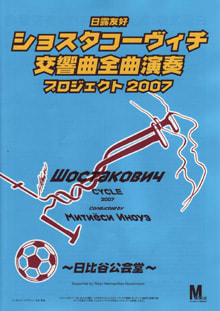
ミッチーこと指揮者の井上道義がヘビメタシンフォニーと呼ぶ、「交響曲第4番」一曲勝負のプログラムです。前回の広響より、オーケストラを東フィルに変えての「ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト」を聴いてきました。
私にはこの曲を咀嚼出来るほどの力は全くありませんが、一連のショスタコーヴィチの交響曲の中でどれが一番好きかと問われれば、現時点では多分これを挙げると思います。そしてこの日は、普段、どこか大人しい印象もある東フィルが一線を越えた、非常に充実した力演を披露してくれました。細かい粗などもろともしない、それこそ車が荒れ地を行くかの如くゴリゴリとうねる低弦、そしてまさにヘビメタのノリで抜群のリズム感を示すティンパニ、さらには美しくも安定感のあるファゴットをはじめとした管楽器群など、どれも力を出し切ったような演奏の様子がとても印象に残ります。またさながらショスタコーヴィチに心の全てを捧げているかのようなコンマス、荒井英治の熱演にも強く引き込まれるものがありました。いつも以上に体を揺らし、椅子からずれ落ちてしまわんというばかりに全身で音楽を表現する様子は、まさに何かが憑依しているかのような鬼気迫る凄みが感じられます。この日の主役を挙げるとすれば間違いなく彼ではないでしょうか。あとは全体にもう一歩、各パート毎の響きを越えるまとまりの意識があればとも思いましたが、それは無い物ねだりのことかもしれません。ここまで熱い東フィルに接したのは初めてだと言えるほどでした。新国ピットの時とはわけが違います。
この4番は私にとってヘビメタというよりも、どちらかと言うとブルックナーと特にマーラーの面白い部分を合わせてさらに高めたような印象を与えてきます。静かに進行するスケルツォや最終楽章で一時、高みへと進む階段はブルックナーのようであり、また目まぐるしく曲想の変化する様や最後のチェレスタなどはマーラーの調べを思い出させました。とは言え、第二楽章の無調の部分やあちこちの音楽からとられたパロディーは、まさに手品を繰り広げるように音楽を展開するショスタコーヴィチならではものです。4番が好きと言っておきながら、実はこの日初めて生に接したわけですが、改めてこれが大変に密度の濃い名曲であることを確認出来ました。
さて既に多くの方もご指摘されておられますが、演奏のラスト、つまりは第三楽章終結部でのチェレスタが鳴り渡る中を弦がピアニッシモで消え行く部分にて悲しい出来事が起りました。フライングの拍手やブラボーなどはこれまでにも何度と体験してきましたが、今回ほど暗澹たる気持ちにさせられたこともありません。背筋のゾクゾクするような彼岸の境地を思わせる、もしくは意味深に、まるで曲が終わらずに永遠に続いていくかのようなこの美しい部分で、それを完全に打ち破る邪魔とも言える行為が入ってしまったわけです。本当に残念でした。
次回は最終日のコンサートを予定していますが、出来れば水曜の公演にも行ってみたいと思います。
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )









