都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト 「交響曲第11、12番」 井上道義
ショスタコーヴィチ交響曲全曲演奏プロジェクト2007(Concert 7)
ショスタコーヴィチ 交響曲第11番、第12番
指揮 井上道義
管弦楽 名古屋フィルハーモニー交響楽団
2007/12/5 19:00~ 日比谷公会堂 階下
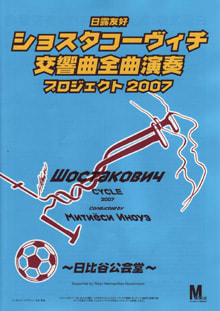
当日券で駆けつけました。ミッチー自身が「世界のどこでもやらない。」とも言う、第11番と第12番の超重量級プログラムです。そしてその大役をつとめるオーケストラは、これまたご本人曰く「これはかけである。」とも述べた名フィルでした。
結論から言ってしまうと、演奏の精度そのものはかなり荒々しい、むしろ粗の目立つ内容でありましたが、それこそまたまたミッチーの言う「ベルリンフィルでも名フィルでも得られる感動は関係ない。」の言葉の通り、非常に感動的なコンサートであったと思います。そしてさらにその感動という点においては、おそらくは第12番の方が演奏の完成度の点で上回るものの、井上の細部までに行き届いた解釈と曲本来の力も借りて、11番がより感銘を受ける演奏であったとも感じました。苦悩を示すように切々と、しかしそれでいながら打ち寄せる大波小波のように起伏も大きく歌う一楽章の冒頭や、今度は一転して奈落の底へ落とされるかのように激しく、また猛然とテンポをまくしあげるアレグロ楽章など、総じて緩急の差の大きい、非常にダイナミックな表現を聴かせてくれたと思います。全てアタッカで続く長大な交響曲ですが、一時の緊張感をそがれることがありませんでした。9、14、4と聴いて来て、一番ミッチーの良さが出ているとも感じたのが今回の11番です。
名フィルは初めてでしたが、あともう一歩、全体的に細やかな表現があればより良かったのではないでしょうか。イングリッシュホルンをはじめとする木管の厚みのある音や、もはや鳴らすというよりも壊さんとばかりに叩くティンパニの潔いほど強烈な演奏には感じるものがありましたが、弦セクション、特にヴァイオリンに音圧感が不足するのが残念に思えました。ただ「同志は倒れぬ」を歌うヴィオラのしっとりとした音色は秀逸です。ここは音に包み込まれるような気持ちで聴き入ることが出来ました。
後半の12番は、私の浅い耳ではまだ曲をどう捉えてよいのかがわかりません。殆ど唐突に登場してすぐさま消える歓喜の主題の調べだけが耳に残りました。歓喜でありながらも、どこかとってつけたかのように申し訳なく登場してきます。不気味です。
座って聴いているだけでも疲労感に襲われるようなプログラムでしたが、井上を含む演奏者の方々の熱意を目の前にすると、そのような悠長なことも言ってられません。次回の日曜日、8番と15番の演奏でこのプロジェクトが締めくくられます。もちろんそちらも聴いてくるつもりです。
ショスタコーヴィチ 交響曲第11番、第12番
指揮 井上道義
管弦楽 名古屋フィルハーモニー交響楽団
2007/12/5 19:00~ 日比谷公会堂 階下
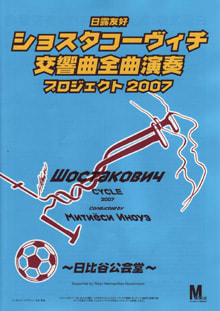
当日券で駆けつけました。ミッチー自身が「世界のどこでもやらない。」とも言う、第11番と第12番の超重量級プログラムです。そしてその大役をつとめるオーケストラは、これまたご本人曰く「これはかけである。」とも述べた名フィルでした。
結論から言ってしまうと、演奏の精度そのものはかなり荒々しい、むしろ粗の目立つ内容でありましたが、それこそまたまたミッチーの言う「ベルリンフィルでも名フィルでも得られる感動は関係ない。」の言葉の通り、非常に感動的なコンサートであったと思います。そしてさらにその感動という点においては、おそらくは第12番の方が演奏の完成度の点で上回るものの、井上の細部までに行き届いた解釈と曲本来の力も借りて、11番がより感銘を受ける演奏であったとも感じました。苦悩を示すように切々と、しかしそれでいながら打ち寄せる大波小波のように起伏も大きく歌う一楽章の冒頭や、今度は一転して奈落の底へ落とされるかのように激しく、また猛然とテンポをまくしあげるアレグロ楽章など、総じて緩急の差の大きい、非常にダイナミックな表現を聴かせてくれたと思います。全てアタッカで続く長大な交響曲ですが、一時の緊張感をそがれることがありませんでした。9、14、4と聴いて来て、一番ミッチーの良さが出ているとも感じたのが今回の11番です。
名フィルは初めてでしたが、あともう一歩、全体的に細やかな表現があればより良かったのではないでしょうか。イングリッシュホルンをはじめとする木管の厚みのある音や、もはや鳴らすというよりも壊さんとばかりに叩くティンパニの潔いほど強烈な演奏には感じるものがありましたが、弦セクション、特にヴァイオリンに音圧感が不足するのが残念に思えました。ただ「同志は倒れぬ」を歌うヴィオラのしっとりとした音色は秀逸です。ここは音に包み込まれるような気持ちで聴き入ることが出来ました。
後半の12番は、私の浅い耳ではまだ曲をどう捉えてよいのかがわかりません。殆ど唐突に登場してすぐさま消える歓喜の主題の調べだけが耳に残りました。歓喜でありながらも、どこかとってつけたかのように申し訳なく登場してきます。不気味です。
座って聴いているだけでも疲労感に襲われるようなプログラムでしたが、井上を含む演奏者の方々の熱意を目の前にすると、そのような悠長なことも言ってられません。次回の日曜日、8番と15番の演奏でこのプロジェクトが締めくくられます。もちろんそちらも聴いてくるつもりです。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )










