都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「田園讃歌 - 近代絵画に見る自然と人間 - 」 埼玉県立近代美術館
埼玉県立近代美術館(さいたま市浦和区常盤9-30-1)
「田園讃歌 - 近代絵画に見る自然と人間 - 」
10/27-12/16

山梨県美のミレー「落ち穂拾い、夏」(1853)と、埼玉県美のモネ「ジヴェルニーの積みわら、夕日」(1888)を二点を核に、主に西欧と日本の近代絵画にて田園風景、自然と人間の関係を辿ります。埼玉県立近代美術館の開館25周年を記念する展覧会です。
構成は以下の通りです。「田園」をモチーフとした作品、約140点が展示されています。
1「豊饒の大地と敬虔な農民たち」:バルビゾン派よりミレー、その周辺。
2「近代都市パリを離れて」:印象派と後期印象派。モネ、ピサロ、ゴーガン、ヴラマンクなど。
3「日本の原風景を求めて」:日本の近代洋画と日本画。浅井忠、萬鉄五郎、村上華岳。
4「何処から、そして何処へ」:19世紀以降のポスターや写真、コンテンポラリーなど。ベアト、木村伊兵衛、リキテンスタイン。


ミレーがそこそこ充実しています。さすがにオルセーの誇る「落ち穂拾い」の展示はありませんが、「落ち穂拾い、夏」(1853)と「一日の終わり」(1865)など油彩数点の他、耕作を主題としたエッチングなどもいくつか紹介されていました。特に興味深いのは、オルセーの作品の前に作られたという版画、「落ち穂拾い(第2版)」(1855)です。エッチングの特性もあるのか、油彩で見るよりも、例えば背景の積みわらで作業する人びとや、今女性たちが拾おうとしている落ち穂そのものなどの細部がとても精緻に表現されています。また落ち穂関連として、実際の作品を模写して描いた和田英作の「ミレー『落穂拾い』模写」(1903)も興味深い作品です。西欧の絵画を摂取して、自身の表現を高めようとした当時の日本人の制作意欲を感じます。秀作でした。


展示のハイライトは、やはり埼玉県美御自慢の作品、モネの「ジヴェルニーの積みわら、夕日」(1888)かもしれません。サーモンピンクに染まる夕景の中を、農業国フランスの富を象徴するという積みわらが微睡むかのように佇んでいます。またこの積みわら主題の作品としては、淡いタッチにて栗のような積みわらを示すピサロの「積みわらのある平原」(1873)も印象に残りました。それにピサロではセザンヌの影響を見る「エラニーの教会と農園」(1884)や、今度はスーラやシニャックの点描を思わせる「エラニーの牧場」(1885)などにも見応えがあります。そして忘れてはいけないのがシスレーの一点、「森のはずれ、6月」(1884)です。画面全体に木々が覆い被さり、後景の視界が狭められるというシスレーらしからぬ構図感がとても斬新に感じられました。また、うねるような幹と大胆なタッチの繁みはどこかゴッホをも連想させます。この展覧会で一番感じ入ったカリエールの「羊飼いと羊の群れ」(1877)と合わせて、ともに一推しにしたい作品です。

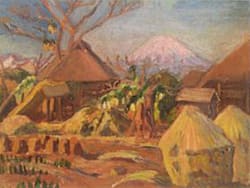
日本の近代絵画(日本画を含む)では、唯一、洋画、日本画の両方に展示のあった萬鉄五郎を挙げたいと思います。実際のところ私は彼の作品がかなり苦手ですが、作風の変遷(堅実な風景描写からゴッホ風の表現を経由し、彼に特徴的な輝かしい赤を用いた絵画へと変化していきます。)も面白い風景画の三点と、躍動感のある墨線にて田園を描いた「秋景農夫図」(1925)にはそれぞれ惹かれるものがありました。またかけがえのない画家の一人でもある、須田国太郎の「信楽」(1935)を見られたのも大きな収穫です。稜線の折重なる山々を背景に、連なる日本家屋と手前に広がる田園、そして小さな積みわら群が、実に重厚な感触にて描かれています。うっすらと桃色を帯びた深い須田カラーも冴えていました。
最後に見る「何処から、そして何処へ」は、その賛否も分かれそうな冒険的なセクションです。西欧の国民国家形成の過程で、ナショナリズム的なものに訴えかけるために作成されたポスター群(19世紀の西欧の食料節約運動のポスターなどが展示されています。大地を耕す逞しい女性の姿が描かれていました。)から、木村伊兵衛、濱谷浩の日本の農村を捉えた作品、さらには積みわらモチーフのリキテンスタインらの絵画までが一堂に紹介されています。そしてここで記憶に残ったのは、明治から昭和前期にかけての日本の農村を捉えた手彩色の観光写真絵葉書です。これらの風景写真は当時、外国人のみやげとして人気があったとのことで、葉書の表題も英語で書かれていました。一概に言えるものではありませんが、どこか西欧における巴水の受容を見る思いもします。
身近な田園風景をじっくりと見る機会などそうありませんが、帰路、武蔵野線の車窓より広がる見慣れた野原の景色がどこか新鮮にうつりました。これから残すべき価値のある風景とはまさにこのようなものを指すのかもしれません。
次の日曜日、16日までの開催です。なお埼玉展終了後、以下、北九州市立美術館(2008/1/2~2/17)、ひろしま美術館(2/23~4/6)、山梨県立美術館(4/19~6/1)へと巡回します。(12/8)
「田園讃歌 - 近代絵画に見る自然と人間 - 」
10/27-12/16

山梨県美のミレー「落ち穂拾い、夏」(1853)と、埼玉県美のモネ「ジヴェルニーの積みわら、夕日」(1888)を二点を核に、主に西欧と日本の近代絵画にて田園風景、自然と人間の関係を辿ります。埼玉県立近代美術館の開館25周年を記念する展覧会です。
構成は以下の通りです。「田園」をモチーフとした作品、約140点が展示されています。
1「豊饒の大地と敬虔な農民たち」:バルビゾン派よりミレー、その周辺。
2「近代都市パリを離れて」:印象派と後期印象派。モネ、ピサロ、ゴーガン、ヴラマンクなど。
3「日本の原風景を求めて」:日本の近代洋画と日本画。浅井忠、萬鉄五郎、村上華岳。
4「何処から、そして何処へ」:19世紀以降のポスターや写真、コンテンポラリーなど。ベアト、木村伊兵衛、リキテンスタイン。


ミレーがそこそこ充実しています。さすがにオルセーの誇る「落ち穂拾い」の展示はありませんが、「落ち穂拾い、夏」(1853)と「一日の終わり」(1865)など油彩数点の他、耕作を主題としたエッチングなどもいくつか紹介されていました。特に興味深いのは、オルセーの作品の前に作られたという版画、「落ち穂拾い(第2版)」(1855)です。エッチングの特性もあるのか、油彩で見るよりも、例えば背景の積みわらで作業する人びとや、今女性たちが拾おうとしている落ち穂そのものなどの細部がとても精緻に表現されています。また落ち穂関連として、実際の作品を模写して描いた和田英作の「ミレー『落穂拾い』模写」(1903)も興味深い作品です。西欧の絵画を摂取して、自身の表現を高めようとした当時の日本人の制作意欲を感じます。秀作でした。


展示のハイライトは、やはり埼玉県美御自慢の作品、モネの「ジヴェルニーの積みわら、夕日」(1888)かもしれません。サーモンピンクに染まる夕景の中を、農業国フランスの富を象徴するという積みわらが微睡むかのように佇んでいます。またこの積みわら主題の作品としては、淡いタッチにて栗のような積みわらを示すピサロの「積みわらのある平原」(1873)も印象に残りました。それにピサロではセザンヌの影響を見る「エラニーの教会と農園」(1884)や、今度はスーラやシニャックの点描を思わせる「エラニーの牧場」(1885)などにも見応えがあります。そして忘れてはいけないのがシスレーの一点、「森のはずれ、6月」(1884)です。画面全体に木々が覆い被さり、後景の視界が狭められるというシスレーらしからぬ構図感がとても斬新に感じられました。また、うねるような幹と大胆なタッチの繁みはどこかゴッホをも連想させます。この展覧会で一番感じ入ったカリエールの「羊飼いと羊の群れ」(1877)と合わせて、ともに一推しにしたい作品です。

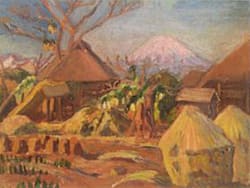
日本の近代絵画(日本画を含む)では、唯一、洋画、日本画の両方に展示のあった萬鉄五郎を挙げたいと思います。実際のところ私は彼の作品がかなり苦手ですが、作風の変遷(堅実な風景描写からゴッホ風の表現を経由し、彼に特徴的な輝かしい赤を用いた絵画へと変化していきます。)も面白い風景画の三点と、躍動感のある墨線にて田園を描いた「秋景農夫図」(1925)にはそれぞれ惹かれるものがありました。またかけがえのない画家の一人でもある、須田国太郎の「信楽」(1935)を見られたのも大きな収穫です。稜線の折重なる山々を背景に、連なる日本家屋と手前に広がる田園、そして小さな積みわら群が、実に重厚な感触にて描かれています。うっすらと桃色を帯びた深い須田カラーも冴えていました。
最後に見る「何処から、そして何処へ」は、その賛否も分かれそうな冒険的なセクションです。西欧の国民国家形成の過程で、ナショナリズム的なものに訴えかけるために作成されたポスター群(19世紀の西欧の食料節約運動のポスターなどが展示されています。大地を耕す逞しい女性の姿が描かれていました。)から、木村伊兵衛、濱谷浩の日本の農村を捉えた作品、さらには積みわらモチーフのリキテンスタインらの絵画までが一堂に紹介されています。そしてここで記憶に残ったのは、明治から昭和前期にかけての日本の農村を捉えた手彩色の観光写真絵葉書です。これらの風景写真は当時、外国人のみやげとして人気があったとのことで、葉書の表題も英語で書かれていました。一概に言えるものではありませんが、どこか西欧における巴水の受容を見る思いもします。
身近な田園風景をじっくりと見る機会などそうありませんが、帰路、武蔵野線の車窓より広がる見慣れた野原の景色がどこか新鮮にうつりました。これから残すべき価値のある風景とはまさにこのようなものを指すのかもしれません。
次の日曜日、16日までの開催です。なお埼玉展終了後、以下、北九州市立美術館(2008/1/2~2/17)、ひろしま美術館(2/23~4/6)、山梨県立美術館(4/19~6/1)へと巡回します。(12/8)
コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )










