都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「富岡鉄斎展」 大倉集古館
大倉集古館(港区虎ノ門2-10-3 ホテルオークラ東京本館正門前)
「大和文華館所蔵 富岡鉄斎展 - 躍動する形と色 - 」
10/6-12/16
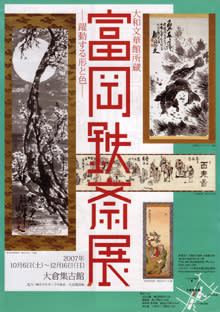
幕末生まれで、最後の文人画家ともいわれる富岡鉄斎(1836-1924)の画業を紹介します。大倉集古館での回顧展です。
今回展示されている大和文華館の富岡鉄斎のコレクションの元を辿ると、実際に当時、鉄斎と交流のあった松山の近藤文太郎氏の所蔵品に行き着きます。近藤は鉄斎がそれほど有名でない頃からの友人で、例えば鉄斎の制作料の取り立てなどを行うほど面倒見の良い人物でもありました。それに鉄斎の妻が近藤と同じく松山出身であるという縁もあったようです。展示でも両者の間柄を示す書簡が多く出品されています。また、近藤から贈られた海老をスケッチした「伊勢海老図」(明治37年)なども紹介されていました。朱色の瑞々しい点描が海老を象っています。活きの良い海老を見て喜んだ鉄斎の姿が目に浮かぶかのようでした。


一般的に鉄斎は文人画家とされていますが、その作風はかなり多彩です。もちろん制作の中心は南画だったようですが、その他にも精緻な大和絵や、極めて即興的な、例えば仙がいの水墨のような作品もたくさん手がけていました。中でも、特にオリジナリティと魅力を感じるのは水墨画です。私淑していた牧渓の画を模した「魚藻図」(大正3年)に見る躍動感や、墨の濃淡だけで夜の寒梅を叙情的に画いた「寒月照梅華図」(明治44年)などには惹かれるものがありました。また彩色ですが、伏見人形を可愛らしく描いた「天神土人形図」(明治35年)も一推しの作品です。桃色の衣を纏う人形がヘタウマのような味わいにて表されています。心が和みました。
幕末期に勤皇思想を奉じ、自身も神官をつとめていたという鉄斎は、いわゆる神国日本を賛美するような作品もいくつか描いていました。そして、その手の主題としてはお馴染みの富士山の画も当然登場しています。ここでは巨大な画面を埋め尽くすかのような富士山が圧倒的な迫力にて描かれていますが、目を凝らすと山頂へ向う人たちが砂糖に群がる蟻のように点々と連なって描かれていることが分かりました。また妙にリアルな岩肌の描写なども気になるところですが、これは鉄斎が実際に登って見た景色が反映されているからなのだそうです。この辺は、大観の描くシンボリックな富士山と一線を画しています。

鉄斎の他、大和文華館より特別出品として、若冲の鶏、松村景文の花鳥、そして抱一の「瓶花図」(1815)が展示されていました。残念ながら抱一の画にはあまり筆の冴えがありませんが、これは彼が執り行った光琳百回忌の折、その協力者へのいわばお礼という形で配布された作品のうちの一つなのだそうです。ちなみに抱一はこの「お礼」を何と100幅制作したと考えられています。粉本も確認されているそうなので、ここに見る類型化された表現は致し方ないのかもしれません。
12月16日までの開催です。(12/8)
「大和文華館所蔵 富岡鉄斎展 - 躍動する形と色 - 」
10/6-12/16
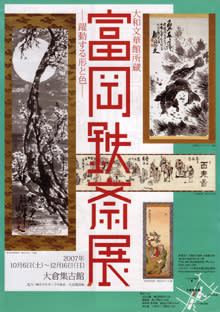
幕末生まれで、最後の文人画家ともいわれる富岡鉄斎(1836-1924)の画業を紹介します。大倉集古館での回顧展です。
今回展示されている大和文華館の富岡鉄斎のコレクションの元を辿ると、実際に当時、鉄斎と交流のあった松山の近藤文太郎氏の所蔵品に行き着きます。近藤は鉄斎がそれほど有名でない頃からの友人で、例えば鉄斎の制作料の取り立てなどを行うほど面倒見の良い人物でもありました。それに鉄斎の妻が近藤と同じく松山出身であるという縁もあったようです。展示でも両者の間柄を示す書簡が多く出品されています。また、近藤から贈られた海老をスケッチした「伊勢海老図」(明治37年)なども紹介されていました。朱色の瑞々しい点描が海老を象っています。活きの良い海老を見て喜んだ鉄斎の姿が目に浮かぶかのようでした。


一般的に鉄斎は文人画家とされていますが、その作風はかなり多彩です。もちろん制作の中心は南画だったようですが、その他にも精緻な大和絵や、極めて即興的な、例えば仙がいの水墨のような作品もたくさん手がけていました。中でも、特にオリジナリティと魅力を感じるのは水墨画です。私淑していた牧渓の画を模した「魚藻図」(大正3年)に見る躍動感や、墨の濃淡だけで夜の寒梅を叙情的に画いた「寒月照梅華図」(明治44年)などには惹かれるものがありました。また彩色ですが、伏見人形を可愛らしく描いた「天神土人形図」(明治35年)も一推しの作品です。桃色の衣を纏う人形がヘタウマのような味わいにて表されています。心が和みました。
幕末期に勤皇思想を奉じ、自身も神官をつとめていたという鉄斎は、いわゆる神国日本を賛美するような作品もいくつか描いていました。そして、その手の主題としてはお馴染みの富士山の画も当然登場しています。ここでは巨大な画面を埋め尽くすかのような富士山が圧倒的な迫力にて描かれていますが、目を凝らすと山頂へ向う人たちが砂糖に群がる蟻のように点々と連なって描かれていることが分かりました。また妙にリアルな岩肌の描写なども気になるところですが、これは鉄斎が実際に登って見た景色が反映されているからなのだそうです。この辺は、大観の描くシンボリックな富士山と一線を画しています。

鉄斎の他、大和文華館より特別出品として、若冲の鶏、松村景文の花鳥、そして抱一の「瓶花図」(1815)が展示されていました。残念ながら抱一の画にはあまり筆の冴えがありませんが、これは彼が執り行った光琳百回忌の折、その協力者へのいわばお礼という形で配布された作品のうちの一つなのだそうです。ちなみに抱一はこの「お礼」を何と100幅制作したと考えられています。粉本も確認されているそうなので、ここに見る類型化された表現は致し方ないのかもしれません。
12月16日までの開催です。(12/8)
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )










