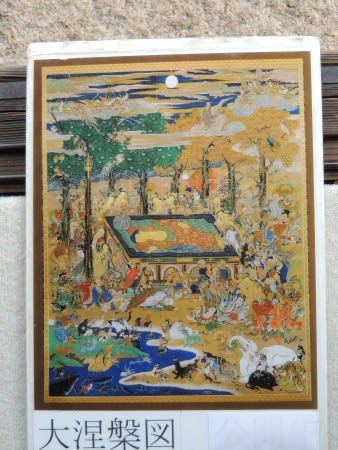東近江市にある猪子山(標高268m)の山頂に「北向岩屋十一面観音」と呼ばれる岩窟の中に祀られた石仏があるといいます。
東近江市にある猪子山(標高268m)の山頂に「北向岩屋十一面観音」と呼ばれる岩窟の中に祀られた石仏があるといいます。猪子山から繖山(標高433m)へは尾根沿いに通じており、「北向岩屋十一面観音」「石馬寺」「桑実寺」「観音正寺」「教林坊」などの寺院が山中に存在する霊山といえる山々。
また、東近江市から野洲・栗東にかけては“巨石や磐座”に対する信仰が感じられる地域で、古墳も多いことから古代より文化が栄えた地でもあったとされています。
猪子山の「北向岩屋十一面観音」は、奈良時代に安置されたものとされ、平安時代には坂上田村麻呂が鈴鹿の鬼賊退治のため、岩屋にこもり十一面観音菩薩に武運を祈願したとも伝わります。

麓の集落で道に迷いながら林道の登り口を探していた時に感じたことは、猪子山の上へと向かう長い石段のある神社が多いこと。
また集落の外れには道祖神として祀っているのかと思われる石仏地蔵が多い。
それだけ神山に対する信仰が深いということになり、寺院も多くみられる信仰の深い地域ともいえます。

当方は「北向岩屋十一面観音」へつながる石段の登り口まで車でショートカットしたのですが、麓から歩いて登っていかれる方が数組おられたのには驚きます。
おそらくは地元の方なのでしょうけど、信仰と健康づくりの両面から日常的にお参りされているのかと想像します。

石段は急な傾斜となっていたが、誰もいない山道とは違って人の姿が見えるので安心して登れる。
とはいっても途中まで登ると、さすがに息が切れてくる。
疲れがきたところにいい言葉の彫られた短歌の石碑があり、その言葉が気持ちを和ませてくれる。
『急坂を 息を切らして 登りきて 観音さまに 会うぞ嬉しき』

観音堂は巨石と一体化したように建てられており、背後にある巨石は「天鈿女命(観音さまの祠岩)」として祀られています。
「天鈿女命(アマノウズメノミコト)」は、「岩戸隠れ」で天照大神が天岩戸に隠れた際に岩屋の前で踊り、大神を誘い出したとされる女神です。

この祠石に岩窟があり、中に祀られた「十一面観音石仏」は、十一面観音の女性的な部分と女神が融合されるようにして信仰されてきた印象を受ける。
観音堂内には先に参拝された方が焚かれたと思われる線香の煙と香りが漂い、厳しい修行の場所というより柔らかな場所のように感じる。

岩窟に祀られた十一面観音石仏は、像高48cm・光背30cm・蓮座高13.5cmの石造仏で、合掌した手に数珠を掛けている姿は珍しいといわれている。
観音堂の中は綺麗に整備され、花も活けられていることから、日常的にお世話をされている方がおられるのでしょう。


観音堂のすぐ横には「巨石信仰岩神群/磐座」として「玉祖神命」が祀られています。
玉祖神命は、天照大神が天岩戸に篭った時におびき出すために「八尺瓊勾玉」を造った神とされ、八尺瓊勾玉は「三種の神器」として謂われがある神器です。
2019年10月に行われた「即位礼正殿の儀」でも三種の神器のうちの「草薙剣」と「八尺瓊勾玉」が「高御座」に運ばれて、皇位が継承されたのも記憶に新しいところです。


猪子山から眺める眺望は雲はかかってはいたが絶景が拡がり、見晴らしがよい。
右に見える山は荒神山。地平線の奥には琵琶湖が広がる。

琵琶湖の手前にある湖は伊庭内湖。
近江八幡市の伊崎寺などがある山と沖島の向こうに微かに見えるのは比良山系かと思われます。

伊庭内湖の上空には気球が飛んでいる。
時折、バーナーの炎も見えましたが、この気球はどこから来てどこへ飛んでいくのでしょうね。

眺望は琵琶湖方面と東側の展望台からも眺めることができる。
こちらは連なる山系の間に広がる盆地ですが、位置関係はよく分からない。

帰路に立ち寄ったのは、近江の奇祭「伊庭の坂下し祭り」の神事が行われる「繖峰三神社」でした。
急勾配の岩場の斜面を重さ400キロもあるとされる三基の神輿を御輿上げし、坂下しの神事の当日に引き下ろされるといいます。

「伊庭の坂下し」は五穀豊穣を願う神事だといい、ニュースや新聞などで取り上げられることの多い神事ですが、登るのも困難かと思われる難所続きの岩場で神輿を下していく猛々しい神事です。
道の途中には高低差6mの断崖絶壁の難所や角度40°を越える急斜面もあるといい、そこを400kgもあるという神輿を下す勇壮な祭りはまさに命がけ。
神事はかつては4月下旬から5月上旬に“辰に昇りて巳に下る”として日を選んでいたそうですが、現在は5月連休に行われるようになり、およそ850年前から神事は行われているといいます。

鳥居の奥にある坂道を見ただけで登る気力が失せてしまい、鳥居を入ったところで手を合わせて帰りましたが、この坂道は約500m続くといいます。
伊庭の坂の凄さは入口から見ただけでは実際の凄さは分かりませんが、“伊庭の祭りは一度は見やれ、男肝つく坂下し”なんて歌もあるそうです。

ところで、猪子山での石段登りの道中では何種かの野鳥が見聞きすることが出来ました。
見聞き出来たのは、冬の野鳥のジョウビタキ・アオジ・ツグミ・アカゲラもしくはアオゲラの囀りなど...。
猪子山は“タカの渡り”の観察ポイントとして有名な山ですが、越冬する小鳥も多そうな山でしたので、伊庭内湖と合わせて探鳥してみるのも面白いかもしれませんね。