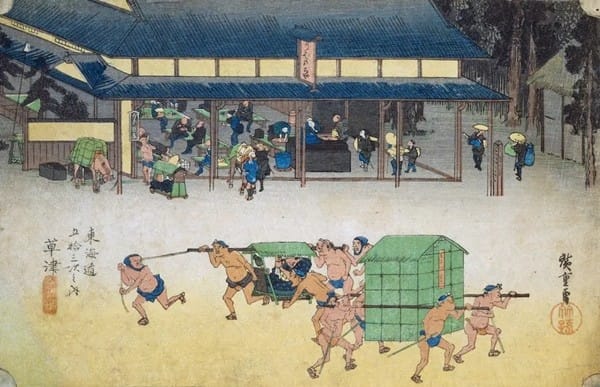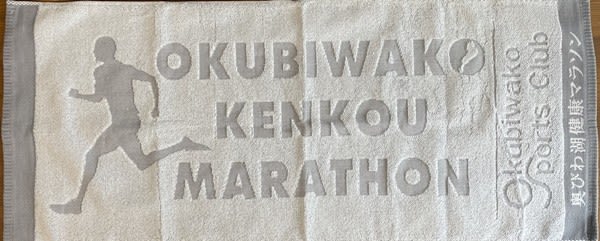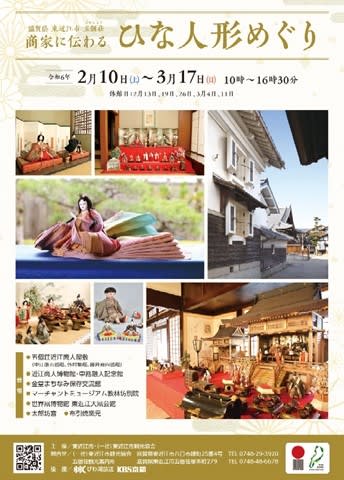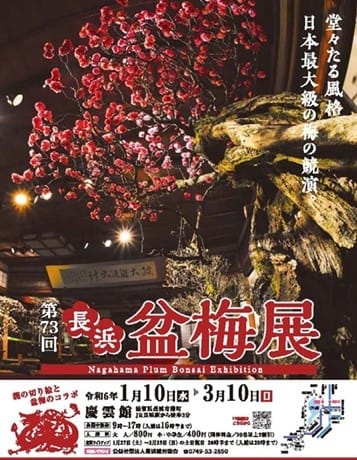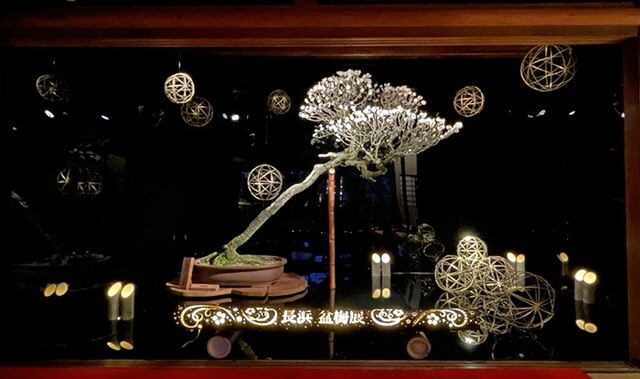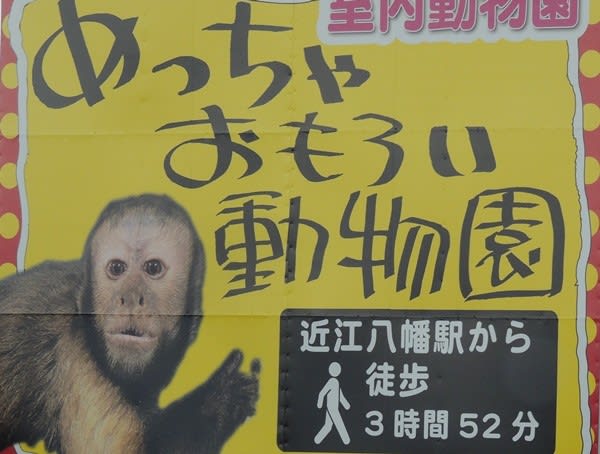今年の紅葉は色づきが遅れているようでしたが、そろそろ見頃かな?と紅葉狩りに行ってみたらジャスト・タイミングで見頃を迎えていました。
今年の紅葉は色づきが遅れているようでしたが、そろそろ見頃かな?と紅葉狩りに行ってみたらジャスト・タイミングで見頃を迎えていました。紅葉は、色づき具合・天気の光加減や太陽の位置、落葉の状態など条件がいろいろある中で、色づきと光の加減は丁度良い時に恵まれたのではないでしょうか。
近年は、紅葉に限らず青紅葉や庭園のリフレクションが写せるようにされている所が多く、床や机の上には鏡面のシートが準備されていました。
みなさん机の上にカメラを載せたり、床に転がってリフレクションの出る位置を探したりします。

今回はリフレクションの紅葉を水晶玉に写し込むという技を教えて頂き、撮影することが出来ました。
紅葉はリフレクションで撮影するとスマホでも雰囲気が出るものなんですが、さらに水晶玉に写し込めば景色は反転する。
教えて頂いた上に撮影までさせて頂いた方には大大大感謝!です。

社務所の間での外にある大きな紅モミジの木はまさに今が見頃。襖絵のように見える艶やかな色づきです。
黄色く色づいたモミジと黒い幹や障子の枠との対比があり、グラディエーションも楽しめます。

障子4枚をリフレクションで撮ってみました。
額縁の中に描かれた絵画のような雰囲気がありますが、ガラス障子の上の部分が摺りガラスなのも雰囲気を出しています。

紅く色づいた方のモミジのリフレクションを社務所の方に教えてもらって、寝転がって撮ってみる。
順番を待ってカメラを持った方々が次々に寝転がって撮影している面白い時間でした。


次は部屋の中で寝転がる方向を変えて黄色いモミジを撮ります。
その場に居た人は状況が分かっているから良いものの、後から来た人は人が交互に寝転がって撮影しているのを見てさぞや驚かれたことでしょう。

犬上川は水量もそこそこあって、削れた川岸の岩々に迫力があります。
安全のためか、川岸へ下りることが出来なくなっていましたのは少し残念でした。

せっかくなのでもう一カ所、紅葉スポットに立ち寄ってみます。
この位置から見える木々は紅葉しているのですが、この角度からは日陰になって色合いが出ないのが惜しい。

長閑な参道には紅いモミジが覆いかぶさり、奥には黄色や橙色の紅葉の奥に銀杏の大木が見えます。
神社や寺院の境内に銀杏があることが多いのは、銀杏は貯水性が高い樹木なため防火の役割があって多いのだとされます。

石段の上には紅や黄色や橙色に緑の葉がグラディエーションを作り、カラフル!と声に出しそうになるような美しさです。
真上を見上げてみたら絵の具で描いたような色彩ですが、これは人が絵の具で描くより美しいのでは?と感じてしまいます。


鐘楼の周辺のモミジは横にある石段にある紅葉共々、色鮮やかな紅葉に囲まれています。
まだほとんど落葉していないので、次は落葉した紅葉の時期へと変わって行くのでしょう。


2躰のお地蔵さんの後方には銀杏の木。
境内奥にある銀杏の大木より樹齢は若いと思いますが、地蔵と銀杏の黄色い葉の組み合わせは今だけ見られる光景です。

寺院へとつながる舗装道は彩りの道。
自然が醸し出すカラフルさは人為的には作り出せないものだと思います。

次の週末は天気が崩れる気配ですので、今年の紅葉はこれが最後かな!?
とはいえ、今年の紅葉にジャスト・タイミングだったようで運が良かったな。