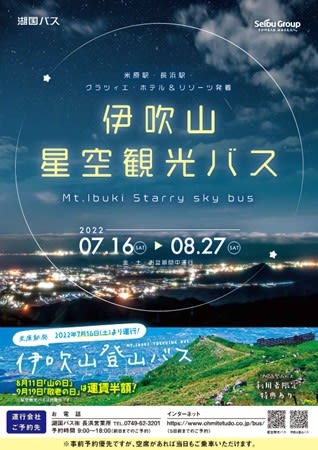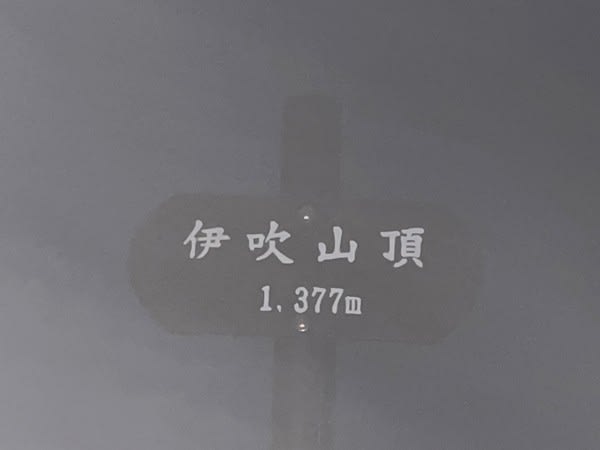正月の3ヶ日が明けた4日からクロヅルが湖北に飛来してきたのがニュースになっていました。
正月の3ヶ日が明けた4日からクロヅルが湖北に飛来してきたのがニュースになっていました。雪の降った翌日で空はドンヨリした暗い雲の下の悪条件で撮影できるか分からないものの、ダメ元で探鳥に行ってきました。
冬の田圃に飛来する野鳥は、野鳥を探すより田圃横に停まる2~3台の車を見つければ容易に発見出来ます。
そもそも冬の田圃道に複数の車が停まっていること自体が実に怪しい。
...ということで田圃道に停まる怪しい車の方向へ行くと、田圃に大きな影が見つかりました!

滋賀県内にクロヅルが飛来したのは3例目ということでレアな鳥ではありますが、天候が悪かったのが難点です。
見つけた後、長い時間羽繕いをしていたのですが、やっと食事を初めてくれました。
タニシかミミズか。何を食べているのでしょうか?
クチバシでつまんで飲み干しています。

忘れていたのですが、当方はクロヅルはライファーではなく、2009年にも撮影しています。
でもその時のクロヅルは幼鳥でしたので、今回見た個体とは違う鳥かと思うほど外見が違います。
2009年のクロヅルは全体的に茶色っぽい姿で、今回のは体全体が淡灰色で頭から首にかけて黒色で頬から後頭部が白い。
クロヅルに関しては16年振りということになりますが、野鳥全体で言えばいつのまにやら野鳥歴20年になってしまいました。

田圃にはクロヅルの他にはコハクチョウの成鳥と幼鳥っぽいのが1羽ずつで親子かな?
クロヅルとのスリー・ショットはならずながら、コハクチョウは今にも飛び立とうとしていました。

コハクチョウ(成鳥)が飛んだ!
クロヅルは気にする素振りもなく食事中。

コハクチョウ(幼鳥)も飛んだ!
相変わらず気にせず食事中のクロヅル。
その後もクロヅルは田圃の中をウロウロしていたが、車の中とはいえ寒空に窓が全開で寒くなってきたのでこれで終了。

鶴は古来より長寿をあらわす吉兆の鳥とされ縁起の良い鳥です。
「吉兆鶴(吉兆クロヅル)」にあやかって明るい話題の多い令和7年になるといいですね!
 【復刻】2009年に湖北に飛来してきたクロヅルの幼鳥!
【復刻】2009年に湖北に飛来してきたクロヅルの幼鳥!過去のファイルを探したら16年前に湖北に飛来したクロヅル幼鳥の動画が出てきました。
映像はかなり悪く証拠動画レベルです。最後はケリに飛ばされてしまいました。