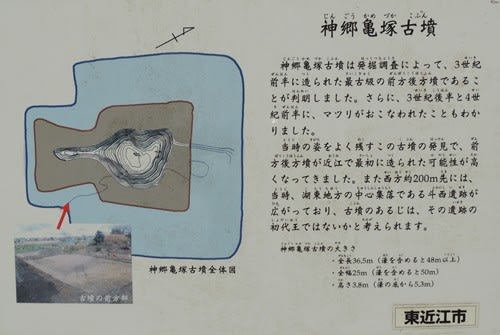南花沢のハナノキ
南花沢のハナノキ国道307号線を走行していると「南花沢のハナノキ」の案内板がいつも目に入ってきます。
「南花沢のハナノキ」は2010年に倒壊したと聞いていましたので訪れてはいなかったのですが、国道307を移動中に急に思い立って訪れてみました。
ハナノキは北花沢と南花沢の2カ所にあり、両方の樹ともに1921年に国の天然記念物の指定を受けているそうです。
「南花沢のハナノキ」は八幡神社の境内にあり、御神木として信仰されてきたといい、崩壊した時は推定樹齢300年以上、伝承では1200年ともされていたといいます。

境内の中央にはかつてあったハナノキの跡地が残されており、石碑が建てられている。
この跡地を見ると、ハナノキがいかに大事に扱われてきた御神木かが伺われます。


跡地に残るのは根っこの部分だけですが、よく見ると何本もの枝が成長しているのが分かります。
落雷等によって空洞化し、腐朽して倒壊したとされますが、この生命力は大したものだと思います。

往時の「南花沢のハナノキ」は幹周が5.2m・樹高が15mだったとされますが、倒壊した主幹は今も御神木として祠の中に安置されています。
その幹たるや歴史的な価値のある御神木そのもので、ゴツゴツした幹の瘤からは樹齢の長さと、生き続けた期間の長さに凄みすら感じます。

ハナノキにまつわる由緒には、聖徳太子が百済寺建立の際に「仏法が末永く隆盛していくなら、この木も成長していくだろう」と箸を南・北花沢に各々1本差されたものが成長したとの伝承があります。
聖徳太子や空海・最澄など食事を終えた箸を植えたものが巨樹になったという伝承は実に多いですね。

境内の横の方には次世代のハナノキが新しい御神木として祀られていました。
このハナノキが何百年か経ったら、巨樹に育ち人々に感嘆の声をもたらすのかもしれません。

北花沢のハナノキ
南花沢から数百mの場所には「ハナノキ公園」があり、公園内には4本のハナノキがありました。
北花沢のハナノキも国指定の天然記念物となっており、国の天然記念物に指定されたハナノキの中で個体指定木3株の内の2株が南北花沢のハナノキだとされます。

北花沢のハナノキは幹周4.4m・樹高17mで樹齢300年以上とされているが、かつては2本の幹に分かれていたといい、1866年の暴風で1本が折れ、1950年のジェーン台風では倒れてしまったという。
その後、手厚い保護によって樹勢を回復してきているようですが、今の姿はかつての半分ほどの大きさだとされています。

ハナノキの下には石仏や五輪塔が祀られ、地域の祈りの場としても祀られているようです。
ただし、この公園は国道沿いの場所にあって環境が良いとは思えず、車の騒音以外に聞こえてくるのは向かいのガソリンスタンドの人の高らかな声だけ。


別角度からハナノキを見てみる。
ハナノキは、おもに木曽川流域の湿地周辺に自生する樹とされていますので、いつの時代かにこの地に移植されたものと考えられているといいます。

さほど広くはない公園ですが、公園内には御神木のハナノキを含めて4本のハナノキが植えられ、それぞれ樹齢の差はあれど、次世代への引継ぎが行われています。
こういう尽力によって花沢のハナノキは歴史を伝えていくのでしょう。