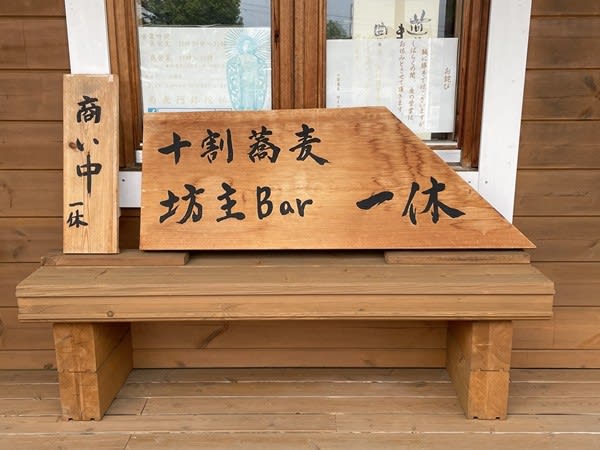秋の虫の声が聞こえてくるようになっても残暑・猛暑日が続いておりますが、秋分の日を過ぎて少しおさまってきたのでしょうか。
秋の虫の声が聞こえてくるようになっても残暑・猛暑日が続いておりますが、秋分の日を過ぎて少しおさまってきたのでしょうか。暑い!暑い!とは言っていても不思議なもので秋の彼岸の時期になると決まっていたかのように彼岸花が開花し始めます。
今はまだ、彼岸花の群生地が真っ赤な花色に染まるとまではいかないものの、川の堤防や林の中にパラパラと彼岸花が咲いています。
彼岸花が満開になればアゲハ蝶の仲間も吸蜜にやってくると思いますが、それはもう少し先のことになりそうです。

雨の秋分の日を過ぎたら急に涼しさを感じるようになりましたので、琵琶湖岸の東屋でゆっくりとした時間を過ごしながらランチとしました。
琵琶湖は場所によっては藻だらけの場所がありますが、藻がほとんどない浜では水が透き通って見える綺麗さで琵琶湖の美しさに見惚れてしまいます。

食後に岸辺に自生している季節の花を探してみると、まずは岸辺や山側に凄い勢いで自生しているセンニンソウが目に付きます。
センニンソウはつる性の多年草で、和名は痩果に付く綿毛を仙人の髭に見たてたことに由来するといいます。
見かけは花の白さが涼し気な花ですが、有毒植物で「ウマクワズ(馬食わず)」なんていう有り難くない別名があるそうです。

イタドリも小さな花を沢山つけており、若芽は食用になるとされ、傷薬として若葉を揉んでつけると血が止まって痛みを和らげるのに役立つそうです。
そんな紅葉から和名が「痛取(イタドリ)」となっているといい、時々見かけているはずなのに普段は素通りしている花のひとつかと思います。

ゲンノショウコはドクダミなどと共に古くから日本で用いられてきた薬草とされ、江戸時代の初め頃から薬草として使われてきたという。
地上部を乾燥させたものを服用するとすぐに効き目が現れることから「現之証拠(ゲンノショウコ)」という名が付いたそうですね。
数頭のシジミチョウの仲間がゲンノショウコに留まって吸蜜していましたよ。


花の名は全部グーグルレンズで検索したので間違っているかもしれませんが、最後は一輪だけ咲いていたタマスダレの花。
タマスダレの原産地はブラジルで明治初期に渡来して半野生化したヒガンバナ科の球根植物だそうです。

木の葉にはアサマイチモンジが留まっています。
イチモンジチョウとアサマイチモンジはよく似ているので白斑で見分けるのだそうです。
同じような茶黒系の色合いのコミスジ・ミスジチョウ・ホシミスジも写真に撮らないと間違ってしまうかもしれませんね。

蝶の季節はあと僅か。秋の渡りのアサギマダラに会えたら今年の蝶は終わりかな?
彼岸花が咲きましたのでこれから一気に秋モードになるのかと思いますが、実感出来るのはこれからかでしょうね。