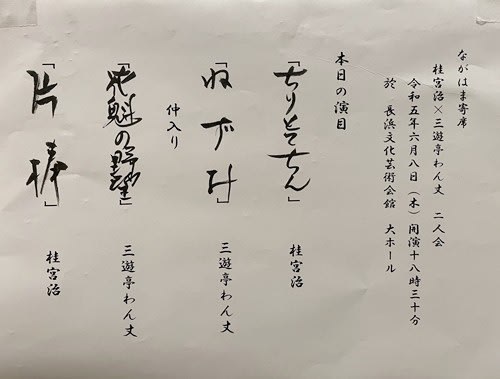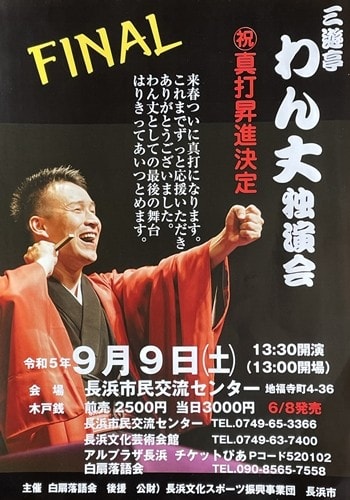「赤坂山(標高823.8m)」の山頂に到着後、前回登山時に断念して今回の登山の目的であった「明王の禿」へと向かいました。
「赤坂山(標高823.8m)」の山頂に到着後、前回登山時に断念して今回の登山の目的であった「明王の禿」へと向かいました。「明王の禿」は花崗岩が風化して出来たとされる荒涼たる奇観の崖で、ザレた砂地に巨大な花崗岩が風化しつつも聳えている。
花崗岩は地表深くで固まったマグマが冷えて固まったものとされますが、「明王の禿」の辺りだけに風化した花崗岩が見られるのは、過去に大崩落があったからなのでしょうか?
登山道に石英のような石が所々で見られたのは、マグマの石英成分が冷えて固まり石英の部分だけが風化に耐えて残ったものというのもこの山の地質の特徴のようです。

「赤坂山」と谷を挟んで向こうに見えるのは「三国山」で、山の右方向に「明王の禿」が見えますが、赤坂山からは激下りと急登の登り返しで行って、同じ工程を帰らなければならない。
しかも激下りをして歩く道は、マキノ高原から赤坂山の登山道に比べてひとけがなく、クマでも出そうな道を歩くことになります。

下りの道中に見えていた「明王の禿」は激坂を下りきって樹林帯を歩くようになると、樹木に隠れて一旦見えなくなります。
三国山が近くなって急登を登り始めると再び「明王の禿」が見えてきますが、急登のしんどさより何か危ないやつに出会ってしまわないかの方が気になる。

そして「明王の禿」を目の前にできる場所に辿り着きます。
“あなたはザレ場や巨石群がホントに好きやね。”と言われそうですが、この圧倒的な迫力の光景を目の前にしたら声も出ない。もしくは感嘆の大声をあげたくなる。

自然の造形美ということになりますが、雪が多く風雨にさらされる場所ですから刻々と姿を変えているのではないでしょうか。
立入禁止等の措置はされていますが、うっかり足を踏み入れたら奈落の底へ真っ逆さまに落ちて、サヨウナラとなりますね。

真ん中辺りに聳える巨石はモアイ像のような姿をしています。
誰が名付けたのか知りませんが、姿はまさにモアイ像。一般的にも「明王の禿のモアイ像」で通じるようです。

こちら側は侵入禁止となっていますが、入れば急降下で落下しそうなので禁止しなくても入りませんよ。
入っていってズルっといったらウォータースライダーならぬサンド・スライダーであの世行き!

この崖を少し高い場所から眺めると、奥に琵琶湖が見えます。
大勢の人が集まるキャンプ場から2時間ほどでこの光景に出会えるのですから、この山は魅力的な山です。

冬近くで積雪のない空気が澄み切った頃に来れば、琵琶湖や日本海が綺麗に見えるのかと想像しますが、秋に登るなら赤坂山~寒風コースかなと先の話を考える。
「明王の禿」から戻る時に樹林帯で会った人と下山して車で移動していた時に、白谷集落の辺りで会いましたので黒河峠から下山されたようで、そのコースも面白そうです。

では赤坂山に戻りますが、結構遠く感じますね。
途中からは急登続きですし、赤坂山の山頂に見える人影のなんとも小さい事!

ここから最後の急登の登り返しとなりますが、正面に見える大きな岩の裏側が山頂です。
歩き切った感を感じつつも、赤坂山の山頂からマキノ高原までは2時間程度かかりますので、もうひと踏ん張りしないといけません。

下山道はさほど変化のある道ではありませんので花を探しながら下りていきます。
登山道で出会った方が“今の季節の赤坂山はドウダンツツジを観ないと駄目よ。”と教えてもらい、サラサドウダンと思われる花の下で臨時の撮影会です。
赤坂山に咲く「サラサドウダン」という花のサラサの名称は、「マキノ温泉サラサ」の命名の由来となっているそうで、この花はサラサかベニか素人には悩ましい花です。
「サラサドウダン」は黒河峠からのルートの方が出会える確率が高いようですが、黒河峠はクマさんに出会ってしまう確率が高くなるとか、ならないとか...。

花を教えてもらった方と話していたのは“イワカガミの群生の多さ”です。
もちろん花期は既に終わってしまっていますが、艶々した葉っぱの多さに驚きますし、花期に訪れたら辺り一面がピンク色に染まりそうな群生の大きさでした。

登山道脇の谷側に背の高い樹木があって蓮のような大きな花の木があった。
ホオノキというモクレン科の植物のようだが、山の中に咲く蓮の花を見たような錯覚に陥るような花でした。

花はヤマボウシやコアジサイ、名前は分からないけど小さく黄色い小花を咲かした花などが見られる。
下はタンナサワフタギでしょうか。花に詳しい人ならもっとたくさんの花が見つけられると思います。

満開のエゴノキは場所によって花が地面に落ちているところもありました。
花にはおおよその花期がありますが、同じ山でも生えている場所の環境によって開花期の早い遅いがあるようです。

登山道の脇にはタニウツギの花が満開の季節を迎えていました。
昔、夏に飛来する野鳥を探しに何度も訪れていた山では、タニウツギの花の開花状況で野鳥の出を推測したりしていたので馴染みのある花です。

1年前に赤坂山に登った時は、最後の木段で足がヘタってしまってヨタヨタと下りてきましたが、今回は足は大丈夫でした。
登山口まで帰ってきてキャンプサイトに下りてくると、朝よりもテントの数が増えています。
「マキノ高原管理事務所」の前にも申し込みの長蛇の列が出来ており、夜はテントが密集しそうな勢いでもありました。

売店の「さらさ庵」で「赤坂山の自然ガイドブック」を購入。
花ならGW前に一度訪れてみたくなりますし、黒河峠からのルートの方は花は多そうなのでそちらから登る手もありそうです。
また、マキノ高原から赤坂山~寒風の周回ルートも稜線歩きが気持ち良さそうですので、この先も登りにきたくなる山です。