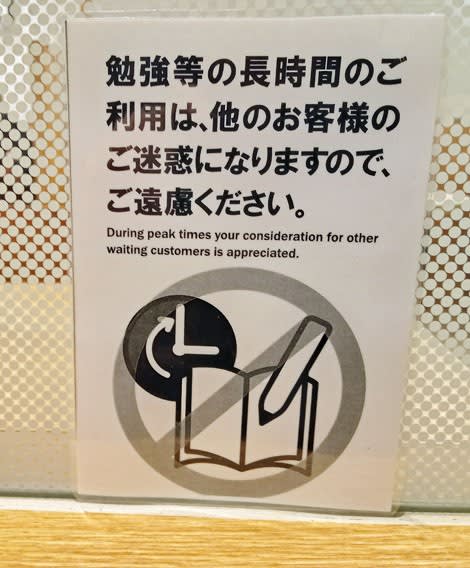柚月裕子著『チョウセンアサガオの咲く夏』(2022年4月6日KADOKAWA発行)を読んだ。
「佐方貞人」シリーズ、「孤狼の血」シリーズや、『盤上の向日葵』『慈雨』など数々のベストセラーで知られる柚月裕子。各種メディアへ発表した13年間の短編11編を集めた初のオムニバス短編集。
「チョウセンアサガオの咲く夏」
40歳過ぎの三津子は、認知症で寝たきりになった72歳になる母の芳枝を介護していた。もっぱら母を介護するだけの日々を送っていた三津子は、母の具合が悪くなると、かかりつけ医の平山がやってきて三津子を褒めたたえる。いつのまにか、賛辞が欲しくて、母の体調が悪くなることを……。
思い返すと、子供の頃、三津子はよく事故にあって、母が抱きかかえて平山のもと駆けつけて来ていた。(代理ミュンヒハウゼン症候群)
「泣き虫(みす)の鈴」
12歳の八彦は豪農で16人の奉公人がいる本多家で奉公している。いつも年長の正造にいじめられて、隠れて泣いていて、そんなときは母から唯一もらった鈴を鳴らして慰めていた。
ある日、旅の女芸人で目が不自由な瞽女(ごぜ)がやって来た。母親位の親方のハツエと、わずかに目が見えるトヨと10歳のキクだ。夜中、正造たちが3人の女をおそい、気づいた八彦は…。
「でも、どうしても泣きたくなったらこの鈴さならせ。おめえの代わりに泣いてくれる」
「サクラ・サクラ」
浩之は勤めている会社が外国企業に買収され、外国人上司に事あるごとに無能呼ばわりされ、自信を失っていた。休暇をとっていたパラオ共和国のペリリュー島には「ペリリュー神社」と日本語で書かれた鳥居と祠(ほこら)があり、現地の老人が、さくらの歌を歌っていた。
第一次大戦後、パラオは日本の委任統治領になっていたが、太平洋戦争がはじまると、重要拠点となり日本は統治に力を入れた。米軍が上陸する二日前、島民代表は日本軍に加わりたいと申し出た。日本軍守備隊長は……。その後、司令部から本土に「サクラサクラ」の暗号電文が送信された。
「お薬増やしておきますね」 精神科医の杉山鈴子はすっかり医師気取りの患者と話を交わす。
「初孫」「原稿取り」「愛しのルナ」 略
「泣く猫」
真紀は警察から連絡を受けて17年も会っていない母・紀代子の住んでいたアパートに向かった。母は20歳で真紀を生み、55歳で死んだ。男ができると娘を捨てて、男と別れると児童養護施設に娘を引取りに来た。
香典を持って訪れてきた店で一緒だったというサオリが「弔問客なんて来ないだろう」、「あっ、大切なお客さんがいることを忘れていた。ごめんね」と言う。猫だった。泣き続ける猫。サオリは「あんなに可愛がられたマキが泣くのは当然でしょう」と言った。
「影にそう」「黙れおそ松」 略
「ヒーロー」 シリーズの主人公・佐方検事の事務官・増田の高校の柔道部の親友の話
私の評価としては、★★★☆☆(三つ星:お好みで、最大は五つ星)
柚月裕子ファンなら、初めての短編集は読まざると得ないだろう。
しかし、冷静に見ると、平均的でごく普通の短編集だ。
「泣き虫の鈴」「サクラ・サクラ」が泣かせるが、あざとい技が気になる短編もある。
「初孫」「原稿取り」のようにどこかで読んだような話もある。「黙れおそ松」のようにふざけすぎの話もある。
ちなみに、チョウセンアサガオ(別名エンジェル・トランペット)は我がブログにも7回ほど登場した。
本書の表紙にもあるが、こんな花だ。
2009年11月

2021年9月