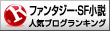なんかふいに衝動的にいきなり突然観たくなって、密林通販にてDVD購入。1967年テレビ特撮作品の方であって、1987年アニメ版でも典型的な原作無視の2001年劇場版でもないです。
なんかふいに衝動的にいきなり突然観たくなって、密林通販にてDVD購入。1967年テレビ特撮作品の方であって、1987年アニメ版でも典型的な原作無視の2001年劇場版でもないです。1966年映画「大忍術映画ワタリ」でワタリを演じた金子吉延と爺役の牧冬吉を青影と白影に迎え、主役の赤影には坂口祐三郎を配しての冒険活劇。坂口は赤影のインパクトが大きすぎて役者として迷走することになりますが、金子と牧のコンビはこのあと1968年の「河童の三平 妖怪大作戦」にも引き継がれることになります。
戦国時代も末期、海を渡って来た奇怪な妖術者の群れがギヤマンの鐘を求めて各地を襲撃し始めた。次々に沈められるポルトガル船。
世界を制覇を狙う卍党の仕業である。
サタン、デウス、マリアの3つの鐘には、強烈なエネルギー製法の手がかりが秘められているという。
日本の平和を願う織田信長は、卍党の野望を粉砕すべく、飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。
「赤影参上!!」
もともと「忍者」というのはRPGと親和性があって、普通に職業クラスに混ざっていたりするのだけれど、これがリアル方向に振れると「諜報や破壊工作に特化した白兵戦の専門家」と解釈されますが、ファンタジー方向に振れると講談的に「奇怪な妖術を使う、白兵戦もできる魔法使い」扱いに。
この『仮面の忍者赤影』も、原作コミックは普通に忍者が活躍する冒険活劇でややリアル寄りだったのに、特撮版の第一部「金目教篇」はファンタジー方向に流れて、巨大ガマや人形を操ったり、長い髪を振り回して嵐を起こしたり、巨漢が二次元化したりとまさにファンタジー。ところが第二部「卍党篇」になると横軸がファンタジーに振り切れたまま、今度は縦軸がSF方向に跳ね上がったのですね。
もともと第一部でも金目像、巨大コマとカラクリ仕掛けのスチームパンク的な要素もちらほらあったわけですが、第二部となると完全にスタッフが自重しなくなります。
「ギヤマンの鐘」こそ典型的なマクガフィン(話を進めるためだけに用意されるアイテム)なのですが、それよりも海から出現し、空を飛ぶ巨大円盤「大まんじ」がなによりインパクトがあります。小道具にしてもリボルバー銃、緊急サイレン、アクアラング、ウォータージェット、空対空ミサイル、光線砲台と大道具、小道具も「どこが戦国時代?」というものが増えてきます。大凧と傘の空中戦ってのもありました。
そして、なによりも敵忍者集団である卍党。
「海を渡って来た奇怪な妖術者の群れ」といいつつ、その正体は甲賀幻妖斎が率いる甲賀忍者うつぼ忍群。主人公が赤影、青影、白影という3種のシンボルカラーのヒーローということで戦隊物の原点とみなされることもありますが、主人公に敵対する卍党こそ、赤・青・白・緑……と、それぞれのシンボルカラーに彩られたウェットスーツを思わせる全身一体型スーツを身につけ、顔はマスク、そしてマントと、まさに戦隊ヒーローの原点なのです。
そして第三部、第四部となると今度は妖怪・怪獣色が強くなるわけですが……今、観ても思い出補正抜きで面白いね。
【仮面の忍者赤影】【第二部 卍党篇】【フジテレビ系】【東映ビデオ】【坂口祐三郎】【金子吉延】【牧冬吉】【天津敏】【大泉滉】【里見浩太朗】【海底都市】