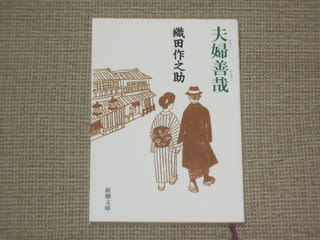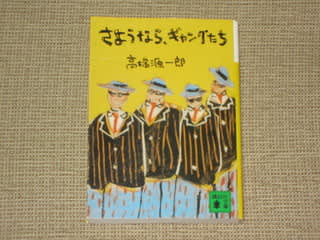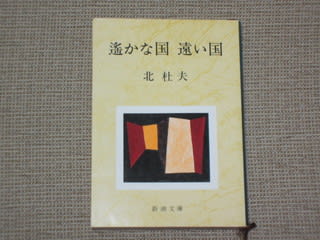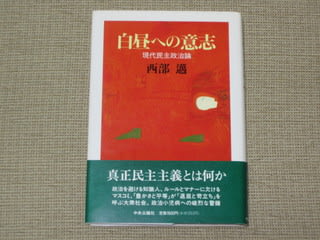織田作之助 昭和25年発行・平成25年改版 新潮文庫版
高橋源一郎の『競馬探偵の憂鬱な月曜日』をこないだ読み返したとき、1990年1月のところに、
>なんで、きみたちは勝っても負けてもそんなに明るいの? 大敗したらお先真っ暗になるのが競馬の礼儀というものです。今年はその辺の競馬道についても考えていきたいと思っております。まだ、読んでない若者は織田作之助の「競馬」でも読んでね、泣いちゃうから。
とあって、とても気になったもんだから、私は若者ではないけど、読んでみようと思った。
私は織田作之助自体一篇も読んだことなかったんで、こういう代表作収めてる文庫本があってよかった。
読んだのはことし3月くらいだけど、仕事で大阪へ行ったりしてるときに、こういうの読めたのはちょっとおもしろかった。
「夫婦善哉」は、芸者の蝶子と、もとは妻子がいたのに蝶子と一緒になって実家からは勘当された柳吉の、ふたりの話、時代は関東大震災のころ。
ふたりでいろんな商売をやるんだが、最初のうちはうまくいきそうなんだけど、そのうち散財したりとかで長続きしない、やがてまた別の商売で立ち直ろうとする、繰り返し。
しょうもない男の生き様が反省しない感じで淡々と書かれてんだが、とにかく文章のリズムがよくて読ませられちゃう。
たとえばー、最初のほうのシーンで、
>(略)本真にうまいもん食いたかったら、「一ぺん俺の後へ随いて……」行くと、無論一流の店へははいらず、よくて高津の湯豆腐屋、下は夜店のドテ焼、粕饅頭から、戎橋筋そごう横「しる市」のどじょう汁と皮鯨汁、道頓堀相合橋東詰「出雲屋」のまむし、日本橋「たこ梅」のたこ、法善寺境内「正弁丹吾亭」の関東煮、千日前常盤座横「寿司捨」の鉄火巻と鯛の皮の酢味噌、その向い「だるまや」のかやく飯と粕じるなどで、何れも銭のかからぬいわば下手もの料理ばかりであった。(略)
なんてとこがあって、江戸の落語とはまた違うけど、トントントンと進んでいく。
全編こんな感じっていえばこんな感じ、私にとっては初めて読んだ感覚。
くだんの「競馬」は、1の番号の馬ばかり買い続ける男の話。
1を買うのは、亡くなった細君の名が一代というからってとこからきてんだが、そこには複雑な感情が入ってる。
「夫婦善哉」
「木の都」
「六白金星」
「アド・バルーン」
「世相」
「競馬」
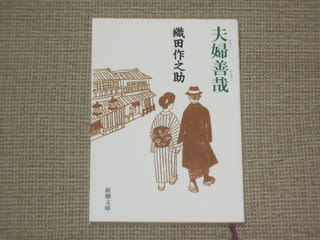
高橋源一郎の『競馬探偵の憂鬱な月曜日』をこないだ読み返したとき、1990年1月のところに、
>なんで、きみたちは勝っても負けてもそんなに明るいの? 大敗したらお先真っ暗になるのが競馬の礼儀というものです。今年はその辺の競馬道についても考えていきたいと思っております。まだ、読んでない若者は織田作之助の「競馬」でも読んでね、泣いちゃうから。
とあって、とても気になったもんだから、私は若者ではないけど、読んでみようと思った。
私は織田作之助自体一篇も読んだことなかったんで、こういう代表作収めてる文庫本があってよかった。
読んだのはことし3月くらいだけど、仕事で大阪へ行ったりしてるときに、こういうの読めたのはちょっとおもしろかった。
「夫婦善哉」は、芸者の蝶子と、もとは妻子がいたのに蝶子と一緒になって実家からは勘当された柳吉の、ふたりの話、時代は関東大震災のころ。
ふたりでいろんな商売をやるんだが、最初のうちはうまくいきそうなんだけど、そのうち散財したりとかで長続きしない、やがてまた別の商売で立ち直ろうとする、繰り返し。
しょうもない男の生き様が反省しない感じで淡々と書かれてんだが、とにかく文章のリズムがよくて読ませられちゃう。
たとえばー、最初のほうのシーンで、
>(略)本真にうまいもん食いたかったら、「一ぺん俺の後へ随いて……」行くと、無論一流の店へははいらず、よくて高津の湯豆腐屋、下は夜店のドテ焼、粕饅頭から、戎橋筋そごう横「しる市」のどじょう汁と皮鯨汁、道頓堀相合橋東詰「出雲屋」のまむし、日本橋「たこ梅」のたこ、法善寺境内「正弁丹吾亭」の関東煮、千日前常盤座横「寿司捨」の鉄火巻と鯛の皮の酢味噌、その向い「だるまや」のかやく飯と粕じるなどで、何れも銭のかからぬいわば下手もの料理ばかりであった。(略)
なんてとこがあって、江戸の落語とはまた違うけど、トントントンと進んでいく。
全編こんな感じっていえばこんな感じ、私にとっては初めて読んだ感覚。
くだんの「競馬」は、1の番号の馬ばかり買い続ける男の話。
1を買うのは、亡くなった細君の名が一代というからってとこからきてんだが、そこには複雑な感情が入ってる。
「夫婦善哉」
「木の都」
「六白金星」
「アド・バルーン」
「世相」
「競馬」