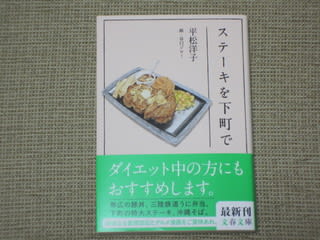星新一 昭和57年 新潮文庫版 全3冊
前回の北杜夫の文庫の解説が星新一だったので、そのつながりで。
星新一の文庫はいくつか持ってたはずなんだけど、探してもこれしか見つからなかった、どこやっちゃったのか。
で、この全3巻は、いつものショートショートぢゃなくて、エッセイのようなもの。
といっても自分で文章書くだけぢゃなくて、アメリカのヒトコマ漫画のコレクションを分類して解説している。(マンガがテーマだから私は読もうと思ったのかもしれない。)
単行本の発行は昭和43年、雑誌連載(エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン)の開始は昭和40年だというから、かなり古い。
著者のそもそものヒトコマ漫画の収集は、孤島物から始まったらしいが、そもそも雑誌などで見かける数からして他のジャンルと比べて圧倒的に多いそうで、当時すでに約三千種を収集しているが、著者の想像するには四万種は存在するだろうと言っている。
ちなみに、次に多いのは、妻と浮気相手がベッドにいるところに夫が帰ってきた構図、情事発覚漫画というものらしい。
基本的には、マンガの話なので、全編気楽な感じで読めるんだけど、ときどき著者のこだわりがみえて、それはそれでおもしろかったりする。
>マニアという患者は自分勝手な定義を作りあげ、それを他人に押しつけて喜ぶ症状を呈するもので、私はいつも苦々しく思っているのだが、自分がその立場になると、同じことをやってしまう。(1巻p.22)
とか。
まじめな研究者(?)の一面もみせてくれて、
>アメリカのヒトコマ漫画の特徴は、画中の人物のだれかが、だれかにむかって、なにかをしゃべっているという点にある。(3巻p.2323)
として、誰が誰に発言しているかという外見で、先にあげた情事発覚漫画は分類できるとしている。
ちなみに、このアメリカ漫画の特徴については、
>(略)時には、なくてもいいような傍観者的な人物を描きそえ、そいつにわざわざしゃべらせたりしている。どの漫画もこの原則に忠実。りちぎと称したくなるほどだ。つまり、絵のなかに口をあけた人物が一人、かならず存在しなければならぬのである。(略)発言には責任がともなうという社会慣習のせいであろうか。(略)(2巻p.132-134)
と別のところでも解説してくれている。
さて、文庫3冊分、基本見開きの右1ページが文章左1ページが漫画、ってつくりの本なので、掲載されてる漫画の数はいーっぱいあって、どれがいいと簡単にはランクづけとかできないんだけど、今回読み返したなかで私がいいと思ったのは、天国漫画のひとつ。
(天国漫画ってのは、雲の上で、頭の上に輪っかがあって、背中に羽が生えてて、白い服を着た住人が、たいがい退屈そうに何か言ってるってジャンルなんだけど。)
地球を遠く見下ろす雲の上で頭に光輪のある二人のうちの一人が「地上でなにかあったらしい、あっというまに数十億人がやってきたと思ったら、あとはひとりもやってこない。」って言ってるやつ。
もうひとつは残念ながら画が載ってないんだけど、ネームだけ文章で紹介してあるやつで、求職にやってきた者に応対してる人事担当係というジャンルで、そのセリフが「わが社の雇用契約にある〈若いうちに楽しめコース〉というのをやってみませんか。三十歳から三十五歳まで有給休暇。あとは休みなく死ぬまで働くというしかけです」ってえの。
ちなみに、著者は自身の仕事について、
>机の原稿用紙にむかい一時間もすると、私はのどから胃にかけて、不快感におそわれはじめる。時には痛んだりする。(略)執筆が苦痛なのは、作家だれしも同じではないだろうか。朝は早くしぜんに目がさめ、筆をすすめながら笑いがこみあげ、思わず口笛でマーチを吹いてしまうなどといった作家は、あまりいないはずである。いやいや書くからこそ執筆なのだ。おもしろくてたまらなければ、それは遊興である。(2巻p.214)
と言っているけど、そんな苦しんでも、あんな軽やかで楽しいものが書けてしまうのだから、たいしたもんだと思う。

前回の北杜夫の文庫の解説が星新一だったので、そのつながりで。
星新一の文庫はいくつか持ってたはずなんだけど、探してもこれしか見つからなかった、どこやっちゃったのか。
で、この全3巻は、いつものショートショートぢゃなくて、エッセイのようなもの。
といっても自分で文章書くだけぢゃなくて、アメリカのヒトコマ漫画のコレクションを分類して解説している。(マンガがテーマだから私は読もうと思ったのかもしれない。)
単行本の発行は昭和43年、雑誌連載(エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン)の開始は昭和40年だというから、かなり古い。
著者のそもそものヒトコマ漫画の収集は、孤島物から始まったらしいが、そもそも雑誌などで見かける数からして他のジャンルと比べて圧倒的に多いそうで、当時すでに約三千種を収集しているが、著者の想像するには四万種は存在するだろうと言っている。
ちなみに、次に多いのは、妻と浮気相手がベッドにいるところに夫が帰ってきた構図、情事発覚漫画というものらしい。
基本的には、マンガの話なので、全編気楽な感じで読めるんだけど、ときどき著者のこだわりがみえて、それはそれでおもしろかったりする。
>マニアという患者は自分勝手な定義を作りあげ、それを他人に押しつけて喜ぶ症状を呈するもので、私はいつも苦々しく思っているのだが、自分がその立場になると、同じことをやってしまう。(1巻p.22)
とか。
まじめな研究者(?)の一面もみせてくれて、
>アメリカのヒトコマ漫画の特徴は、画中の人物のだれかが、だれかにむかって、なにかをしゃべっているという点にある。(3巻p.2323)
として、誰が誰に発言しているかという外見で、先にあげた情事発覚漫画は分類できるとしている。
ちなみに、このアメリカ漫画の特徴については、
>(略)時には、なくてもいいような傍観者的な人物を描きそえ、そいつにわざわざしゃべらせたりしている。どの漫画もこの原則に忠実。りちぎと称したくなるほどだ。つまり、絵のなかに口をあけた人物が一人、かならず存在しなければならぬのである。(略)発言には責任がともなうという社会慣習のせいであろうか。(略)(2巻p.132-134)
と別のところでも解説してくれている。
さて、文庫3冊分、基本見開きの右1ページが文章左1ページが漫画、ってつくりの本なので、掲載されてる漫画の数はいーっぱいあって、どれがいいと簡単にはランクづけとかできないんだけど、今回読み返したなかで私がいいと思ったのは、天国漫画のひとつ。
(天国漫画ってのは、雲の上で、頭の上に輪っかがあって、背中に羽が生えてて、白い服を着た住人が、たいがい退屈そうに何か言ってるってジャンルなんだけど。)
地球を遠く見下ろす雲の上で頭に光輪のある二人のうちの一人が「地上でなにかあったらしい、あっというまに数十億人がやってきたと思ったら、あとはひとりもやってこない。」って言ってるやつ。
もうひとつは残念ながら画が載ってないんだけど、ネームだけ文章で紹介してあるやつで、求職にやってきた者に応対してる人事担当係というジャンルで、そのセリフが「わが社の雇用契約にある〈若いうちに楽しめコース〉というのをやってみませんか。三十歳から三十五歳まで有給休暇。あとは休みなく死ぬまで働くというしかけです」ってえの。
ちなみに、著者は自身の仕事について、
>机の原稿用紙にむかい一時間もすると、私はのどから胃にかけて、不快感におそわれはじめる。時には痛んだりする。(略)執筆が苦痛なのは、作家だれしも同じではないだろうか。朝は早くしぜんに目がさめ、筆をすすめながら笑いがこみあげ、思わず口笛でマーチを吹いてしまうなどといった作家は、あまりいないはずである。いやいや書くからこそ執筆なのだ。おもしろくてたまらなければ、それは遊興である。(2巻p.214)
と言っているけど、そんな苦しんでも、あんな軽やかで楽しいものが書けてしまうのだから、たいしたもんだと思う。