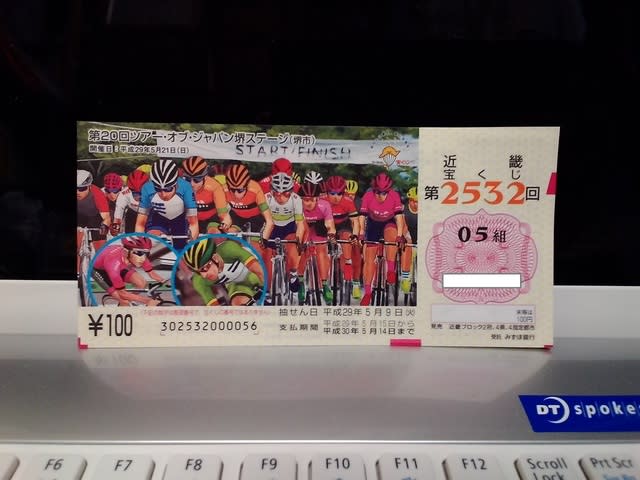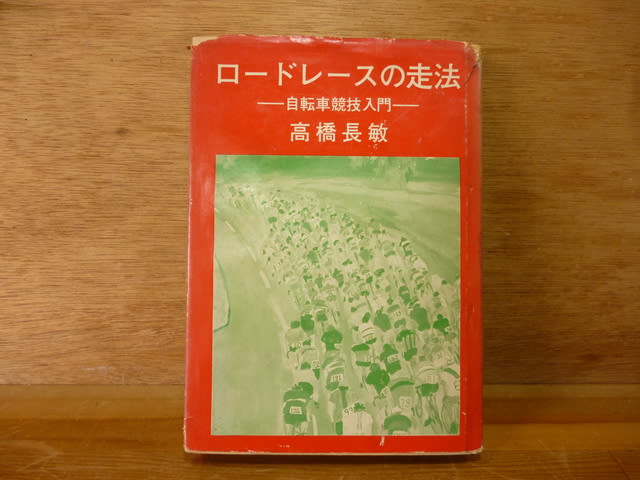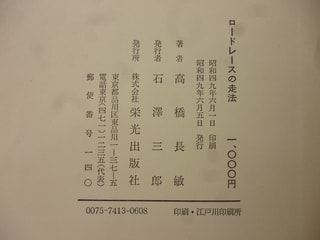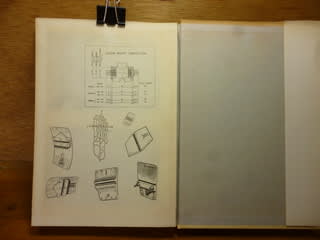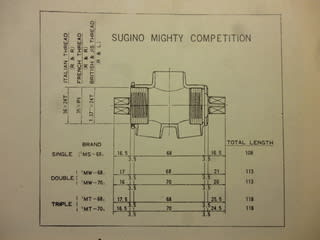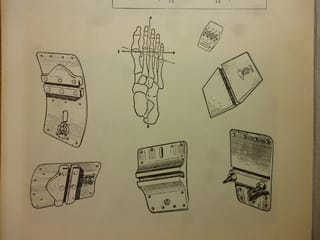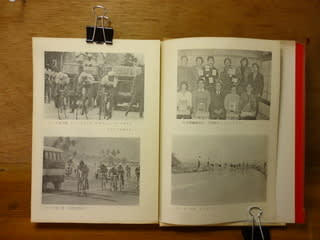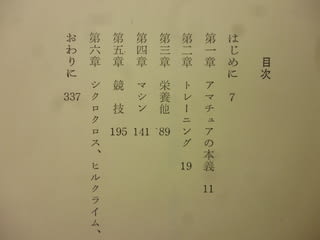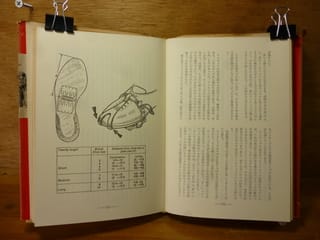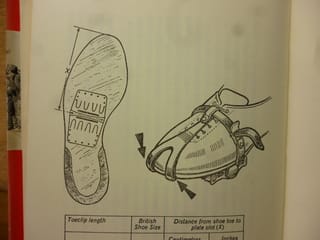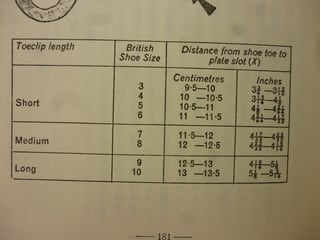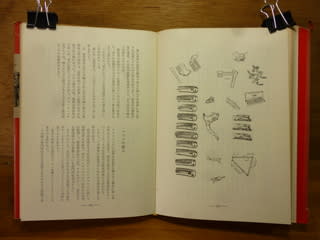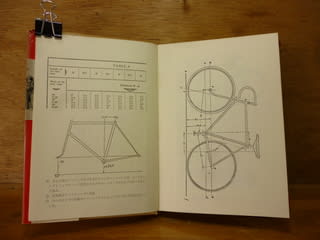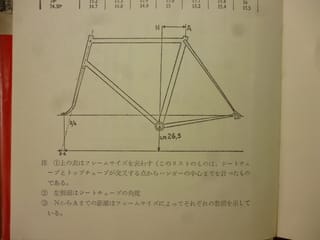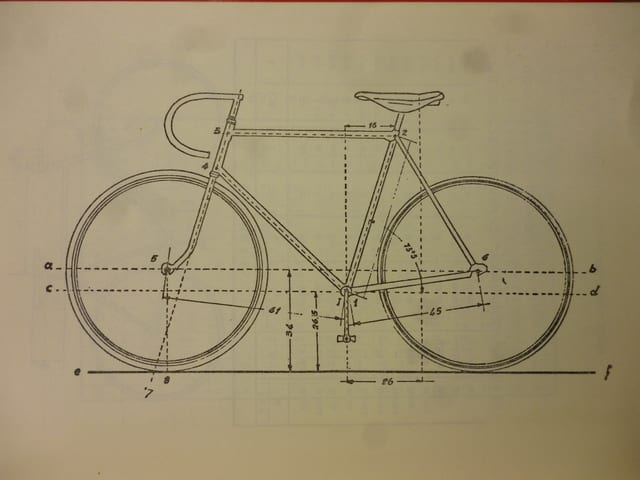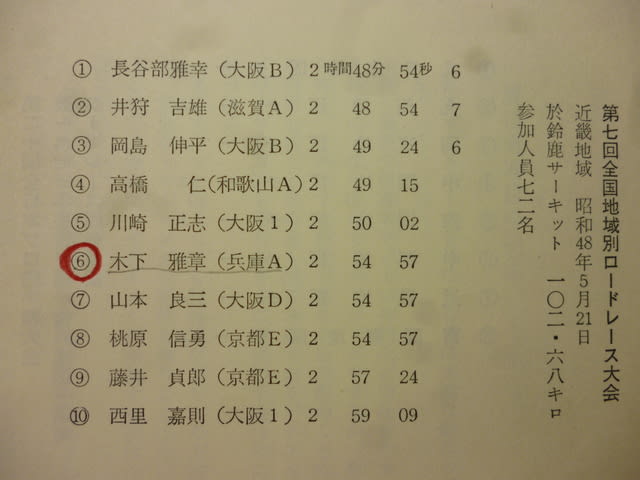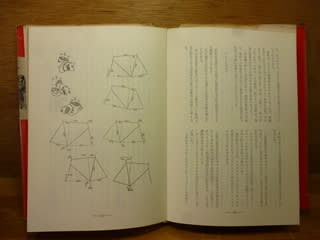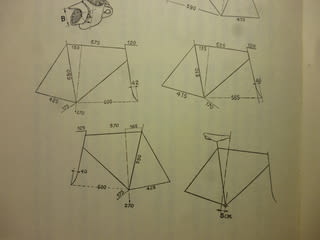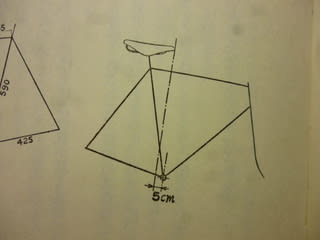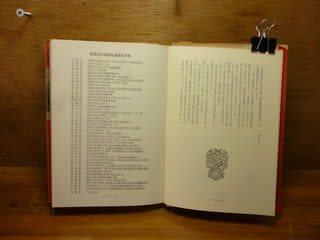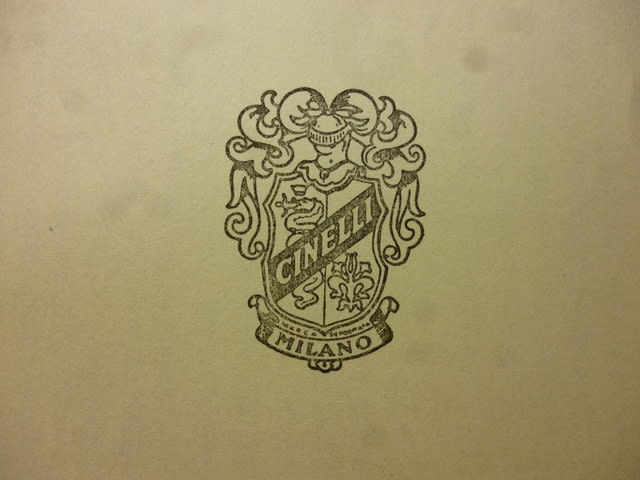木製の自転車用スタンドは何度かご紹介しましたがその作り方を改めて
ご紹介させて頂きます 自転車とホイールスタンドにも使える便利なスタンドです

自転車を自立させる木製スタンドですが 今迄にも何度か記事にしています
今回は誰でもが作れるように書き進めて行きたいと思います
使う材料はコンパネ 12mm 大きさは最小 550×220mm の物1枚
角材 35mm 長さは最低 1150mmを 1本ご用意下さい
この写真はコンパネを切る為に線を引いています(建築では墨付けと言います)


完成形はこの様になります 自転車の後輪を挟み
自立させています

またこの様にホイール立てにも使えるので便利です


墨付けしたコンパネを切ります サイズは
底辺 270mm 上辺 200mm 高さ 220mm の等脚台形です


台形の上辺の右側の一部を切り落します
横方向 50mm 縦 40mm の寸法です

切り出したコンパネです


コンパネの切り口はノコの返りで荒れています


切り口や表面を空研ぎ用のペーパーで研磨します
ペーパーは何でも良いですが このペーパーは
目詰まりがし難く木工には向いています
番手は 240番位で良いと思います

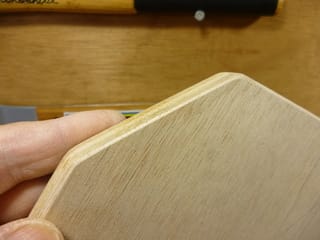
面取りが終わりました 角を取る事で手触りだけでは無く
そこから木が割れたり欠けたりする事も防ぎます

ペーパーは小さな木片を用意しそれに巻き付けて
使うと使い易いです
今回はコンパネの表面にもペーパーを掛けています
これは仕上がりを綺麗にしたければすれば良いと思います


最終的には全体を塗装しますが 完成後内側になる
片面だけ先に色を塗ります 塗りたくない部分には
マスキングテープで養生します


塗料は何を使っても良いです 今回はオレンジのスプレーを
選びました 刷毛塗りでも OK 油性、水性どちらを選んでも
問題ありません


塗装の仕方は何度かに別けて塗り重ねて行きます
木材は金属と違い塗料が浸み込みます


乾燥させてから一度ペーパーで表面を均して
再度スプレーすると綺麗な塗装が出来ます


内側の塗装は木材の表面保護ですが この様なカーボン
ホイールに木材を直接触れさせたく無いと言う事も含んでいます

塗装が乾燥するまでに角材を切ります 今回は
35mm 角を使いますが 30mm 角でも大丈夫です

長さは 270mm 300mm それぞれ 2本づつ切りました


タイヤを置く部分を少し削ります


角材の角が直接タイヤに当るより この様にした方が
タイヤに優しいですよね


角材の面取りと全体をペーパーで滑らかに仕上げて
おきます


これで角材の準備は完了です


コンパネの塗装も乾燥しました



これからコンパネと角材を組立てます ビスの位置に
印をつけています 角材は 270mm の方です


お互いの接着に木工用ボンドを使います 木材同士には
かなりな強度が出ます はみ出すのが嫌なのでボンドを
均しています でもこのボンドは乾燥するまでなら
濡れた雑巾で拭けば綺麗に取れます


印をしていた所に木工用ビス 25~32mm を使い
固定して行きます 角材とコンパネの下面は揃えています



二組の部材を組立てました これをもう一つの角材
300mm をベースにしてスタンドを作ります

自宅近くで見掛けた可愛い花です 葉の緑に綺麗な白い色が良く栄えますね
木製の自転車スタンドを組立てる準備が出来ました 次は自転車に合せて組立てて行きます
次回もどうぞお付き合い下さい
次の工程 【 木製 自転車用スタンドの作り方 完成】
ご紹介させて頂きます 自転車とホイールスタンドにも使える便利なスタンドです

自転車を自立させる木製スタンドですが 今迄にも何度か記事にしています
今回は誰でもが作れるように書き進めて行きたいと思います
使う材料はコンパネ 12mm 大きさは最小 550×220mm の物1枚
角材 35mm 長さは最低 1150mmを 1本ご用意下さい
この写真はコンパネを切る為に線を引いています(建築では墨付けと言います)


完成形はこの様になります 自転車の後輪を挟み
自立させています

またこの様にホイール立てにも使えるので便利です


墨付けしたコンパネを切ります サイズは
底辺 270mm 上辺 200mm 高さ 220mm の等脚台形です


台形の上辺の右側の一部を切り落します
横方向 50mm 縦 40mm の寸法です

切り出したコンパネです


コンパネの切り口はノコの返りで荒れています


切り口や表面を空研ぎ用のペーパーで研磨します
ペーパーは何でも良いですが このペーパーは
目詰まりがし難く木工には向いています
番手は 240番位で良いと思います

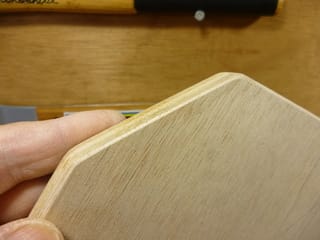
面取りが終わりました 角を取る事で手触りだけでは無く
そこから木が割れたり欠けたりする事も防ぎます

ペーパーは小さな木片を用意しそれに巻き付けて
使うと使い易いです
今回はコンパネの表面にもペーパーを掛けています
これは仕上がりを綺麗にしたければすれば良いと思います


最終的には全体を塗装しますが 完成後内側になる
片面だけ先に色を塗ります 塗りたくない部分には
マスキングテープで養生します


塗料は何を使っても良いです 今回はオレンジのスプレーを
選びました 刷毛塗りでも OK 油性、水性どちらを選んでも
問題ありません


塗装の仕方は何度かに別けて塗り重ねて行きます
木材は金属と違い塗料が浸み込みます


乾燥させてから一度ペーパーで表面を均して
再度スプレーすると綺麗な塗装が出来ます


内側の塗装は木材の表面保護ですが この様なカーボン
ホイールに木材を直接触れさせたく無いと言う事も含んでいます

塗装が乾燥するまでに角材を切ります 今回は
35mm 角を使いますが 30mm 角でも大丈夫です

長さは 270mm 300mm それぞれ 2本づつ切りました


タイヤを置く部分を少し削ります


角材の角が直接タイヤに当るより この様にした方が
タイヤに優しいですよね


角材の面取りと全体をペーパーで滑らかに仕上げて
おきます


これで角材の準備は完了です


コンパネの塗装も乾燥しました



これからコンパネと角材を組立てます ビスの位置に
印をつけています 角材は 270mm の方です


お互いの接着に木工用ボンドを使います 木材同士には
かなりな強度が出ます はみ出すのが嫌なのでボンドを
均しています でもこのボンドは乾燥するまでなら
濡れた雑巾で拭けば綺麗に取れます


印をしていた所に木工用ビス 25~32mm を使い
固定して行きます 角材とコンパネの下面は揃えています



二組の部材を組立てました これをもう一つの角材
300mm をベースにしてスタンドを作ります

自宅近くで見掛けた可愛い花です 葉の緑に綺麗な白い色が良く栄えますね
木製の自転車スタンドを組立てる準備が出来ました 次は自転車に合せて組立てて行きます
次回もどうぞお付き合い下さい
次の工程 【 木製 自転車用スタンドの作り方 完成】