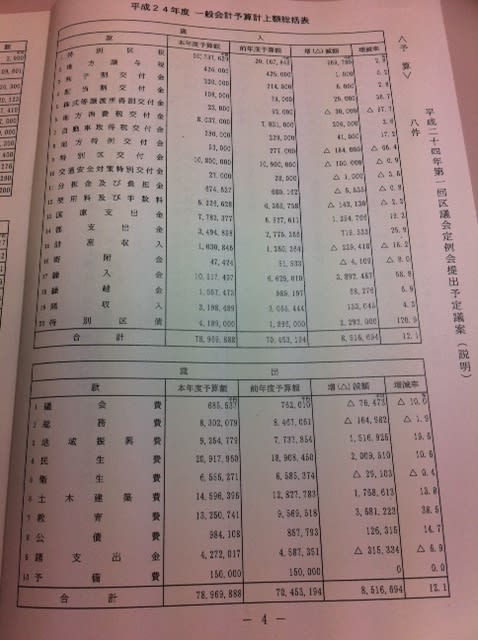渡辺謙氏のスピーチに私も感銘を受けます。
痛みを伴いますが、それを乗り越え、新しい日本を築かねばならないと思います。
渡辺氏は言います。
「「原子力」という、人間が最後までコントロールできない物質に頼って生きて行く恐怖を味わった今、再生エネルギーに大きく舵を取らなければ、子供たちに未来を手渡すことはかなわないと感じています。」
今しか、できないでしょう。
この機を逸すると、取り返しのつかない事態に日本は陥ってしまうかもしれないと危惧するところです。
*****東京新聞(2012/1/27)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/feature/news/davos.html
スイスで25日に開会した世界経済フォーラム年次総会「ダボス会議」で、俳優の渡辺謙さんがスピーチに立ち、各国から寄せられた東日本大震災の被災地支援への深い感謝と立ち上がる決意を語るとともに、原子力から再生エネルギーへの転換を訴えた。
渡辺さんは、震災発生直後から、インターネットにメッセージなどで被災者を応援するサイト「kizuna311」を立ち上げ、現地を幾度も訪れるなど、支援活動を積極的に続けている。
スピーチは現地時間25日午前(日本時間同日午後)に行われた。渡辺さんは「私たちの決意として、世界に届いてほしいと思います」と話している。
スピーチ全文は次の通り。
初めまして、俳優をしております渡辺謙と申します。
まず、昨年の大震災の折に、多くのサポート、メッセージをいただいたこと、本当にありがとうございます。皆さんからの力を私たちの勇気に変えて前に進んで行こうと思っています。
私はさまざまな作品の「役」を通して、これまでいろんな時代を生きて来ました。日本の1000年前の貴族、500年前の武将、そして数々の侍たち。さらには近代の軍人や一般の町人たちも。その時代にはその時代の価値観があり、人々の生き方も変化してきました。役を作るために日本の歴史を学ぶことで、さまざまなことを知りました。ただ、時にはインカ帝国の最後の皇帝アタワルパと言う役もありましたが…。
その中で、私がもっとも好きな時代が明治です。19世紀末の日本。そう、映画「ラストサムライ」の時代です。260年という長きにわたって国を閉じ、外国との接触を避けて来た日本が、国を開いたころの話です。そのころの日本は貧しかった。封建主義が人々を支配し、民主主義などというものは皆目存在しませんでした。人々は圧政や貧困に苦しみ生きていた。私は教科書でそう教わりました。
しかし、当時日本を訪れた外国の宣教師たちが書いた文章にはこう書いてあります。人々はすべからく貧しく、汚れた着物を着、家もみすぼらしい。しかし皆笑顔が絶えず、子供は楽しく走り回り、老人は皆に見守られながら暮らしている。世界中でこんなに幸福に満ちあふれた国は見たことがないと。
それから日本にはさまざまなことが起こりました。長い戦争の果てに、荒れ果てた焦土から新しい日本を築く時代に移りました。
私は「戦後はもう終わった」と叫ばれていたころ、1959年に農村で、教師の次男坊として産まれました。まだ蒸気機関車が走り、学校の後は山や川で遊ぶ暮らしでした。冬は雪に閉じ込められ、決して豊かな暮らしではなかった気がします。しかし私が俳優と言う仕事を始めたころから、今までの三十年あまり、社会は激変しました。携帯電話、インターネット、本当に子供のころのSF小説のような暮らしが当たり前のようにできるようになりました。物質的な豊かさは飽和状態になって来ました。文明は僕たちの想像をも超えてしまったのです。そして映画は飛び出すようにもなってしまったのです。
そんな時代に、私たちは大地震を経験したのです。それまで美しく多くの幸を恵んでくれた海は、多くの命を飲み込み、生活のすべてを流し去ってしまいました。電気は途絶え、携帯電話やインターネットもつながらず、人は行き場を失いました。そこに何が残っていたか。何も持たない人間でした。しかし人が人を救い、支え、寄り添う行為がありました。それはどんな世代や職業や地位の違いも必要なかったのです。それは私たちが持っていた「絆」という文化だったのです。
「絆」、漢字では半分の糸と書きます。半分の糸がどこかの誰かとつながっているという意味です。困っている人がいれば助ける。おなかがすいている人がいれば分け合う。人として当たり前の行為です。そこにはそれまでの歴史や国境すら存在しませんでした。多くの外国から支援者がやって来てくれました。絆は世界ともつながっていたのです。人と人が運命的で強く、でもさりげなくつながって行く「絆」は、すべてが流されてしまった荒野に残された光だったのです。
いま日本は、少しずつ震災や津波の傷を癒やし、その「絆」を頼りに前進しようともがいています。
国は栄えて行くべきだ、経済や文明は発展していくべきだ、人は進化して行くべきだ。私たちはそうして前へ前へ進み、上を見上げて来ました。しかし度を超えた成長は無理を呼びます。日本には「足るを知る」という言葉があります。自分に必要な物を知っていると言う意味です。人間が一人生きて行く為の物質はそんなに多くないはずです。こんなに電気に頼らなくても人間は生きて行けるはずです。「原子力」という、人間が最後までコントロールできない物質に頼って生きて行く恐怖を味わった今、再生エネルギーに大きく舵を取らなければ、子供たちに未来を手渡すことはかなわないと感じています。
私たちはもっとシンプルでつつましい、新しい「幸福」というものを創造する力があると信じています。がれきの荒野を見た私たちだからこそ、今までと違う「新しい日本」を作りたいと切に願っているのです。今あるものを捨て、今までやって来たことを変えるのは大きな痛みと勇気が必要です。しかし、今やらなければ未来は見えて来ません。心から笑いながら、支え合いながら生きて行く日本を、皆さまにお見せできるよう努力しようと思っています。そしてこの「絆」を世界の皆さまともつないで行きたいと思っています。